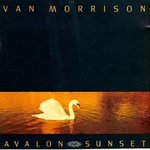Elvis Costelloのアルバムで初めて聴いたのは1979年のArmed Forcesで14歳のときだった。Costelloは25歳。ロックを聴き始めたころに夢中になったのは、Costello、Talking Heads、そしてIan Dury&The Blockheadsだ。Talking Headsは初めて行ったコンサートだった。前座はプラスチックス。Ian Duryには大学になってコンサートに行った。Elvis Costelloも何度か見に行った。だが、Get Happy以後、I wanna be lovedのヴィデオクリップを見るまで、Costelloからはかなり遠ざかっていた。New Waveを過ぎてからのCostelloと自分の趣味とが合わなくなっていたのだ。そのCostelloを再認識したのがこのKing of Americaだった。Costelloは32歳。
Elvis Costelloのアルバムで初めて聴いたのは1979年のArmed Forcesで14歳のときだった。Costelloは25歳。ロックを聴き始めたころに夢中になったのは、Costello、Talking Heads、そしてIan Dury&The Blockheadsだ。Talking Headsは初めて行ったコンサートだった。前座はプラスチックス。Ian Duryには大学になってコンサートに行った。Elvis Costelloも何度か見に行った。だが、Get Happy以後、I wanna be lovedのヴィデオクリップを見るまで、Costelloからはかなり遠ざかっていた。New Waveを過ぎてからのCostelloと自分の趣味とが合わなくなっていたのだ。そのCostelloを再認識したのがこのKing of Americaだった。Costelloは32歳。
架空の物語として自分のオリジンをもう一度見つめ直すような、過去への回帰がそのころの自分の心持ちに呼応したと言えばよいだろうか。New Waveを聴き続けながらも、大学に入って、それよりも過去の、Kinks、Eno、Kevin Ayersなどを知るにつれて、いままで聴いてきた音楽が流行に過ぎなかったという気が強くした。そんなときに出されたのがこのアルバムだ。ここにはアメリカへの屈折した憧憬がある。だがあくまでも音作りは正面から切り込んだシンプルで素直な音作りだ。臆面もなく過去と対峙する姿勢が、当時のロックを聴く自分の姿勢と重なって、このアルバムは何度も何度も聴いた。その後も、LPのみならずボーナストラックにつられてCDも買い直して、ライブ収録のはいった2枚組CDなども追っかけた。
バックにアメリカのルーツ・ミュージックの演奏を代表する面々をそろえ(おそらくCostelloより年上のメンバーが多いのでは?)、アコースティックな構成で、スタンダードと言える楽曲が並んでいる。カバー曲であるDon't let me be misunderstoodなどあまりにも素直すぎて、微笑ましい程だ。7曲目Little Palacesではアコースティック・ギターとマンドリンの音だけにほぼあわせて、Costelloのせつないシャウトが聴かれる。そしてこのアルバムを一番象徴しているのはB面の1曲目American without tearsかもしれない。アコーデオンの音色が喜びと悲しみをないまぜにした微妙な感情を伝えてくれる。しかしこのB面には他にも名曲が並んでいる。Jack of all paradesやSuit of ligthsなどCostello流のポピュラー音楽の粋を集めた曲だと思う。New Waveの余韻とルーツへの憧れがうまく調和している曲ではないだろうか。
このアルバムを契機として、しばらく新譜を買い続けるのだが、SpikeにしてもBrutal Youthにしても、強く何度も聴きたいとは思えなかなった。こうして再びCostelloと離れていった。今度はいつCostelloに再会するのだろうか。
死についての考察で、最初に考えられているのは、死が非人間的なものか、それとも人間化されうるものかという点である。従来、死は「人間存在の無」に向かって開かれたひとつの扉であると考えられ、無は「存在の絶対的停止」であった。
この死の非人間的あり方が、人間化へと向かう契機は、死が内面化され、個別化され、私の「個人的な人生の現象」とみなされるときからである。死の個別化は、私のこの人生はかけがえのないものであり、二度とくりかえされることのない唯一のものだという考えをもたらすことになる。
この死の人間化に哲学的形態を与えたのが、ハイデガーであるとされる。ハイデガーにとって死とは「現存在の本来の可能性」であり、それによって、自己は全体として構成される。すなわち死の人間化は、人間を個別の、他とは取りかえのきかないものとしてとらえさせ、さらには、死によって、人生全体が個人に閉じられたものとしてとらえられるということである。そしてその個人が個人の人生を、全的に所有できていることが自由と呼ばれていると解釈される。
サルトルは、その上で死の問題の再検討を開始する。
死は非人間的な概念ではないとし、死を人間存在から切り離すことを否定する。しかしそれは死が人間存在にア・プリオリに属することを意味しない。
サルトルのいう死の個別性の可能性はあくまでも体験のレベルであれば、ということではないだろうか。死ぬ体験を最終的にするのはあくまでも私であり、この自明性は、感動を体験することが私固有であることと同じである。だれも私に代わって、愛することの感動を体験することはできない。
そしてサルトルは、死の個別性に、「世界のなかにおける私の諸行為を、それらの機能、それらの効果、それらの結果という観点から」考察することを対置する。ある女を幸福にするという「目的のため」ならば、誰かが私に「代わって」することができる。死についても同様で、祖国のために/代わって死ぬことは私の代わりの誰かでもできるのだ。したがって、死が私の死になるのは、あくまでも主観性のパースペクティブの中に限られるとする。
次の批判点は、死は期待できないということである。私の死の可能性は、「つねに考慮にいれられなければならないが」、「期待するわけにはいかない」。なぜならば、私の死の可能性は、生物的にのみ言いうることであり、この可能性はむしろ「empêchement inattendu」の側にある。ここには死は予見されえないという前提がある。生物的には一刻一刻と私たちは死に近づいているだろう。しかし死が予見されえない、死は突然襲ってくる、という立場に立てば、死が遠のく(たとえば国際会議によって平和を延長される手段が見出された)こともある。
意味づけという点から言えば、こうした死は、すべてを未決定に陥れるのであり(処女作を書いた後に死に襲われた作家が、書くべき書物としていたのはこの一作だけだったとは言えないし、彼は多くの書物を書いたとも言えない)、行為の価値が「宙ぶらりん」である以上、「死は原理的に人生からあらゆる意味を除き去るところのものである」とする。すなわち死がある以上、私たちのあらゆる行為が持ちうる価値、意味というのは、本質的に決定できないということであろう。
サルトルは、死が私の諸可能を無化するだけではなく、「死は、私が私自身についてそれであるところの観点に対する、他者の観点の勝利である」とする。つまり、人が死ぬということは、人生が中止され未決定のままになるのであるが、過去の生が相対的な意味付与を受けるのは、「他人の記憶」の中だけだということである。
サルトルに従えば、我々生者は、本質的に全ての死者と関係を持っている。その死者たちを「広い無名の集団」として把握することもあれば、「はっきりした個人」として把握することもある。この個と全体を、近親者と世界中の人間を、生者と死者との関係としてとらえることによって、隔たりを設けないこと、ここに個と共同性、他者と私の関係を考える大きな示唆があるように思う。たとえ、距離や関心に大きな違いがあるとしても、それは度合いの異なりであって、個と社会が断ち切れていないことが重要なのである。
生者は「対象的な意味づけ」を死者にほどこしていくが、それは同時に生者の人格の規定でもある。サルトルは言う。「それゆえ、対自は、自己の事実性そのものによって、死者たちに対する全《責任》の内に、投げこまれている。対自は、死者たちの運命を自由に決定することを強いられている」。また、死者とは私たち生者が生きている以上、たえず意味を更新される対自的な存在となる。
それでは生と死の差異はなにか。「生は、自己自身の意味を決定する。(...)生は、本質的に自己批判の能力、自己変身の能力をもっており、この能力によって、生は自己をひとつの《いまだーない》としてして規定する」。一方、「死は、一つの全面的な所有権剥奪をあらわすものである。(...)死の存在そのものは、われわれ自身の人生において、他者の利益のために、われわれをそっくりそのまま他者のものたらしめる」。すなわち、私たちの死後の存在は、そのまま生者たちの価値判断にゆだねられ、かつ、その価値は決定されることなく、そのつど、生者の責任において、意味を付与され続けるのだ。したがって、「私が生きているかぎり、私は、他人が私について発見するところのものを、否認することができる」のに対して、「死ぬとは、もはや他人によってしか存在しないように運命づけられること」となる。
こうしてサルトルは、死と有限性を根本的に切り離す。私たちが有限であるのは死ぬからであるという結びつきを引き離し、そうではなく、「有限であるとは、自己を選ぶことである」と定義しなおす。すなわち、私たちは、あるひとつの可能性を選択し、それにむかって自分を投企するが、それは、他の諸可能性を廃棄することであり、それによって自分とは何者かを限定するのだ。ここで、自由の行為とは、この有限性を引き受ける、ということになる。したがって、死とは、必然性でも、有限性でもなく、反対に私たちの有限性を奪いにくる偶然の事実なのだ。
 R&Bのクラシックを歌ったこのアルバムが好きな理由は、はっきりしている。オリジナルよりも、Laura Nyroが歌っているからここまで思い入れができるということにつきている。オリジナルを聞いてもここまで感動することがないのは、それはオリジナルの楽曲がどんなに素晴らしくても、ある形式、約束事にのっとっている感じがしてしまうからだ。もちろん、それは僕が聞き所を心得ていないということなのだが。
R&Bのクラシックを歌ったこのアルバムが好きな理由は、はっきりしている。オリジナルよりも、Laura Nyroが歌っているからここまで思い入れができるということにつきている。オリジナルを聞いてもここまで感動することがないのは、それはオリジナルの楽曲がどんなに素晴らしくても、ある形式、約束事にのっとっている感じがしてしまうからだ。もちろん、それは僕が聞き所を心得ていないということなのだが。
では、Laura Nyroのこのアルバムの何を聴いているのか。それは、黒人音楽へのオマージュではない。むしろ、歌いたい曲を、歌いたい仲間と歌っている喜び、その喜びから発する、曲自体の生命感だ。どんなに素晴らしい曲であっても、歌い継がれなければ、単なるクラシックになってしまう。愛情を持って歌い継ぐ人間がいてこそ、曲に新しい命が吹き込まれる。
その歌い手としてこのLaura Nyroほど、素晴らしい白人歌手はいない。たとえば3曲目のメドレー、バックヴォーカルとのかけあいのはつらつさ、後半の曲へつながるところの躍動感、5分弱でありながら、どんどん高揚してゆく流れが素晴らしい。それと対照的なのが、4曲目のDesiree。エコーのかかったヴォーカルの静謐さは、死の直前まで変わらなかったことを改めて再認識する。
このアルバムも他の好きなアルバムと同じように、白人/黒人というカテゴリーでは決して分けられない。そしてどんな定番の曲であっても、ぬくもりのあるハミングを聴かせ、豊かな声量でソウルフルに歌いあげ、変幻自在に色づけされている。音楽の歴史的・社会的背景に、歌い手の歴史的・社会的背景には決して還元できない、パフォーマンスの現在性(今、ここで、歌が歌われているという事実そのものがもつ重みのようなもの)こそに惹かれるのだ。
その瞬間を収めたこのアルバムは本当に希有な幸福感を伝えてくれるアルバムだと思う。他のアルバムも素晴らしいけれど、どれか一枚を選べと言われれば、このカヴァー集だろうか・・・
アメリカの心理学者ジョン・H・ハーヴェイの『悲しみに言葉を』は、喪の作業において、体験の言語化が、どのようにその悲しみから人を立ち直らせるのか、幅広く検証した研究書である。その意義のひとつは、悲しみから立ち直ることは、その人を成長させるといった、体験を踏み台にし、喪失を自明のものとする考え方ではなく、「喪失を意味づけることによって、何か肯定的な事柄を他者に伝えること」に重きをおいている点である。
喪において成長は必要不可欠ではない。それよりもむしろ他者とのつながり、ある場所を共有すること、そしてさらにはそれが何らかの共感(理解ではなく)へと至ることが、喪を避けることのできない必然として生きる人間にとって重要なことなのだろう。
こうした喪の意味づけが、たとえば精神療法において、その人間の生の尊厳を回復するという意味においてなされる限り、意味づけは、慎重にそして最大限の思慮をはらってなされるべき営みであろう。
ハーヴェイは様々な喪失体験を挙げているが、ここで考えたいのがホロコーストと戦争における喪失体験である。この喪失体験は、いかにこうした惨禍が起きないようにするのか、すなわち個人の回復の次元を超えて、私たち人間全体の課題としてここでは挙げられている。
戦争においては個人の体験と、歴史的意味がときに激しく緊張関係を持って切り結ぶことになる。心的外傷が明るみに出されたのも、戦争に狩り出された兵士たちの戦争体験からである。ハーヴェイは戦争体験者たちの証言を取り上げながら、喪にことばを与える彼らの言動に大きな尊厳を与えている。たとえばつぎのような具合に。
恐ろしかったのは確かです。でも、崇高な大義のために戦っていることがわかっていたので、恐怖に打ち克つことができたのです。
自分自身よりもほかの人間のことを思いやる。誰かのために自分の命を捨てることができるーこれが勇気というものでしょう。
これはノルマンディー上陸作戦に参加した兵士の証言であり、50周年の記念式典に際して、ハーヴェイ自身が立ち会って聞いた声である。この声にたいしてハーヴェイは「こうした記念行事は、(...)新しい人生、意味、希望を含み込むことになるのである」と述べている。(以上、引用も含め、『悲しみに言葉を』p.190-191.)
記念するとは、喪の行為に対する50年たってからの「新しい意味が付け加えられた」ということだ。ハーヴェイは続けて、この新たな慰霊碑は、人々の「集合的な記憶のイメージそのものだ」と付け加えている。
だがここでさらに付け加えて言わなくてはならなかっただろう。「集合的な記憶は、歴史とは異なる」と。「集合的な記憶は、体験の正当化には役立ち、それがひいては個人に希望をもたらすかもしれないが、それは、あらゆる正当化は歴史の営みとは本質的に異なり、無反省な混同をときにはもたらしてしまう」のだと。
私たちは歴史と記憶とを混同してはならないと思う。歴史とは出来事を人間の共同性の次元でとらえたものだと、おおまかに言ってしまうならば、歴史とは、記憶に依拠することが、個人がその体験の記憶を想起することが、そのまま他者の記憶と接触し、交渉することが必然となる場所である。この他者とどのような形であれ関係性を成立させてしまうのが、歴史という共同性の必然ではないか。そうでなければそれは歴史という名では語れないだろう。
戦争体験においては、個人の自らの体験の意味づけが、歴史という共同性の確立において否定されるということがおきる。それは、戦争が、死者の死を蹂躙し、生者の生をも否定する、その意味で人間性を破壊する出来事であることを訴えている。だからこそ戦争の記憶は時に隠蔽され、だからこそ、個人の証言が大きな意味をもつ。この個と共同性の記憶と意味づけをめぐる矛盾こそが、戦争の歴史の難しさだ。死の問題を避けない以上は、この矛盾は必ず私たちの前に立ち表れてくるのではないか。
この論議を、アイマンの記憶についての考察を助けにして考えてみたい。
第6章では、それまでのロックやワーズワースを引用しながら想起とアイデンティティの連関を探究したあと、この同じ連関を社会学、歴史学において検討している。ニーチェ、アルヴァックス、そしてノラの名前を挙げたうえで、かれらの記憶理論に、「想起の構成主義的で、アイデンティティを確保する性格」が強調されているとする。
想起・構成・アイデンティティと個人と共同性の歴史意識をめぐる問題がこの三語によってかなり明らかになると思われる。
想起とは、フロイトの事後性によって説明されている。事後性とは、「知覚された対象は、想起の行為において初めて、つまり、場合によっては数年後あるいは数十年後になって初めて解釈される」という意味である。「フロイトは、記憶の痕跡(注:これは全体を持たない破片、意味づけを欠いたイメージとして理解できるだろう)を活性化することを書き換え」と呼んだが、体験の50年を経ての意味づけはまさにこの書き換えであり、戦争の知覚は、50周年の記念行事によって、解釈され直されるのだ。
構成とは、下記にみる機能的説明で整理されているように、「ある部分を想い起こし、ある部分を忘れる」という「選択的」な振る舞いによって、想起が成立することを意味する。
そしてアイデンティティとはまさに、この想起の構成主義は、アイデンティティを保証する重要な作用だということだ。戦争体験者は、みずからの体験をまさに構成主義的に想起することによって、みずからの生を意味づけ、人生を肯定する姿勢が生まれてくる。
さらに、この想起の構成主義は、個人の想起のメカニスムだけではなく、この著書の中心的課題である文化的記憶についてもおなじ作用が働くことが指摘される。
今ここで、アスマンがモデルとして提出している記憶の二つの作用、機能的記憶と蓄積的記憶を整理しておこう。ただし、アスマンの力点はこの二つの記憶の間でたえず流通が行なわれているとするパースペクティブに置かれていることに注意すべきである。
機能的記憶とは、住まわれた記憶とも言われているもので、i)集団、機関、個人であれ、何らかの担い手と結びつき、ii)過去、現在、未来を橋渡しし、iii)選択的な作用をもち、iv)アイデンティティの輪郭を描き、行為に価値を与えるとされる。個人の記憶として考えれば、「思い出や経験を一つの構造につなぎ合わせ」、「形成的な自己像として生を規定し、行為に方向性を与える」。したがってある主体(個人であれ、共同体であれ)は、機能的な記憶によって、過去を取捨選択し、ひとつの時間性を描けるよう出来事を再構成し、それを人生の価値基準としてゆくのだ。
一方蓄積的記憶とは、i)特定の担い手とは切り離され、ii) 過去、現在、未来は切り離され、iii)価値付けの序列はなく、iv)真実を志向するがゆえに、価値や規範が保留されている。つまり、この記憶にとって過去とは、「無定形な集塊」であり、「使用されず融合されていない思い出の暈」とされる。ただし、重要ななのはこの記憶は機能的な記憶と対立するのではなく、一部は無意識のままとどまるように、いわば背景として沈潜しているということだ。いまだ意味づけられることなく、使用価値が与えられることなく、しかし消え去ってはいないアーカイブなのだ。これは<人類の記憶>と呼ばれているが、むしろ記録と呼んだほうがよいかもしれない。
では機能的な記憶の役割とは何か。ここで取り上げたいのが、「正当化」である。「正当化は、公的あるいは政治的な記憶の最優先の関心事」だとされる。体験者の想起による、過去の意味づけは必ずこの正当化をはらんでしまうのだ。ハーヴェイの上にみた指摘は、まさに意味づけによる喪からの回復の物語に、個人の生の肯定を見るゆえに、この記憶が果たしている、過去の体験者の自己への、そしてその体験者が参与した戦争行為の、正当化をまったく看過してしまっているのだ。
そしてもう一点、なぜ機能的な記憶の役割が歴史を形成しないのか。これについてはアスマンが引いているアルヴァックスの考察が役立つだろう。それは、集合的な記憶が、出来事のシンボル化に過ぎないからだ。シンボル化に過ぎない以上、まさにアルヴァックスが言うように、「集合的記憶は、それが結びついている集団と同様に常に複数形で存在する」のである。これは、歴史の記憶、すなわち「単数形で存在」することと対立する。歴史が純粋に単数形で存在することは、もちろん前提とはできない。ただ、ここで確認したいのは、集合的記憶とは、もしそれが歴史とされるとならば、その歴史は、集団の利害、行為の正当化、相対主義的な歴史観を必ず孕んでしまうということだ。もっと単純に言ってしまうならば、集合的記憶はシンボル化=この戦争は何だったのかという問いへの、事後的に構成された答えなのだ。
それに対して、蓄積的記憶は歴史に何らかの寄与をしうるのだろうか。アスマンは蓄積的記憶は、「文化の知識を更新するための基本的資源」であるとする。この二つの記憶が間の境界が「高度に透過的」でなくてはならないという。しかしそれがいかに可能で、どのようにその透過性が保証されるのか。そこには「検証」が必要となるだろう。この検証こそが歴史的事実と呼ばれるものではないだろうか。それがシンボルや選択といういわば言語化において避けることのできない作用を認識しながらも、それを絶えず修正していく歴史的な理性の謂いとなるのではないだろうか。
だが、これだけでも十分ではない。こうした考察を深めた後にもう一度証言者のディスクールに戻ってこないといけない。利害をもたない証言者の記憶の物語について、それが検証に耐えうるかどうかということも含めて、さらに考えなくてはならない。そこには倫理が最終的に要請されるのだろうか。
 86年に限定盤としてだされ、02年にリイシューされた吉田美奈子のミニ・アルバムである。吉田美奈子の活動は大きく何期かに分けられると思うが、このミニ・アルバムの色調は、95年のExtreme beautyや96年のKeyに近い。モンスター・イン・タウンを絶頂とする時期は、そのきらめく高音の素晴らしさに引き込まれるのだが、この90年代後半は、そのなめらかさを保ちながらも、低音の落ち着きが、曲にやさしさと静謐をもたらしてくれている感じがする。2曲目Chrismas treeの「街の灯が輝き増すたびに 魅せられる程の物語りがある」という部分など、低音ヴォイスの充実を感じる。4曲目Shadows are the througts(of the radiance)の「拾い集めて 心に停める」という部分もそうだ。この曲などは、「時よ」や「風」を彷彿とさせるけれど、ずっと大人なアレンジだ。
86年に限定盤としてだされ、02年にリイシューされた吉田美奈子のミニ・アルバムである。吉田美奈子の活動は大きく何期かに分けられると思うが、このミニ・アルバムの色調は、95年のExtreme beautyや96年のKeyに近い。モンスター・イン・タウンを絶頂とする時期は、そのきらめく高音の素晴らしさに引き込まれるのだが、この90年代後半は、そのなめらかさを保ちながらも、低音の落ち着きが、曲にやさしさと静謐をもたらしてくれている感じがする。2曲目Chrismas treeの「街の灯が輝き増すたびに 魅せられる程の物語りがある」という部分など、低音ヴォイスの充実を感じる。4曲目Shadows are the througts(of the radiance)の「拾い集めて 心に停める」という部分もそうだ。この曲などは、「時よ」や「風」を彷彿とさせるけれど、ずっと大人なアレンジだ。
もともと自主制作盤だったせいか、アレンジがずっとシンプルなのだろう。3曲目のゴスペルテイストの曲や、5曲目のヴォーカルの多重録音など、趣向はこらされているのだが、とても手作り感があって、聞いていて落ち着く。
昔クリスマス・イヴに編集テープを作っていて一晩を過ごしてしまった先輩がいたが、クリスマス・イヴに聞くに最高の一枚がこのBellsだと思う。宗教的な情熱や敬虔さが、音楽にソウルを吹き込んだことは否定しない。しかし神を歌わずとも、曲の美しさに感動し、心が洗われることがある。吉田美奈子の音楽にはそうした質素な充実があるのだ。ただ、そこに音楽があるだけでいい。その声があるだけでいい。それはなにものの対象としない純粋な祈りなのだ。
ゼーバルトは言う。「歴史的ないし文学的描写によって、空襲の恐怖を公共の意識にもたらすことに私たちは成功していないのではないか」と。この講演では、歴史的な事象にたいして、文学はどのような表現をもちうるのか、そして文学的な表現をいままで戦後ドイツはもちえなかったのはなぜなのか、が主題となっている。
ゼーバルトは、戦後、ドイツが戦時下において、ほとんど正当化される理由もなく無差別な空襲を受けたこと、それも徹底的な絨毯爆弾によって、市民も巻き添えにした潰滅的な破壊が国土においてなされたことが、これまでほとんど書かれなかった事実を指摘する。それはあたかも健忘症にかかったかのような症状とでも言える。しかしゼーバルトが語るのは次のようなことではない。「空襲について語ろうとするのは、戦争の加害者は同時に被害者でもあった、ところが加害者としてのナチスの行為があまりにもひどいものであったため長らくドイツは自らが被害者でもあり、それを主張する権利をもっていない、被害を訴えることはタブーであるために長らく沈黙してきた」云々...したがって、次のような主張とは全くもって異なっている。
「もうそろそろ我々も被害者であったのだ、連合軍から悲惨な目にあわされたのだ、ということを主張してよいのではないか」。
ゼーバルトが「告発」といってもよいほど強く、かつ執拗に訴えるのは、それら沈黙は自重や遠慮ではなく、むしろ自らその過去を封印することで、戦後の復興を成し遂げ、また自信を回復してきたのだ、という点である。それはすなわち、心理の巧妙なすりかえがあったのだということだ。たとえば戦後すぐドイツではオペラが上演され、三島憲一『戦後ドイツ』によれば、「ベルリンで毎晩200個所以上で芝居が上演され、毎日最低六つの演奏会があり、そして、オペラハウスも休演することがめったになかった」とのことである。こうした戦後のドイツの風景にたいしてゼーバルトは、「人類の歴史において、このような演奏をおこなうのはドイツ人のみであり、これほどの苦難を耐え抜いたのもドイツ人のみであるといういびつな誇りに、彼らの胸はふくらみはしなかったか」と。いびつな誇り、その心持ちが戦後の荒廃したなかでドイツ人に新しい生を歩ませることになる。三島憲一はそのあたりの事情を「このあたりの変わり身の早さは、ドイツ人全体にも共通している」と、辛辣な表現で指摘している。ゼーバルトは「当時のドイツほど、知りたくないことを忘れる人間の能力、眼前のものを見ずにすます能力が端的に確かめられた例は希有であったろう」と述べている。そしてその実体は「抑圧のメカニズム」の働きなのである。
では文学は何をしてきたのか。あるいは言語は何を表象してきたのだろうか。いや問いとしては、なぜ文学はその描写をもちえなかったのか。言語はどんな表現に逃げをうったのか、と問うほうがより的確だろう。
まずそもそもは、上記で言われた「変わり身の早さ」によって、そもそも描写の対象にしなかったということが挙げられる。そしてもうひとつは言語の表象の困難さという問題である。
空襲とはひとつの言語に絶する出来事である。それは「生の形では描写を拒む現実」である。人が「思考や感覚の許容量」を超える体験をしたとき、その表現は、思考や感覚が麻痺しているゆえに、ほとんどが紋切り型の表現になってしまう。それによって、現実と言語の間には大きな齟齬が生まれてしまうのである。それは同時に、理解を絶する体験を本当に表象するところまでいかず、「蓋をして毒消し」をしてしまうことになる。
だが、最大の問題は、表象が不可能だったのではなく、もちろんきわめて難しいとはいえ、それがタブーだった点にある。空襲を表象しようとする試みは、戦後復興のなかで誇りを取り戻そうとしてきたドイツ国民に対して、その誇りによって戦後、精神衛生を保ってきたドイツ国民に対して、じつは壁の裏側には、おびただしい死者、死臭、残骸、荒廃、血と汚物、そうした我々の精神に混乱をもたらす事実が、いたるところに転がっていることに言及せざるをえないからである。ゼーバルトはレーディヒという忘れ去られた作家を持ち出し、かれの「嫌悪と嘔吐を催させる」文体が、戦後に忘却の上に成り立つ戦後の文化的記憶から締め出されたのは、「防疫ラインを破るおそれがあったからだ」と述べている。空襲について語ることは、それが我々を忘却へと葬ってしまうほど、紋切り型でしか表現できないほど、我々の経験を超えた出来事である。しかしもしそれについて語りうるならば、それが同時に戦後ドイツという過去の忘却の上に今まで成り立ってきた文化が実は幻想であることを、それゆえに書くことがその幻想から覚まし、時間の寸断(戦前と戦後)というまやかしを暴き出すことになること、これこそが恐怖であり、ドイツの理性はその恐怖を今まで封印にしてきたことを、ゼーバルトは告発するのだ。
しかしでは、どのような表象ならば語ることが可能なのか。ゼーバルトが挙げる数少ない成功例がノサックである。ノサックは「非人間性と紙一重の、倫理的感覚の欠如」を書き残す。
文学が歴史と異なってできることはこの点だ。文学は、歴史と異なり、ひとつの断片、物語化されえないひとつの断片でさえ、言語として表象する可能性を持っている。それが個人の視野におさめられたものでもかまわない。ただし、それが個人にとどまってしまえば、それは文学とならず、日記や覚書となろう。また装飾を交えてしまっては神話となってしまうだろう。文学とは、あくまでも「虚飾をまじえぬ客観性に裏打ちされた真実」を語らねばならないのだ。それでこそ、ひとつの断片であっても、他者とつながる契機が生まれるのである。歴史であれば、個の断片は、普遍性へと回収され、歴史的意味を帯びる。文学はこの大きな意味とはことなる、個でありながら、他者と了解可能な表象を探る言語の実践なのではないだろうか。
だからこそゼーバルトは「私の人生と、空襲の歴史とが交錯する点」をいくつも述べてきたのではなないだろうか。
 大学の学食で、大学院生のmrt君と昼飯を食べながら、日本の音楽の話になった。年齢のわりには古いものをよく知っている彼と、年齢の割には新しいものをかろうじて知っている僕の間には、非常に親密な「わかる」感覚がある。この日も「エグザイルにはメンバーが何人いるかわからないし、アンジェラ・アキはこちらが気恥ずかしくなってしまう。でサザンにたいしてはまったく無関心でしかいられない、好き嫌いの次元以前に、視野に入りようがない」ということで、大いに盛り上がってしまった。平成生まれがまわりにちらほらいるなかで、ぼくらの話はほとんど意味不明だろう。
大学の学食で、大学院生のmrt君と昼飯を食べながら、日本の音楽の話になった。年齢のわりには古いものをよく知っている彼と、年齢の割には新しいものをかろうじて知っている僕の間には、非常に親密な「わかる」感覚がある。この日も「エグザイルにはメンバーが何人いるかわからないし、アンジェラ・アキはこちらが気恥ずかしくなってしまう。でサザンにたいしてはまったく無関心でしかいられない、好き嫌いの次元以前に、視野に入りようがない」ということで、大いに盛り上がってしまった。平成生まれがまわりにちらほらいるなかで、ぼくらの話はほとんど意味不明だろう。
では日本のロックにだれがいるだろうか。ここで名前がのぼるのが若い割にはロックの歴史をしっかり咀嚼している「くるり」。というわけで、その夜家に帰って「ワルツを踊れ」を聞いてみた。I-tunesをみたら、なんと最後に再生したのは去年の12月・・・結局そう、最近のくるりは少し聞くに耐えないところがあるのだ・・・たくたくのライブはとてもよかったが。
では何が一番再生されているか。それがこのThe Guitar plus meという日本的な文脈からかなり遠いところにいるミュージシャンである。今回の新譜も今までとまったく変わらない。歌詞はすべて英語で、対訳つき。この新譜は大手コロンビアからの発売だが、音数は今まで通り、きわめて質素である。1曲目のhighway througt desertから、まったく今までの音作り同様のやさしいアコースティックギターが流れてくる。音を重ねながらもこのすきすき感があるところがなんともいえない魅力だ。
また3曲目school bus bluesのようなコード進行、ヴォーカルも音の階梯を降りてゆくような、せつなさ、それがI can't see your smileという歌詞と重なる。
次のBlue printもほぼギターの弾き語りで、そこに多重ヴォーカルが重なる。
YouTubeでみたthe guitar〜は超絶ギター少年だったが、アルバムではそこまでテクニックに走ることはない。fortune-tellerには途中でギターソロが挿まれるが、それもテクニックを聴かせるものではなく、あくまで曲の流れの一場面だ。それよりも一本一本の弦の音色がここまで違うのかと教えてくれる、丁寧な演奏である。winter afternoonは、リフが幾度ともなくくりかえされ、そこにハミングのようなヴォーカルが重なってくる。その溶け合いかたが、とてもやさしい。
1stアルバムから基本的には何の変化もない。アルバムジャケットも音の構成も。ギターの肌触りと、人工音の類い稀なフュージョンといえばよいだろうか。最後の曲horizonはそうした人工音の中に、アコースティックギターが流れてくる魅惑的な構成だ。イントロを3秒聴けば、すぐに彼の音楽だとわかる。
そして詩的喚起力の強さーそれが、作品に淡い物語性を生んでいる。それもこのミュージシャンの魅力であり、アルバムを通して聴きたくなる強い磁力のもとであるのだろう。
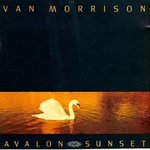 Van Morrisonのアルバムにはアストラル・ウィークス、ムーンダンスといった初期の傑作群がある。これは誰もまねしようがないし、Van自身再演することなど不可能なほどオリジナリティにあふれたアルバムである。白人によるソウルの咀嚼。かつロックというジャンルがあらゆる他のジャンルを咀嚼しつくすエネルギーをたずさえたジャンルであることを証明してくれるアルバムだ。またライブにもIt's too late to stop nowのようなソウルフルなアルバムがある。しかし、Van Morrisonのアルバムは70年代だけではない。80年のInto The Musicなどずいぶん聞きやすいが、魂の充実を感じさせる好盤である。そして80年代終わりにだされたこのAvalon Sunsetも時代の制約をはるかに超えたアルバムに仕上がっている。
Van Morrisonのアルバムにはアストラル・ウィークス、ムーンダンスといった初期の傑作群がある。これは誰もまねしようがないし、Van自身再演することなど不可能なほどオリジナリティにあふれたアルバムである。白人によるソウルの咀嚼。かつロックというジャンルがあらゆる他のジャンルを咀嚼しつくすエネルギーをたずさえたジャンルであることを証明してくれるアルバムだ。またライブにもIt's too late to stop nowのようなソウルフルなアルバムがある。しかし、Van Morrisonのアルバムは70年代だけではない。80年のInto The Musicなどずいぶん聞きやすいが、魂の充実を感じさせる好盤である。そして80年代終わりにだされたこのAvalon Sunsetも時代の制約をはるかに超えたアルバムに仕上がっている。
初期のアルバムはLaura Nyroと同じくこちらに緊張を迫るが、この時期のアルバムはすこし肩の力を抜いて、楽しみながら聴けるのがよい。どの曲もオーソドックスな感じがするが、じっくり練られているし、多少「お決まり」であってもVan Morrisonならば許してしまおうという気になる。
とくに4曲目。Have I told tou lately that I love youの甘さはいったい何だろう。叙情に押し流されてしまいそうな曲ではあるが、Van Morrisonの落ち着いた懐の深い歌い方に、素直に感動するのだ。Take away my sadnessという甘ったるい歌詞も一緒に口ずさみたくなる。そんな静かな魅力に溢れた曲が並ぶ。ストリングスもまったく大げさには聞こえない。
7曲目のWhen will I ever learn to live in Godもよてもよい曲だ。しかしなぜ神を歌うのだろうか。それはゴスペルのような神と強い関係をもつ音楽との共通性ゆえだろうか。たしかに曲の最後女性コーラスとサビを繰り返すところなど、神へのゴスペル讃歌と言えなくもない。
それ以外にも美しい曲が収められている。ストレートにR&B色の強い曲を聴くよりも、実はこのAvalon Sunsetのような、控えめであっても、じっくり歌を聴かせてくれるVan Morrisonが好きだ。80年代のうすっぺらな音楽が席巻するなかで、ここまで歌を大切にしたアルバムを出していたことに驚く。
ようやく40枚ほどレヴューを書いてきて80年代のレコードを初めて紹介することができました。でもこのアルバムはもっとも80年代らしくないアルバムだけれど・・・
 『血の轍』は、おそらくディランの数々の素晴らしいアルバムの中で、「歴史的名盤」、ロックの歴史を刻む記念碑的アルバムではないだろう。むしろきわめてプライベートな愛聴盤として、ごく個人的に孤独のうちに聴かれながら、実に多くの人々の心をとらえきたアルバムと言えるだろう。きわめて個人的な事柄が、大きな普遍性をもつ、その意味でこのアルバムは、名盤である。
『血の轍』は、おそらくディランの数々の素晴らしいアルバムの中で、「歴史的名盤」、ロックの歴史を刻む記念碑的アルバムではないだろう。むしろきわめてプライベートな愛聴盤として、ごく個人的に孤独のうちに聴かれながら、実に多くの人々の心をとらえきたアルバムと言えるだろう。きわめて個人的な事柄が、大きな普遍性をもつ、その意味でこのアルバムは、名盤である。
これだけ美しい曲が並んでいるのに、好きな女の子にあげる編集テープにはどの曲も入れられない。それがディランのヴォーカルの魅力。みうらじゅんが書いていたが、なんでこんなダミ声の唸るような歌が、心を引くのか。本当にそう思う。中学生のときに聴いたディランは、とにかく曲という体裁を感じられなくて、ブツブツ言っている感じがして、聴けなかった。
ディランをあらためて聴いたのは大学時代の先輩の最も好きな曲が、このアルバムにおさめられている、You're gonna make me lonesome, when you goとIf you see her, say helloだというのを知ったからだ。
このアルバムにはディラン自身の別離から始まる、喪失やあきらめや、人生へのまなざしといったものが痛々しいほど散りばめられている。
Simple Twist of Fate「運命がくるっと回る」とでも訳せばいいのか自信がないが、
彼が目をさますと 部屋はからっぽ
彼女はどこにもいなかった
彼はかまうことないと自分に言い聞かせ
窓を大きく開けて
空虚を中に感じた
それは彼がかかわることのできない
運命のひとひねり
朝目を覚ます。それは毎日訪れるささいな事柄だ。昨日とも明日とも変わらない。しかしそこではすでに運命がひとひねりしてしまっている。今日からは空虚なのだ。この喪失がこのアルバム全体を浸している。Lonesomeからsay helloまで心はどのような軌跡を描くのだろうか。それが描かれているのがこのアルバムである。
その軌跡とは「血の轍」である。心から血を流すディランの痛ましさが、ロックという音楽に乗って、同じ心を持つすべての人を訪れるのだ。
 Elvis Costelloのアルバムで初めて聴いたのは1979年のArmed Forcesで14歳のときだった。Costelloは25歳。ロックを聴き始めたころに夢中になったのは、Costello、Talking Heads、そしてIan Dury&The Blockheadsだ。Talking Headsは初めて行ったコンサートだった。前座はプラスチックス。Ian Duryには大学になってコンサートに行った。Elvis Costelloも何度か見に行った。だが、Get Happy以後、I wanna be lovedのヴィデオクリップを見るまで、Costelloからはかなり遠ざかっていた。New Waveを過ぎてからのCostelloと自分の趣味とが合わなくなっていたのだ。そのCostelloを再認識したのがこのKing of Americaだった。Costelloは32歳。
Elvis Costelloのアルバムで初めて聴いたのは1979年のArmed Forcesで14歳のときだった。Costelloは25歳。ロックを聴き始めたころに夢中になったのは、Costello、Talking Heads、そしてIan Dury&The Blockheadsだ。Talking Headsは初めて行ったコンサートだった。前座はプラスチックス。Ian Duryには大学になってコンサートに行った。Elvis Costelloも何度か見に行った。だが、Get Happy以後、I wanna be lovedのヴィデオクリップを見るまで、Costelloからはかなり遠ざかっていた。New Waveを過ぎてからのCostelloと自分の趣味とが合わなくなっていたのだ。そのCostelloを再認識したのがこのKing of Americaだった。Costelloは32歳。