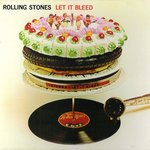今から20年も前。トッド・ラングレンの再発の頃だったか、その話を友人にしたら「こんなアルバムもあるよ」と紹介してくれ、CDまで貸してくれたのが、Hall&Oatesの「War Babies」だった。そのままCDは返さずじまいで今も手元にある。このアルバムは、彼らのサードにあたり、ソウルな風味にロック色を入れたいと思った本人たちが、トッドにプロデュースを頼んで制作された。オーバー・プロデュースで有名なトッドだが、このアルバムもかなり激しいアレンジになっている。
今から20年も前。トッド・ラングレンの再発の頃だったか、その話を友人にしたら「こんなアルバムもあるよ」と紹介してくれ、CDまで貸してくれたのが、Hall&Oatesの「War Babies」だった。そのままCDは返さずじまいで今も手元にある。このアルバムは、彼らのサードにあたり、ソウルな風味にロック色を入れたいと思った本人たちが、トッドにプロデュースを頼んで制作された。オーバー・プロデュースで有名なトッドだが、このアルバムもかなり激しいアレンジになっている。
それに対してこのセカンドは、まだ本人たちの手探り感というか、もがき感が残っていて、甘酸っぱさをかきたてている。特に裏ジャケの二人の表情はやるせなさが漂っている。その後の哀愁を帯びてはいてもパンチの効いたロック調とは異なる、エルトン・ジョンに似た青春の青さを感じさせる内省的な音楽だ。1曲目のハーモニーの繊細さ、高音の美しさがこのアルバムの瑞々しさを伝えてくれる。アコースティックソウルの肌触りとしては、たとえば5曲目の、弾き語りからヴォーカルが重なるI'm just a kidの冒頭、そしてサビのハモリなどに十分感じられる。
ちなみにこのアルバムにはBernard Purdieなど一流ミュージシャンが参加しているが、確かにアレンジが素晴らしい。2曲目のフックの効いたドラム(これはPurdieではないが)などセンスの良さが光る。
ここには彼らの初期のヒット曲She's Goneが入っている。10ccのようなしっとりとした曲調から、親しみやすいサビに入り、そしてサックスの音色へと、とても聞きやすい構成だ。AORやディスコサウンドへ行く手前の、というかもうすぐそこにひかえているような音作りだが、たとえばはずかしい音色のギターの音にもならずあくまでアコースティック、機械音の打ち込みのようにならず、あくまでも肌ざわりを大切にした、手作りの音楽だ。
名盤はこんなところに眠っている。
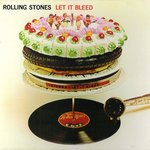 バンドの音だが、スタジオミュージシャンすべて含めてのバンドの音になっている。それによってアルバムの雰囲気も、一曲一曲も、決まったジャンルにはおさまりきらない、スケールの大きさを獲得している。血統のない雑種としての音楽だ。そしてそこには、音楽自体を創造してゆこうとする高い志がある。
バンドの音だが、スタジオミュージシャンすべて含めてのバンドの音になっている。それによってアルバムの雰囲気も、一曲一曲も、決まったジャンルにはおさまりきらない、スケールの大きさを獲得している。血統のない雑種としての音楽だ。そしてそこには、音楽自体を創造してゆこうとする高い志がある。
バンドは、それぞれが強い個性を発揮しながらも、決してバラバラにならずひとつのエネルギーを作ってゆくから面白い。ブライアン・ジョーンズが抜け、ミック・テイラーが加入するという過渡期に制作されたこのアルバムには、メンバー交代の不安定さなど感じられない。それどころか、アメリカのミュージシャンが入って、様々なバックボーンを持った音が混じりあい、そこから強い緊張感をもった音楽が生まれているのだ。
1曲目からMary Claytonの力強いヴォーカルにからみつくようにミックのハープが響き、ニッキー・ホプキンスのピアノが跳ねるなか、曲がどんどん進行してゆく。2曲目のロバート・ジョンソンのカバー曲に参加しているのはRy Cooder。埃が舞い上がるような寂寥感の演出が実にうまい。
ここにおさめられているのは、ジャンルを無視したポピュラリティあふれる曲ばかりだ。3曲目はフィードルから始まる、ブリティッシュロックと南部アメリカンロックの混合が見事なCountry Honk。4曲目はディープなスワンプロックのコード進行から始まり、ぐいぐいと疾走してゆくスピード感見事な一曲。最後のドラムのシンバルがひたすらたたかれまくられるのがかっこいいです。そしてA面最後のLet it bleedは、クレジットをみると、このスライドはキースが弾いている。Ladies&GentelmensのDVDではミック・テイラーの職人技の微動だにしない姿勢から生まれるスライドギターの音が、実にバンドの要となっていたが、この曲のスライドはテイラーに負けていない...
B面1曲目は、ふたたびねちっこいブルース。最後のYou can't always get what you wantは「地の塩」に続くアカペラ路線を拡大した曲。アル・クーパーのホルンに、アコースティックギター、そしてヴォーカルが入り、一気に曲が盛り上がっていく。アル・クーパーはピアノ、オルガンも担当し、コーラスの編成はジャック・ニッチェ。これこそストーンズの真骨頂ではないだろうか。どこまでも音を厚く塗り重ねて、猥雑とさえいえるような、いろんな音の混ざり具合こそストーンズの音楽を聞く醍醐味だと思う。ロックの雑種としての魅力に強くひきよせられるのだ。ロックだと思う。
 もはやおぼろげな記憶しか残っていないのだが、ユーミンが、自分の曲を校歌にした瀬戸内海の小学校を訪ねる番組を見たことがあった。小学生たちと交流をしたユーミンの目には涙があふれていた。自分の曲を大切に歌ってくれる子どもたちと、その子どもたちが暮らす海の風景に囲まれて、自然のなかで自分の歌が歌い継がれてゆくことの喜びゆえの涙だったのではないだろうか。
もはやおぼろげな記憶しか残っていないのだが、ユーミンが、自分の曲を校歌にした瀬戸内海の小学校を訪ねる番組を見たことがあった。小学生たちと交流をしたユーミンの目には涙があふれていた。自分の曲を大切に歌ってくれる子どもたちと、その子どもたちが暮らす海の風景に囲まれて、自然のなかで自分の歌が歌い継がれてゆくことの喜びゆえの涙だったのではないだろうか。
校歌になったのは「瞳を閉じて」。「遠いところへいった友だちに 潮騒の音がもう一度届くように 今 海に流そう」。今は一緒にいる小学生たちも大きくなればやがて島を離れていくだろう。しかしどれだけ遠くに離れても、この育った海の潮騒のことをいつまでも覚えていてくれるように、そしてどれだけ遠くに離れていても、ずっと友だちのままだということを伝えるために、ガラスのびんを海に流す。自分の書いた詞が、子どもたちの心のよりどころになっていく。それを実感してユーミンは泣いたのではなかったか。
荒井由実時代の7枚のシングル、計14曲を集めたこのCDは、実に贅沢なCDだ。A面、B面関係なく、どの曲もおもわず口ずさめる親しみさと、おしゃれでありつつも「翳り」をふと感じる陰影に富んでいる。デビューシングルの「返事はいらない」のピアノ、ギターのイントロから「この手紙が届くころには」という歌いだしのメロディに驚く。ロックというにはあまりに素朴で、フォークというにはあまりに洗練されている。
そして自分がはじめて聞いたユーミンの曲「あの日に帰りたい」。その後松任谷由実という名前を見つけて、あれっと思ったことを覚えているので、おそらく荒井由実をオン・タイムで聞いていたのだろう。もっともハイファイセットのほうがなじみがあったのだが。
ところでこのCDの曲解説はだれが書いたがクレジットがないのだが、簡素な説明でほぼ曲の魅力が言い尽くされている。たとえば先ほどの「瞳を閉じて」については、「海をテーマにした数々の作品を創っているユーミンだが、すがすがしさという点ではこの曲が秀でている」。うん、その通り。
そしてシングルを集めているということで、バージョン違いが何曲もありマニアの心を満たしてくれるCDでもある。
喪の作業において赦しはどのように作用するのか。この問題を設定することは、加害者と犠牲者の関係を考えることである。ただし犠牲者とは、被害を受けた当事者の場合もあれば、その当事者の近親者の場合もある。犠牲者が亡くなっている場合、近親者が深く傷ついている場合があるからこそ、赦しは、誰が誰をどのような状況で赦すのかということがたえず問われることになる。
デリダのここでの発言は、ヨーロッパの戦後の戦争責任、南アフリカの真実と和解委員会、コソヴォ紛争など、赦しを巡る歴史的、政治的傾向を踏まえてのものである。しかしその上で、赦しは根源的に「法律=政治的なものが近づくことのできない」、その限界を超えるものとして、あらゆる制約をはずれたものとして本質的に規定される。
この問題はたとえば次の英語のタームを考えてみるとわかりやすいだろう。
赦し(forgiveness):犠牲者が復讐権を放棄する。
赦免(pardon):加害者が一切の罰から解放される。権限は加害者への懲罰権を持っている人物や制度(司法制度など)に限られている。
和解(reconciliation):被害者と加害者の関係を修復、ないし、関係を新たに創造することを言う。
(グレイビル他『アーミッシュの赦し』亜紀書房、2008, p.8)
政治的な発言の意図は、おうおうにしてこの和解にある。しかし当然ながら和解とは赦しではない。それは「償い」である。赦免とはまさに法的な領域に属するものであって、私たちが決して赦さなくても、加害者が赦免されることはあり、反対に私たちが赦しているとしても、加害者が赦免されないこともある以上、赦しと赦免は根本的に異なる概念である。
デリダは赦しの根源性を考える上で、ジャンケレヴィッチとアレントの赦しについての考察を次のように批判する。ジャンケレヴィッチの論点は二つある。ひとつは「人道に反する罪を、(...)人間を人間にするものーすなわち、赦す力そのものに対する罪を赦すことは問題になりえない」と明言した点。つまり人間を人間たらしめるもの=人間性そのものに対する罪は、赦しえないものである=時効になりえないとする点。そして赦しの本質を考える上でより重要な論点は、「罪人が赦しを求めなかったのだから、赦すことはなおさら問題になりえない」と主張したことである。これはデリダに言わせれば、過ちや改悛によって赦しが始まるとすることであり、赦しに条件がついてしまうことになる。さらにジャンケレヴィッチと同様の考えとして、アレントの『人間の条件』から「罰は、介入がなければいつまでも続いてしまいかねない何ごとかに終止符を打とうとする点で赦しと共通している」という一節を挙げ、罰することと赦すことの対称性において、「購いえないもの」、「償いえないもの」は、「赦しえないもの」であると等価に語ってしまっていることを指摘する。
しかしデリダにとって赦しの根源性が露になる地点とは、赦しえないものを赦すというアポリアの地点である。そのそも罪人が改悛したならば赦しの可能性が出てくるといったのでは、それは改悛した罪人を赦すことではあっても、罪人そのものを赦すことにはならない。こうしてデリダはジャンケレヴィッチが「救済、和解、贖罪、購い、償い」を意味するものとして赦しを考えていると批判し、赦しを次のように規定する。
「無条件の、非エコノミー的な、交換を超えた、贖罪や和解の地平さえ超えた赦し」
しかし、現実には、たとえば赦しと和解とがはっきりと区別されることは難しい。国家元首が求める赦しは実際には和解のプロセス、セラピーとほとんど混同されているとデリダは言う。しかも現実においては、人道に反する罪を罰することによって、何らかの制裁が発動され、主権国家の主権が制限されていく。そしてそれは具体的に強い国が弱い国に、物理的、軍事的、経済的に可能な場合に限って、主権の制限を行使するのである。
それでもデリダはあくまでも赦しと和解を峻別するべきであると説く。デリダは、「合目的化された赦し」は赦しではないとして、そして和解のプロセスは「健忘や喪の作業等々を経て行われる健康あるいは正常性のあの再構成」であり、赦しとは区別するべきと言うのだ。
では、政治戦略を超えて、そして「心理療法上のエコノミー」も超えて、さらには、「正常性」という意味での喪からの回復も超えて、赦しを考えるならば、赦しはどこに求められるのだろうか。デリダは次のように言う。
「一切の制度、一切の権力、一切の法律=政治的審級を超過する何ごとかが、心情に、あるいは理性に到来することを、(...)受け入れるべきではないでしょうか」
この心情とは何だろうか。デリダの本論の中心課題ではないが、この政治性から離れて、個人の心情へと移行することは、喪の作業と赦しとの関係について考えるための示唆を与えてくれるように思われる。ひとつが忘却である。法律=政治的審級においての赦しは、赦しによる喪の作業のプロセスの正常化は、忘却と等価で語られてしまうことが多い。これは赦しに名を借りた赦免に他ならない。赦しに名を借りて法的なプロセスを放棄していることに他ならない。
対して個人の心情における赦しとは決して忘却と等価ではない。そもそも加害者を赦すことと、その行為を忘れることにはいかなる相関性もないのだ。喪の状況にいる本人に「忘れなさい」と忘却を促すことは、正常化のプロセスとは関係がないどころか、むしろ逆の効果しか生まないのではないか。個人の心情のなかでは忘れることなく、赦すことが可能である。忘れることなく、過去を再構成してゆくことも可能である。そもそも赦すことは喪の作業に終止符を打つことではない。そして根本的に赦しは、法律=政治的審級のように、「尺度によって測りうる」ものではないのだ。
無条件の赦しは、だからこそ、政治的制約を超えて考えるべき主題となる。最後にデリダは困難な問いとして「無条件だが主権なき赦し」を思考すべきとする。主権的権力を超えた赦しは、おそらくは個のレベルと共同性のレベルの差異を消し去る地点において、措定された概念であり、それをデリダは「来るべき民主主義」と呼んでいる。はたしてそのような赦しを思考しうるのか。この問題は、おそらくは時間の推移の中で何を記憶し、何を忘却とするのか、喪失したものをいかに再構成してゆくのかという課題を抜きにして、考えることは不可能であろう。
(ジャック・デリダ「世紀と赦し」現代思想2000年11月号、鵜飼哲訳)
 今から20年も前。トッド・ラングレンの再発の頃だったか、その話を友人にしたら「こんなアルバムもあるよ」と紹介してくれ、CDまで貸してくれたのが、Hall&Oatesの「War Babies」だった。そのままCDは返さずじまいで今も手元にある。このアルバムは、彼らのサードにあたり、ソウルな風味にロック色を入れたいと思った本人たちが、トッドにプロデュースを頼んで制作された。オーバー・プロデュースで有名なトッドだが、このアルバムもかなり激しいアレンジになっている。
今から20年も前。トッド・ラングレンの再発の頃だったか、その話を友人にしたら「こんなアルバムもあるよ」と紹介してくれ、CDまで貸してくれたのが、Hall&Oatesの「War Babies」だった。そのままCDは返さずじまいで今も手元にある。このアルバムは、彼らのサードにあたり、ソウルな風味にロック色を入れたいと思った本人たちが、トッドにプロデュースを頼んで制作された。オーバー・プロデュースで有名なトッドだが、このアルバムもかなり激しいアレンジになっている。