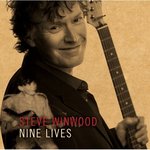 自分がロックを愛している理由を考えてみると、結局はロックというジャンルは、はっきりしていないことにつきるように感じる。ロックとは関係ない映画をみてて、「これってロックだよね」などとつい言ってしまうが、そのロックの意味の根拠など実はきわめてあいまいなのだ。だがそれがロックの強みなのだ。
自分がロックを愛している理由を考えてみると、結局はロックというジャンルは、はっきりしていないことにつきるように感じる。ロックとは関係ない映画をみてて、「これってロックだよね」などとつい言ってしまうが、そのロックの意味の根拠など実はきわめてあいまいなのだ。だがそれがロックの強みなのだ。
かつてトルコ人の友人に、「日本人はとても優秀な民族であり、自分は尊敬している。だが、西洋の文化に汚染されてしまっているのが残念だ。日本には素晴らしい伝統ミュージックがあるのに、なぜおまえはビートルズやローリング・ストーンズなど聞いているのだ(注:ぼくはあまりストーンズは聞かないけど)」と言われたことがあるが、まさにそこにロックの秘密がある。ロックは、イギリス、アメリカで生まれたかもしれないが、その源流にはブルース、ジャズ、あるいはフォークなどの影響があるわけで、「源流」は結局「源流」にはなりえない。だがその雑食性にロックの楽しみがあるのだ。ぼくは、いまだに「本物」のブルースやソウルは聞けない。日本の伝統音楽も同じ理由で。
そう考えると、このSteve Winwoodのアルバムはまさにロックアルバムである。アフリカンなパーカッションに、ブルースぽいギターライン、それに白人Winwoodのソウルフルなヴォーカルがからむ。この雑食性に富んだアルバムに、Winwoodの音楽観の豊穣さが十分に凝縮されている。60歳のミュージシャンが作るアルバムは、これまでの音楽を咀嚼しつくした上で、それらを奥深くまで含みこんだロックである。
どの曲もリズムの進行が素晴らしい。パーカッションとギターのリフのからみや、ハモンドオルガンがフューチャーされる瞬間、個々の楽器がこれほど完璧にセッションしているアルバムが他にあるだろうか。
そしてSpencer Davis Groupの頃から変わらない、これこそホワイト・ソウルというヴォーカル。
とくに心を奪われるのはたとえば、ソプラノサックスが美しい、大地の広がり、飛翔の高みを感じさせる二曲目。On a brave new morning, smiling at the skyという歌詞のすがすがしさから始まり、どこまでも深みを感じさせるアレンジが展開され、やがてOh what you're healingと、歌い上げられる。このヴォーカルも素晴らしい。だが一番素晴らしいのは、この曲がアフリカにもイギリスにも、どこにも根をはっていない、真にロックとしかいいようのない曲のエッセンスだ。
もちろん繰り返されるギターリフが印象的な一曲目から、ロックのかっこよさに引き込まれる。三曲目の変則拍子の展開も緊迫感があり、そこにはりのあるヴォーカルが重なるところが、聞き所だ。そしてブルージーなギターがはじけ飛ぶ、クラプトン参加の四曲目。黒っぽいロックが聞きごたえたっぷりである。他にも八曲目の最初のハモンドオルガンが入ってくるところなどは、何度聞いても鳥肌がたってしまう。パーカッションの効いた部分と、盛り上がるところでのハモンドオルガンとヴォーカルの絡みの対比に本当にどきどきする。最後の十曲目はまずもって泣けてくる名曲。
40年以上のキャリアをもつ人間が、今だにクリエイティブなアルバムをだし、人々を感動させ続けている。ロックの存在価値は、Winwoodのような最高の仕事人によって保たれているのだと実感できる2008年最高のロックアルバム。
