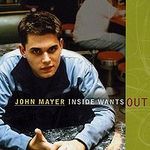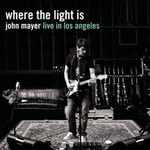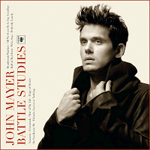 09年のニューアルバムは、John Mayerのブルース・ギターはほとんど聞かれない。ギターは落ち着いた音色で全体の曲のアンサンブルにとけ込んでいる。心地よいエコーが聞いた静かな印象のアルバムだ。
09年のニューアルバムは、John Mayerのブルース・ギターはほとんど聞かれない。ギターは落ち着いた音色で全体の曲のアンサンブルにとけ込んでいる。心地よいエコーが聞いた静かな印象のアルバムだ。
アルバムのテイストとしてはHeavier Thingsのコンセプトに近いだろう。しかしそのときには実現できなかった音楽が見事にこのアルバムに実現されている気がする。飾り立てたり、ひけらかしたりすることのない、質素で節制が効いていて、聞き終わった瞬間にゆっくりと心の中で音楽が熟成されていく。ラストの曲を聞き終えるとまた1曲目から聞き直したくなる。
シンプルな深みーたとえばAll We Everは、アレンジだけとれば叙情的な曲だが、アコースティックなシンプルさと、途中で入るギターがとても控えめで、とても上品な曲に仕上がっている。Perfectly Lonlyはもう定番といえるようなキャッチーな曲だ。しかし決してコマーシャルではない。ただ純粋に楽しんで音楽を演奏している。そこに心ひかれる。Crossroadsのカバーも何の飾りも力みもない。ストイックにブルースギターがはじけて、いさぎよく終わっている。War of My Lifeは、ドラムも単純だし、ギターのリフもほとんど変化しない。Mayerのヴォーカルにもまったく力みがない。でもだからこそ自然体の音楽がすんなり体に染みてくるのだ。
そしてラストの曲になってようやく、Mayerのしびれるギタープレイが聞ける。この曲はHPで公開されていたライブでもエンディングで演奏されていてかなりの盛り上がりを見せるのだが、アルバムテイクはそれにくらべてばかなり控えめだ。
聞き込めば聞き込むほどこれは名盤だという確信がふつふつとわいてくる。大人の挑戦としてロックだ。ひとりのミュージシャンをずっと追いかけていく楽しみはこんなところにある。
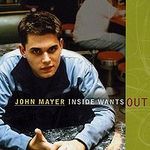 35分のEPということだが、最初の1曲を除けば、残りの8曲はすべてアコースティックであり、十分統一感がとれた1枚のアルバムだと言ってよいだろう(日本盤は1曲ボーナスつき)。
35分のEPということだが、最初の1曲を除けば、残りの8曲はすべてアコースティックであり、十分統一感がとれた1枚のアルバムだと言ってよいだろう(日本盤は1曲ボーナスつき)。
曲の最初の一小節を聞いただけで、まわりの風景が変わってしまう。ギター1本で、色彩豊かな世界が目の前に広がってゆく。No Such Thingは朝の起き抜けに聞きたい、さわやかで瑞々しい曲だ。つぎのMy stupid mouthは、少し落ち着いた、ギターのリフレインが心にじっくり刻まれる名曲。最初のわずか5秒のメロディだけれど、その刹那のメロディが、ずっと心に刻まれる。ふと気づくと自然に口ずさんでしまう、忘れられない曲だ。そしてサビのJohn Mayerの高音のヴォーカル・・・こういう曲を聴いてしまうと、なぜ自分がクラプトンに感動できないのか納得してしまう。John Mayerの曲の美しさは、こちらが立ち止まって、曲に向き合うことを余儀なくさせられる、そして、曲が終わっても、そのメロディがいつまでも響き続けている、強い「出会い」に満ちているのだ。ぼくにとってクラプトンの大方の曲はBGMでしかない。心地よくても、消費され、時間の流れにそのまま運びさられていってしまう音楽だ。
John Mayerの曲には、繊細さと強さが同居している。たとえば去年のライブアルバムでも1曲目にはいっていたNeonでのギターワークなど、繊細な弦からきわめて力強い音が流れ出してくる。もちろんcomfortableのような、ストリングスの入った泣きの曲もよいけれど。そして最後のQuietは三拍子の静謐な曲だ。リンゴ・スターのGood nightとあわせて聞きたい「おやすみソング」だ。
もし自分が17歳で、アメリカに暮らしている高校生で、ふとラジオから流れてくるJohn Mayerの曲を耳にしたら、おそらくはずっとJohn Mayerに寄り添って彼の音楽を聞き続けていくことになるだろう。30歳になっても40歳になっても彼の曲を聞いている間は17歳のままだろう。John Mayerもいくらキャリアを重ねても決して大御所にはならないだろう。プロでありながらも、デビュー当時の繊細さをずっと持ち続けてくれるだろう。
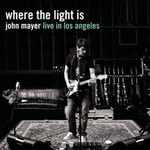 John Mayerは自分が最も聞きそうにないミュージシャンである。なにしろ顔よし、声よし、ギターよし。自分が惹かれる顔は、たとえば上前歯の2本の間にすきまがあるような顔。声は高音で裏返ってしまうようなへろへろ声。ギターは、弦が弛んでるのではと思うような、しまりのない音。その理想はKinksのLolaのB面一曲目All this tomorrowだ。イントロのギターのなさけなさ、ぐ〜っともりあがっていくところのRayの鼻づまり声。そしてあのニヒルな顔。すべてが好きだ。
John Mayerは自分が最も聞きそうにないミュージシャンである。なにしろ顔よし、声よし、ギターよし。自分が惹かれる顔は、たとえば上前歯の2本の間にすきまがあるような顔。声は高音で裏返ってしまうようなへろへろ声。ギターは、弦が弛んでるのではと思うような、しまりのない音。その理想はKinksのLolaのB面一曲目All this tomorrowだ。イントロのギターのなさけなさ、ぐ〜っともりあがっていくところのRayの鼻づまり声。そしてあのニヒルな顔。すべてが好きだ。
それに比べるとJohn Mayerはギターの弦は張り詰めている。声に一点の曇りもない。そしてあのルックス(アメリカ的美男子!)。どこを聞けばと思ったのだが、やはりアメリカン・ロックに対する憧憬の深さと、真のオリジナリティにまで達する技量の深さだろうか。ジェフ・ベックやクラプトンにはどうしても感動できないのに、彼のギターの音色にはほんとうに翻弄される。そしてヴォーカルはギターと同じく変幻自在。歌いながら、ギターをこれほどまでに弾くのだからまたすごい!
それから彼の魅力のひとつは、最近のスマートなブルースの影に多少隠れているが、90年代以降のミュージシャンぽい叙情性だ。この内省的ともおもえるメロディの美しさが、彼の音楽を手に届く等身大のものにしてくれる。とはいえおそらくヒットしたはずのWaiting on the world to changeは、一聴して親しみやすい、なつかしさを感じさせるメロディラインだが、Paul Youngほどではなく、どちらかといえば凡庸で叙情性とはほど遠い。それよりもアコースティックということもあるのだろう、Stop this trainや、名曲Daughtersは、確かなギターワークに裏打ちされた叙情性がうまく表現されている。特にDaughtersの最後、彼の声が高くなっていくところは、このアルバムの最高の瞬間だ。このアコースティックセットはこのライブアルバムの聞きどころだろう。
とはいえ実際は6曲だけ。なんだかここのパートは余技にすぎないと言っているかのようである。
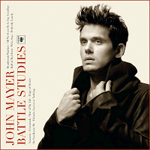 09年のニューアルバムは、John Mayerのブルース・ギターはほとんど聞かれない。ギターは落ち着いた音色で全体の曲のアンサンブルにとけ込んでいる。心地よいエコーが聞いた静かな印象のアルバムだ。
09年のニューアルバムは、John Mayerのブルース・ギターはほとんど聞かれない。ギターは落ち着いた音色で全体の曲のアンサンブルにとけ込んでいる。心地よいエコーが聞いた静かな印象のアルバムだ。