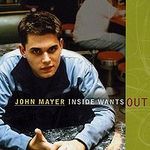 35分のEPということだが、最初の1曲を除けば、残りの8曲はすべてアコースティックであり、十分統一感がとれた1枚のアルバムだと言ってよいだろう(日本盤は1曲ボーナスつき)。
35分のEPということだが、最初の1曲を除けば、残りの8曲はすべてアコースティックであり、十分統一感がとれた1枚のアルバムだと言ってよいだろう(日本盤は1曲ボーナスつき)。
曲の最初の一小節を聞いただけで、まわりの風景が変わってしまう。ギター1本で、色彩豊かな世界が目の前に広がってゆく。No Such Thingは朝の起き抜けに聞きたい、さわやかで瑞々しい曲だ。つぎのMy stupid mouthは、少し落ち着いた、ギターのリフレインが心にじっくり刻まれる名曲。最初のわずか5秒のメロディだけれど、その刹那のメロディが、ずっと心に刻まれる。ふと気づくと自然に口ずさんでしまう、忘れられない曲だ。そしてサビのJohn Mayerの高音のヴォーカル・・・こういう曲を聴いてしまうと、なぜ自分がクラプトンに感動できないのか納得してしまう。John Mayerの曲の美しさは、こちらが立ち止まって、曲に向き合うことを余儀なくさせられる、そして、曲が終わっても、そのメロディがいつまでも響き続けている、強い「出会い」に満ちているのだ。ぼくにとってクラプトンの大方の曲はBGMでしかない。心地よくても、消費され、時間の流れにそのまま運びさられていってしまう音楽だ。
John Mayerの曲には、繊細さと強さが同居している。たとえば去年のライブアルバムでも1曲目にはいっていたNeonでのギターワークなど、繊細な弦からきわめて力強い音が流れ出してくる。もちろんcomfortableのような、ストリングスの入った泣きの曲もよいけれど。そして最後のQuietは三拍子の静謐な曲だ。リンゴ・スターのGood nightとあわせて聞きたい「おやすみソング」だ。
もし自分が17歳で、アメリカに暮らしている高校生で、ふとラジオから流れてくるJohn Mayerの曲を耳にしたら、おそらくはずっとJohn Mayerに寄り添って彼の音楽を聞き続けていくことになるだろう。30歳になっても40歳になっても彼の曲を聞いている間は17歳のままだろう。John Mayerもいくらキャリアを重ねても決して大御所にはならないだろう。プロでありながらも、デビュー当時の繊細さをずっと持ち続けてくれるだろう。
Tweet