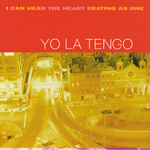バラカン・モーニングを聞いていたら、今日6月22日はジェシ・エド・デイヴィスの命日だそう。88年にドラッグ中毒で43歳で死亡。出したCDは3枚。ごそごそCDラックの中から探し出して、本当に久しぶりに聞いた。どのアルバムもいいけれど、最も地味かもしれないが、ファーストが一番彼のパーソナルな部分がでていて好きだ。(でもジャケはセカンドの写真が素敵かな...サード裏ジャケのスタジャン姿の本人も陽気なネイティブ・アメリカンの雰囲気でいい写真だ)
バラカン・モーニングを聞いていたら、今日6月22日はジェシ・エド・デイヴィスの命日だそう。88年にドラッグ中毒で43歳で死亡。出したCDは3枚。ごそごそCDラックの中から探し出して、本当に久しぶりに聞いた。どのアルバムもいいけれど、最も地味かもしれないが、ファーストが一番彼のパーソナルな部分がでていて好きだ。(でもジャケはセカンドの写真が素敵かな...サード裏ジャケのスタジャン姿の本人も陽気なネイティブ・アメリカンの雰囲気でいい写真だ)
70年から73年のわずか4年の間に、あたかも早すぎる死を予期していたかのように3枚のアルバムが出された。アルバムによって曲調が大幅に違うということはない。スパンが短かったこともあるが、それ以上にジェシの音楽スタイルは最初から確立されていたと言える。彼のスライドギターにのせたバンド演奏で、爽快なスワンプロックを聞かせてくれる。その意味でまさにこの時代の音だとも言ってしまえる。しかしこの朴訥な、決してうまいとはいえない歌声はジェシ独自のものだ。そしてリトル・フィートのように、実は繊細なメロディラインで決して泥臭くならないところが、彼をソウル、ゴスペルの味わいを残しながらもむしろSSWとしてとらえたくなるゆえんである。2曲目、Tulsa Countyの「町を抜け出して、国境までいってしまいたい」という所在なさもよいし、次のWashita Love Childでは、彼の卓越したギターを堪能できる。そして、4曲目はうってかわってロックパーティのにぎやかさをそのままリズムラインにした曲だ。B面にはいっても名曲が続く。最初の曲はホンキートンク調のピアノから入り、女性コーラスがはいってくるところなど、いわゆる南部ロックの骨太さが感じられる。次のRock'n Roll Gypsiesは、クレジットをみたらスワンプ・ロック・シンガーRoger Tillisonの曲だった。これもほんのりとゴスペルの味わいがあってほのぼのする。最後はVan Morrisonのクレイジー・ラブ。
デビュー当初は、ジョージ・ハリスン、エリック・クラプトン、レオン・ラッセルの交流から彼の名前も知られたらしいが、そのような人脈がなくてもこの3枚のアルバムはずっとロックの名盤として残り続けるだろう。
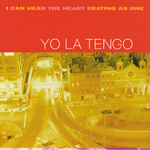 Yo La Tengoのアルバムを買ったのは確か80年代後半で、DB'sなどのアメリカインディーズを聞いていたときに、DB'sのピーター・ホルサップルやクリス・ステイミーの同志のアルバムとして買ったように思う。しかしそのアルバムの内容はむしろ、Peru Ubuなどのアングラ・ロックに等しく、聞くのに「忍耐」が必要だった。
Yo La Tengoのアルバムを買ったのは確か80年代後半で、DB'sなどのアメリカインディーズを聞いていたときに、DB'sのピーター・ホルサップルやクリス・ステイミーの同志のアルバムとして買ったように思う。しかしそのアルバムの内容はむしろ、Peru Ubuなどのアングラ・ロックに等しく、聞くのに「忍耐」が必要だった。
ところがこのバンド、粘り強く存在していたようで、今も活躍しているとのこと。入学以来500枚以上CDを買っている愛すべきO君から最近の愛聴盤と紹介され、聞かせてもらったところ、なるほど彼のいうようにソニック・ユース+ダイナソーな音作りで、さっそくCDを購入した。
ただこうして聞いてみるとむしろこのアルバムは4ADっぽい、マイ・ブラッディ・バレンタインのような音像処理のほうが耳に入ってくる。たとえば5曲目などはJoy Divisionにあるギターのエコーを最大限に聞かせて、それにヴォーカルを埋没させるような音作りである。そして途中からはFeeliesのようなアメリカのガレージバンドぽいギターを聞かせてくれる。でも面白いのはこのギターの音、結局はイーノの実験音楽的ロックと同じ音色なのだ。まさにこの雑食性こそ、このバンドの魅力なのだろう。
実際にはどうかわからないが、スタジオの録音代がまったくかかっていないようなチープな音、脱力したヴォーカルが全体の雰囲気を作っている。この金のかかっていない貧乏くさい音が、このバンドにシンパシーを感じてしまう理由である。もちろん本人たちはスタジオにこもっていろいろ機材をいじくっては楽しんでいるのだろうが...
 ストーンズといえば、あまりにもキャッチーで「キマっている」ところがどうしても聞けなかった。「黒く塗れ」、「悪魔を哀れむ歌」などあまりにも出来過ぎで、約束事を聞かされている気になってしまう。それにくらべればKinksのだらしなさ、音のすかすか感が気持ちよく、ロックは不良のためではなく、すなわち外見ではなく、日常において社会に違和感を持っていながらもなんとか暮らしている人間のためでもあるという意を強く持たせてくれた。
ストーンズといえば、あまりにもキャッチーで「キマっている」ところがどうしても聞けなかった。「黒く塗れ」、「悪魔を哀れむ歌」などあまりにも出来過ぎで、約束事を聞かされている気になってしまう。それにくらべればKinksのだらしなさ、音のすかすか感が気持ちよく、ロックは不良のためではなく、すなわち外見ではなく、日常において社会に違和感を持っていながらもなんとか暮らしている人間のためでもあるという意を強く持たせてくれた。
しかしこの『メインストリート」を聞いて、ストーンズは「キャッチー」や「決め」ではなく、ポピュラリティなのだと強く認識した。ここにあるブルース、ソウル、そして今でいうワールドミュージックなどが、白人の若者たちによって咀嚼され、演奏され、広いポピュラリティを獲得している。それがストーンズの魅力だと感じた。ここにあるのは、ロックという混血の音楽であり、始源から切り離された私生児が持つ音楽の魅力だ。
とにかく今回のSHMCDは、よい意味で音の分離が明確で、それぞれの音が粒だっている分だけ、それぞれの楽器がここぞというタイミングで絡み付いているのがよてもよくわかる。たとえばロバート・ジョンソンのカバーStop Breaking Downのミック・テイラーのぐねぐねにワイルドなスライドに、ミック・ジャガーのマウス・ハープ、ニッキー・ホプキンスのキーボードがからんでくるところなど、すでにブルースでありながら、それを超えるポピュラリティを持ってしまっている。ポピュラリティとは、人種や出自を問題にせず、どんな生き方をしてきた人間にも通じる音楽ということだ。
自分はロックミュージシャンがなんだかわけもなく「イェー」と叫んでいるのを心から唾棄する人間だが、1曲目Rocks Offの冒頭の「Yeah」にはゾクゾクしてしまう。無礼講のパーティにふさわしい猥雑なかけ声だ。
個人的に心に突き刺さるのは、ソウルテイストというかゴスペル感のあふれるTorn and Frayedや、Let It Loose, Shine a Lightだろうか。「ベガーズ・バンケット」の「地の塩」を聞いて卒倒した自分としては、この高揚感にしびれっぱなしである。
このCDを買ったときには、焼け買いで他にも買いあさったのだが、このアルバムがハードローテーションで、まったく聞けていないし、ボーナストラックもまだまだ聞く体勢になれない。
そう、ソウルといえば「ダイスをころがせ」。この曲にもロックの恒例の代名詞「ベイビー」が連呼されるが、この曲ほど「ベイビー」がかっこいい曲もないだろう。バックコーラスとの盛り上がり、夜を徹して踊りたくなる名曲です。
 フランスの詩人アラゴンについて調べていて、次のような彼のことばがあった。「プロレタリア文学は、形式において民族的であり、内容において社会主義的であろう、というスターリンの言葉をもう一度思い出そう」。
フランスの詩人アラゴンについて調べていて、次のような彼のことばがあった。「プロレタリア文学は、形式において民族的であり、内容において社会主義的であろう、というスターリンの言葉をもう一度思い出そう」。
文学同様、音楽も民族の精神、階級の精神に結びつけて語られやすい。たとえば音楽に託された虐げられた人々の魂の声というような言い方である。たとえ抑圧ということばを持ち出さなくても、なぜマイケル・ジャクソンが兄弟ともども幼くして芸能生活を始めているのか、そこには黒人と芸能という切っても切り話せない社会生活の一端がはっきりと示されている。
アラゴンからずいぶん飛躍だが、それでも音楽という文化はメッセージをもち、ある階級や人種の抵抗のシンボルになりうる。しかし音楽が本当に生き始めるのは、その音楽が、当初の対象であった、階級や人種の閉じられた壁を越えるときではないだろうか。Isley Brothersは、当初から曲が白人ロックグループに取り上げられ、ひとえにポピュラー・ミュージックとしての俗化に寄与してきた。
そして70年代前後。ソウルにインスパイアされた白人ミュージシャンの曲をカバーすることになる。それも洗練されたアレンジのメロディラインと、練り上げられたファンクのリズムで、音楽が何らかのジャンルに属す必要などまったくないことを実感させてくれたのである。時代の重々しさを引きずった前作も重要だが、Isleyらしい吹っ切れ感があって、こちらのアルバムのほうを何度も聞いてしまう。
たとえばSweet Seasonの解釈が好きだ。60年代のポップスの定型を抜け出して、軽やかなコーラスを聞かせて、後半はファンク調のギターをからめて、Keep On Walkin'にうつり、コーラスもドゥワップにかわるとこころがスリリング。
Work To Doも最初のピアノの音が印象的だが、ヴォーカルはその甘さを軽く拭うかのようにパンチが効いている。このシャウトしながら、高音をのばしてゆくサビの部分が最高です。
スイートであるが決してBGMではない。この静かな主張が、70年という時代を越えて現在まで届いてくる。そこには洗練という音へのこだわりが必要だったのだ。だから、このアルバムを聞きながら、歌詞ではなくサウンドへと注意が行ってしまう。そうした聞き方はアルバムが出された当時ならばできなかったかも知れないが...
 バラカン・モーニングを聞いていたら、今日6月22日はジェシ・エド・デイヴィスの命日だそう。88年にドラッグ中毒で43歳で死亡。出したCDは3枚。ごそごそCDラックの中から探し出して、本当に久しぶりに聞いた。どのアルバムもいいけれど、最も地味かもしれないが、ファーストが一番彼のパーソナルな部分がでていて好きだ。(でもジャケはセカンドの写真が素敵かな...サード裏ジャケのスタジャン姿の本人も陽気なネイティブ・アメリカンの雰囲気でいい写真だ)
バラカン・モーニングを聞いていたら、今日6月22日はジェシ・エド・デイヴィスの命日だそう。88年にドラッグ中毒で43歳で死亡。出したCDは3枚。ごそごそCDラックの中から探し出して、本当に久しぶりに聞いた。どのアルバムもいいけれど、最も地味かもしれないが、ファーストが一番彼のパーソナルな部分がでていて好きだ。(でもジャケはセカンドの写真が素敵かな...サード裏ジャケのスタジャン姿の本人も陽気なネイティブ・アメリカンの雰囲気でいい写真だ)