Un chagrin de passageは、サガンの晩年の作品である。主人公の男は40歳になる建築家であり、ラグビーで鍛えた肉体の持ち主である。作品は医者に肺がんを告げられた朝から、その診察が誤りであったことを知る夜までを描いている。その間が「つかの間の悲しみ」である。しかし、この作品の残酷さは、悲しみはこの一日ではなく、実は彼の人生のそのものが愚かなものでしかないことを、この誤診があばきたててしまったところにある。
主人公が«le prototype du Français médiocre»(p.53)というとき、その凡庸さとは何だろうか。あさはかな友情、心のかよわない、自らのmacho(優位)ぶりを示すだけの愛人との関係、過去の愛を求める幼稚な精神。それらがすべて主人公の凡庸さを物語る。しかも、彼はそれらの他人を訪ねながら、ひとつの喜劇をあくまでも演じているのである。愛人や昔の10年前に別れた女と最後の6ヶ月を過ごすことを望み、愛のない妻の介護をかたくなに拒否する姿には凡庸を通りすぎてもはや哀れみしかない。
サガンのこのような構成を通して、私たちが感じるのは、「俗っぽく、群れをなし、ありふれたもの」(p.149.)であればあるほど、成功するこの社会の欺瞞である。社会が求める価値は、所詮は凡庸であり、その凡庸さを疑いもしない、主人公を典型とする人間たちは、実際にはそうした生の裏にある虚無に気づいていないのだ。
お決まりの筋の展開、人間の行動、想定内の出来事の集積は、物語の凡庸さを私たちに印象づける。生も死もドラマティックなものではなく、生きることはただ凡庸でしかないという強烈な厭世観。そのサガンの諦念を感じざるをえないのだ。
 CD4枚+DVD1枚。ディスク・ユニオンの中古で2000円ちょっとで購入。DVDはオースティンでのライブだが、これは必見。どの曲もメンバーがはねている。とくにギターとベース。若いバンドの演奏って実にいいと感じさせてくれる。とにかくすばらしい。
CD4枚+DVD1枚。ディスク・ユニオンの中古で2000円ちょっとで購入。DVDはオースティンでのライブだが、これは必見。どの曲もメンバーがはねている。とくにギターとベース。若いバンドの演奏って実にいいと感じさせてくれる。とにかくすばらしい。
Disc2は前半が新宿JAMでのライブ。あの狭い空間で濃密な音楽が流れたかと思うと、感慨深い。一曲目Omoideはもったいぶったイントロが実にかっこよく、ドラムのロールからギターが入ってきてのっけから最高にスリリングなのだが、このテイクはドラムのバランスが大きいせいか、かなりストレートな曲に出来上がっている。解散直前にくらべれば曲のもつレンジがせまいけれども、ライブバンドとして卓越した技量をみせつける爽快さがこのテイクにはある。次の「大あたりの季節」もノイジーではあるが、いわゆるロックバンドの定式を抜け出しているわけではない。ライブバンドのノリだけで押し通してしまう若さがあるといおうか。いったいこのバンドはどれほどのスピードで円熟へと達してしまったのだろうか。
このdisc2を聞くと、演奏力だけでは歴史にならないことを強く感じる。このライブだけでは、Number Girlが日本のロック史に名を刻むバンドになったかどうかわからない。演奏だけではなく、いわゆるオーラのようなもの、唯一無二なものが生まれて初めて、歴史の中でこのバンドを考えることができる。解散時の圧倒的な存在感、何かが取り憑いたような存在感ではない。たとえば8曲目「日常を生きる少女」など、このテイクでは単調なタテノリで、性急で突っ込みがちだ。しかし「シブヤ」では、それだけではおさまらない幅がある。ヴォーカルが遠いといおうか、それでも曲として深まりがあるのだ。空気をつかんでひきのばしたような、それでいてはりつめた音の世界が広がってゆく。
Disc4は、裸のラリーズのように、ギターのエコーと、それがノイズとなって渦巻くところから曲が始まる。最高にかっこいい始まり方だ。この1曲目の「日常に生きる少女」から2曲目の「Omoide」へとつながるところも実にいい。Omoideは渋谷のライブ盤、そして札幌ラストコンサートのテイクの鬼気迫る「いってしまった」感にくらべると、こちらのテイクは、たたみかける「まともな」演奏だが、音の圧力はひけをとらない。
このdisc4のベストテイクはZazenbeats kemonostyle。もともとヴォーカルは叫びではなくうなりのようなものだが、この曲では吠えまくっている。サイケデリックなギターによる演奏が延々と続き、そこにひたすらヴォーカルがかぶってくるところ、この10分のノイズの渦巻きが圧巻だ。そのあとのeitht beaterもやたら攻撃的だ。もうこれ吠えまくりでほとんど歌になっていない・・・実にエフェクターの効き具合がたまらない。
で、disc1,4はまだ聞く時間がない・・・
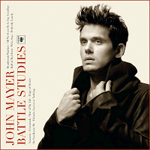 09年のニューアルバムは、John Mayerのブルース・ギターはほとんど聞かれない。ギターは落ち着いた音色で全体の曲のアンサンブルにとけ込んでいる。心地よいエコーが聞いた静かな印象のアルバムだ。
09年のニューアルバムは、John Mayerのブルース・ギターはほとんど聞かれない。ギターは落ち着いた音色で全体の曲のアンサンブルにとけ込んでいる。心地よいエコーが聞いた静かな印象のアルバムだ。
アルバムのテイストとしてはHeavier Thingsのコンセプトに近いだろう。しかしそのときには実現できなかった音楽が見事にこのアルバムに実現されている気がする。飾り立てたり、ひけらかしたりすることのない、質素で節制が効いていて、聞き終わった瞬間にゆっくりと心の中で音楽が熟成されていく。ラストの曲を聞き終えるとまた1曲目から聞き直したくなる。
シンプルな深みーたとえばAll We Everは、アレンジだけとれば叙情的な曲だが、アコースティックなシンプルさと、途中で入るギターがとても控えめで、とても上品な曲に仕上がっている。Perfectly Lonlyはもう定番といえるようなキャッチーな曲だ。しかし決してコマーシャルではない。ただ純粋に楽しんで音楽を演奏している。そこに心ひかれる。Crossroadsのカバーも何の飾りも力みもない。ストイックにブルースギターがはじけて、いさぎよく終わっている。War of My Lifeは、ドラムも単純だし、ギターのリフもほとんど変化しない。Mayerのヴォーカルにもまったく力みがない。でもだからこそ自然体の音楽がすんなり体に染みてくるのだ。
そしてラストの曲になってようやく、Mayerのしびれるギタープレイが聞ける。この曲はHPで公開されていたライブでもエンディングで演奏されていてかなりの盛り上がりを見せるのだが、アルバムテイクはそれにくらべてばかなり控えめだ。
聞き込めば聞き込むほどこれは名盤だという確信がふつふつとわいてくる。大人の挑戦としてロックだ。ひとりのミュージシャンをずっと追いかけていく楽しみはこんなところにある。
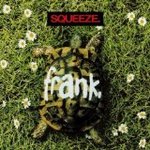 当時はロックしか聞いてなかった自分にとって、スクイーズはひねくれたブリティッシュ・ニュー・ウェーブバンドということで気に入っていた。しかし今聞き返してみると、このバンドは、了見のせまかった自分にとっても十分聞けるソウルテイストのロックだったのだと思う。たとえばポール・ウェラーのソウルへの傾倒はあまりに素直すぎて聞けなかった。それに対してスクイーズはもっと洗練されていて、ルーツを気にしなくても聞けるバンドだった。
当時はロックしか聞いてなかった自分にとって、スクイーズはひねくれたブリティッシュ・ニュー・ウェーブバンドということで気に入っていた。しかし今聞き返してみると、このバンドは、了見のせまかった自分にとっても十分聞けるソウルテイストのロックだったのだと思う。たとえばポール・ウェラーのソウルへの傾倒はあまりに素直すぎて聞けなかった。それに対してスクイーズはもっと洗練されていて、ルーツを気にしなくても聞けるバンドだった。
また当時はXTCと並んだあまのじゃくバンドという印象だったが、アンディ・パートリッジのようなインテリ然としたそれゆえ攻撃的な(もう少しいくと人の悪い)アプローチは感じられない。むしろいろんな実験的なことをやるんだけど、どれも結局は同じ味になってしまって、でもまあそれでもいいか、といった枠を破れないというか枠のくっきりしたバンドだ。そんな投げやりなユーモアはたとえば5曲目の雰囲気によく表れている。
89年のFrankはなかでも最もストレートなポップアルバムだと思う。ベスト・テイクはLove Circlesだ。とっても爽やかで、でもどこかせつない。20年も前に聞いたのに、今だに胸がしめつけられるのは、曲がフォーエバー・ヤングなのか、自分がそうなのか・・・ギターのリフがこの頃のニュー・ウェーブのいかにもの音で青臭いのだけど、曲の展開は完璧、とくにサビの前の少しマイナーなメロディがいい。青春の代表的な一曲。
もちろん他の曲もいい。冒頭のイントロ明けのIf it's Loveは一回聞いただけですぐに口ずさめる優れたポップソングであり、そうしたところでビートルズに近いと言われるのかもしれない。この曲はヴォーカルがほどよくパンチがあって、曲のノリのよさとあっている。どの曲も親しみやすいのに、それでもスクイーズのオリジナリティを十二分に感じることができる。そのあたりの個性と普遍性を兼ね備えているところが、このバンドの卓越したところなんだろう。
数年前にでたクリス・ディフォードの弾き語りライブも感動ものだった。かつてのスクイーズの曲を弾き語りで演奏しているのだが、それだけによけい曲のよさが際立つ。その意味でもイギリス・ニューウェーブの文脈を超えて、ポップ・ロックとしての代表バンドとしてスクイーズをあげることができる。
 前作Innervisionsは、完璧な作品で、一音一音まで緊密に構成され、その完成度の高さに聞き終わるとちょっと脱力状態になってしまうが、このFirst Finaleは、もう少し余裕をもって聞けるアルバムである。
前作Innervisionsは、完璧な作品で、一音一音まで緊密に構成され、その完成度の高さに聞き終わるとちょっと脱力状態になってしまうが、このFirst Finaleは、もう少し余裕をもって聞けるアルバムである。
それはたとえばToo shy to sayやThey won't go when I goのようにメロディだけとるならば、あまりにも直接的で平明な曲があるからかもしれない。
だが24歳にしてすでに人生の「ファースト・フィナーレ」と言ってしまうほどアルバムの充実度は高い。ポップでいて驚きに満ちた音楽だ。その驚きというのは実は細かいところに現れる。たとえば1曲目、さびのBum, Bumのバック・コーラスの「ニャー」というかけ声が不思議だ。
このアルバムで一番好きなのはA面5曲目のCreepin'。のっけからドラムスの入り方がかっこいい。その後もこの曲はシンセではなくて、ドラムスが見事におかずをいれながら入ってきて、甘い愛の歌にもかかわらずタイトな雰囲気に仕上がっている。それから2曲目のゴスペルタッチのHeaven is〜。こちらの気分をいやがおうにも高揚させてくれる。
B面にはいると、ファンクのねばりこいリズムにのせて、曲がはねる。「ジャクソン5が僕と一緒に歌うよ〜」っていうところもノリノリでいいです。最後のPlease don't goも卓越したセンスを感じる曲だ。おなじみのハーモニカもよいし、Tell me whyの力のこもった歌い方もよいし、Don't go babyとたたみかけてくるところの迫力、そしてクラップ音がはいってゴスペルテイスト全開で終わっていくところなど、まさにフィナーレだ。
高みに達した落ち着きが感じられるとはいえ、音はあくまでカラフルだし、ヴァラエティに富んでいる。やりたいことをそのままできてしまえる、そのような天才の恍惚を満喫できる一枚だ。
 前からちゃんと聞きたいと思っていたが、1枚もアルバムは持っていなかった。先日ラジオでかかっていたAngel from montgomeryがあまりにいい曲だったので、この曲がおさめられているアルバムを購入した。それ以来この曲、ヘビーローテーションである。
前からちゃんと聞きたいと思っていたが、1枚もアルバムは持っていなかった。先日ラジオでかかっていたAngel from montgomeryがあまりにいい曲だったので、この曲がおさめられているアルバムを購入した。それ以来この曲、ヘビーローテーションである。
R&Bの姉御として、渋いギタープレイを聞かせてくれ、90年にグラミー賞を受賞してからはその迫力にますます拍車がかかるとともに、円熟味をみせているBonnie Raittだが、このアルバムはなんと全編ヴォーカルアルバムである。その意味では特殊なアルバムなのかもしれない。豪快さや颯爽としたところもないまろやかなアルバムだが、だからと言って決して悪いアルバムではないのは、取り上げている曲がすばらしいからだ。
プロデューサーはJerry Ragovoy。60年代の有名なプロデューサーとのこと。このあたりの人脈をもっと知らねば・・・。
1曲目、2曲目はジョニ・ミッチェル、ジェームス・テイラー。そして3曲目にAngel〜がかかる。これはJohn Prineの曲。このミュージシャンもアルバムを聞いたことがないのだが、小尾さんのSongsでは、この曲の歌詞もひきながら紹介されている。たそがれ感がただよいつつも、大地にしっかりと根ざした確信がひしひしと伝わってくる名曲だ。
このアルバムが必ずしもBonnie Raittのアルバムである必然性はないのかもしれない。それほど切実な歌い方ではないし、この時代の才能ある女性ミュージシャンならば多かれ少なかれアプローチしていた方法だと思うからだ。アメリカのルーツを意識しながらもあくまでもポップ。とはいえAORにはならず。趣味のよいストリングスが入り、スタジオ・ミュージシャンによる粋なアレンジの上に、ヴォーカルがかぶさってくる。
ただここに歌われている曲は、彼女がとりあげたことで、よりいっそうこれからも歌われ続ける、歴史に埋もれたりはしない名曲であることを確信させてくれる。とにかく曲が生き生きしているのだ。結局はアルバム通して一気に聞いてしまえるご機嫌な音楽なのだ。
