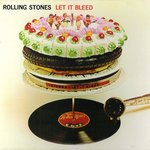ディスコ、パンクミュージックに対するストーンズからの返答と言われた『女たち』。しかし今から振り返ればディスコやパンクは一過性のブームや衝動に過ぎず、その中で生き残ったミュージシャンはごくわずか。それに対して今でも『女たち』は聞かれ続けている。
ディスコ、パンクミュージックに対するストーンズからの返答と言われた『女たち』。しかし今から振り返ればディスコやパンクは一過性のブームや衝動に過ぎず、その中で生き残ったミュージシャンはごくわずか。それに対して今でも『女たち』は聞かれ続けている。
そもそもこのアルバムにディスコやパンクの影響を見つけることにどんな意味があるのだろうか。確かにMiss Youはディスコを意識した当時の「音」である。しかしそれ以外の曲はストーンズの刻印がしっかりと押されている。2曲目When the Whip comes downの性急な感じは「パンク」とあい通じるところはあるかも知れない。しかしそれよりもタイトル歌詞のリフレイン部分の騒々しさはいかにもストーンズである。ライブで観衆を一気に煽る「定番」だ。
3曲目はテンプテーションズのカバーということだが、ギターの「ジャラーン」という音だけですでにストーンズ自身の曲だと言ってしまえる。「定番」のバラードにもいい曲がおさめられている。9曲目のBeast Of Burden。
このアルバム、もちろん名盤なのだが、それでも何かしっくりこないものがある。それは、ストーンズが「再生産」されてしまっているということだ。ディスコやパンクではなく、まさしく「ストーンズ」がどの曲にも認められるならば、それはすでに「ストーンズ定番の音」が決まってしまっているということだ。すでにレシピはわかっていて、これで調理すればどういう味かも決まってしまっているかのような...もはや驚きや失望もない、このアルバムを聞いていだくのは「安心感」なのだ。この時代であっても「ストーンズ健在」のような。健在していてもしょうがない。むしろ存在をたえず否定し、更新してゆくところにストーンズの見かけとは反対の音楽に対する禁欲なまでの探究心があったのではないだろうか。
そう考えると「音」のざらつき感もないし、なんだか衛生殺菌されたような音作りになっている。むしろこのアルバムに時代の影響を求めるのならば、この生気を消し去るような音のパッケージなのではないだろうか。
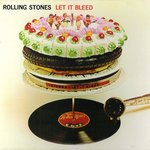 バンドの音だが、スタジオミュージシャンすべて含めてのバンドの音になっている。それによってアルバムの雰囲気も、一曲一曲も、決まったジャンルにはおさまりきらない、スケールの大きさを獲得している。血統のない雑種としての音楽だ。そしてそこには、音楽自体を創造してゆこうとする高い志がある。
バンドの音だが、スタジオミュージシャンすべて含めてのバンドの音になっている。それによってアルバムの雰囲気も、一曲一曲も、決まったジャンルにはおさまりきらない、スケールの大きさを獲得している。血統のない雑種としての音楽だ。そしてそこには、音楽自体を創造してゆこうとする高い志がある。
バンドは、それぞれが強い個性を発揮しながらも、決してバラバラにならずひとつのエネルギーを作ってゆくから面白い。ブライアン・ジョーンズが抜け、ミック・テイラーが加入するという過渡期に制作されたこのアルバムには、メンバー交代の不安定さなど感じられない。それどころか、アメリカのミュージシャンが入って、様々なバックボーンを持った音が混じりあい、そこから強い緊張感をもった音楽が生まれているのだ。
1曲目からMary Claytonの力強いヴォーカルにからみつくようにミックのハープが響き、ニッキー・ホプキンスのピアノが跳ねるなか、曲がどんどん進行してゆく。2曲目のロバート・ジョンソンのカバー曲に参加しているのはRy Cooder。埃が舞い上がるような寂寥感の演出が実にうまい。
ここにおさめられているのは、ジャンルを無視したポピュラリティあふれる曲ばかりだ。3曲目はフィードルから始まる、ブリティッシュロックと南部アメリカンロックの混合が見事なCountry Honk。4曲目はディープなスワンプロックのコード進行から始まり、ぐいぐいと疾走してゆくスピード感見事な一曲。最後のドラムのシンバルがひたすらたたかれまくられるのがかっこいいです。そしてA面最後のLet it bleedは、クレジットをみると、このスライドはキースが弾いている。Ladies&GentelmensのDVDではミック・テイラーの職人技の微動だにしない姿勢から生まれるスライドギターの音が、実にバンドの要となっていたが、この曲のスライドはテイラーに負けていない...
B面1曲目は、ふたたびねちっこいブルース。最後のYou can't always get what you wantは「地の塩」に続くアカペラ路線を拡大した曲。アル・クーパーのホルンに、アコースティックギター、そしてヴォーカルが入り、一気に曲が盛り上がっていく。アル・クーパーはピアノ、オルガンも担当し、コーラスの編成はジャック・ニッチェ。これこそストーンズの真骨頂ではないだろうか。どこまでも音を厚く塗り重ねて、猥雑とさえいえるような、いろんな音の混ざり具合こそストーンズの音楽を聞く醍醐味だと思う。ロックの雑種としての魅力に強くひきよせられるのだ。ロックだと思う。
 ストーンズといえば、あまりにもキャッチーで「キマっている」ところがどうしても聞けなかった。「黒く塗れ」、「悪魔を哀れむ歌」などあまりにも出来過ぎで、約束事を聞かされている気になってしまう。それにくらべればKinksのだらしなさ、音のすかすか感が気持ちよく、ロックは不良のためではなく、すなわち外見ではなく、日常において社会に違和感を持っていながらもなんとか暮らしている人間のためでもあるという意を強く持たせてくれた。
ストーンズといえば、あまりにもキャッチーで「キマっている」ところがどうしても聞けなかった。「黒く塗れ」、「悪魔を哀れむ歌」などあまりにも出来過ぎで、約束事を聞かされている気になってしまう。それにくらべればKinksのだらしなさ、音のすかすか感が気持ちよく、ロックは不良のためではなく、すなわち外見ではなく、日常において社会に違和感を持っていながらもなんとか暮らしている人間のためでもあるという意を強く持たせてくれた。
しかしこの『メインストリート」を聞いて、ストーンズは「キャッチー」や「決め」ではなく、ポピュラリティなのだと強く認識した。ここにあるブルース、ソウル、そして今でいうワールドミュージックなどが、白人の若者たちによって咀嚼され、演奏され、広いポピュラリティを獲得している。それがストーンズの魅力だと感じた。ここにあるのは、ロックという混血の音楽であり、始源から切り離された私生児が持つ音楽の魅力だ。
とにかく今回のSHMCDは、よい意味で音の分離が明確で、それぞれの音が粒だっている分だけ、それぞれの楽器がここぞというタイミングで絡み付いているのがよてもよくわかる。たとえばロバート・ジョンソンのカバーStop Breaking Downのミック・テイラーのぐねぐねにワイルドなスライドに、ミック・ジャガーのマウス・ハープ、ニッキー・ホプキンスのキーボードがからんでくるところなど、すでにブルースでありながら、それを超えるポピュラリティを持ってしまっている。ポピュラリティとは、人種や出自を問題にせず、どんな生き方をしてきた人間にも通じる音楽ということだ。
自分はロックミュージシャンがなんだかわけもなく「イェー」と叫んでいるのを心から唾棄する人間だが、1曲目Rocks Offの冒頭の「Yeah」にはゾクゾクしてしまう。無礼講のパーティにふさわしい猥雑なかけ声だ。
個人的に心に突き刺さるのは、ソウルテイストというかゴスペル感のあふれるTorn and Frayedや、Let It Loose, Shine a Lightだろうか。「ベガーズ・バンケット」の「地の塩」を聞いて卒倒した自分としては、この高揚感にしびれっぱなしである。
このCDを買ったときには、焼け買いで他にも買いあさったのだが、このアルバムがハードローテーションで、まったく聞けていないし、ボーナストラックもまだまだ聞く体勢になれない。
そう、ソウルといえば「ダイスをころがせ」。この曲にもロックの恒例の代名詞「ベイビー」が連呼されるが、この曲ほど「ベイビー」がかっこいい曲もないだろう。バックコーラスとの盛り上がり、夜を徹して踊りたくなる名曲です。
 ディスコ、パンクミュージックに対するストーンズからの返答と言われた『女たち』。しかし今から振り返ればディスコやパンクは一過性のブームや衝動に過ぎず、その中で生き残ったミュージシャンはごくわずか。それに対して今でも『女たち』は聞かれ続けている。
ディスコ、パンクミュージックに対するストーンズからの返答と言われた『女たち』。しかし今から振り返ればディスコやパンクは一過性のブームや衝動に過ぎず、その中で生き残ったミュージシャンはごくわずか。それに対して今でも『女たち』は聞かれ続けている。