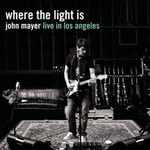 John Mayerは自分が最も聞きそうにないミュージシャンである。なにしろ顔よし、声よし、ギターよし。自分が惹かれる顔は、たとえば上前歯の2本の間にすきまがあるような顔。声は高音で裏返ってしまうようなへろへろ声。ギターは、弦が弛んでるのではと思うような、しまりのない音。その理想はKinksのLolaのB面一曲目All this tomorrowだ。イントロのギターのなさけなさ、ぐ〜っともりあがっていくところのRayの鼻づまり声。そしてあのニヒルな顔。すべてが好きだ。
John Mayerは自分が最も聞きそうにないミュージシャンである。なにしろ顔よし、声よし、ギターよし。自分が惹かれる顔は、たとえば上前歯の2本の間にすきまがあるような顔。声は高音で裏返ってしまうようなへろへろ声。ギターは、弦が弛んでるのではと思うような、しまりのない音。その理想はKinksのLolaのB面一曲目All this tomorrowだ。イントロのギターのなさけなさ、ぐ〜っともりあがっていくところのRayの鼻づまり声。そしてあのニヒルな顔。すべてが好きだ。
それに比べるとJohn Mayerはギターの弦は張り詰めている。声に一点の曇りもない。そしてあのルックス(アメリカ的美男子!)。どこを聞けばと思ったのだが、やはりアメリカン・ロックに対する憧憬の深さと、真のオリジナリティにまで達する技量の深さだろうか。ジェフ・ベックやクラプトンにはどうしても感動できないのに、彼のギターの音色にはほんとうに翻弄される。そしてヴォーカルはギターと同じく変幻自在。歌いながら、ギターをこれほどまでに弾くのだからまたすごい!
それから彼の魅力のひとつは、最近のスマートなブルースの影に多少隠れているが、90年代以降のミュージシャンぽい叙情性だ。この内省的ともおもえるメロディの美しさが、彼の音楽を手に届く等身大のものにしてくれる。とはいえおそらくヒットしたはずのWaiting on the world to changeは、一聴して親しみやすい、なつかしさを感じさせるメロディラインだが、Paul Youngほどではなく、どちらかといえば凡庸で叙情性とはほど遠い。それよりもアコースティックということもあるのだろう、Stop this trainや、名曲Daughtersは、確かなギターワークに裏打ちされた叙情性がうまく表現されている。特にDaughtersの最後、彼の声が高くなっていくところは、このアルバムの最高の瞬間だ。このアコースティックセットはこのライブアルバムの聞きどころだろう。
とはいえ実際は6曲だけ。なんだかここのパートは余技にすぎないと言っているかのようである。
 ブリティッシュ・ロックの芸術表現としての高まりは、アルバムをひとつの作品として仕上げるというコンセプチュアル・アートの運動としてとらえることができるだろう。そうしたアート性を志向してゆくと、ビートルズのように歌って踊らせるようなコンサートはできなくなる。スタジオにこもって、幾重にも音を重ねてゆく作品はステージでは再現不能だ。
ブリティッシュ・ロックの芸術表現としての高まりは、アルバムをひとつの作品として仕上げるというコンセプチュアル・アートの運動としてとらえることができるだろう。そうしたアート性を志向してゆくと、ビートルズのように歌って踊らせるようなコンサートはできなくなる。スタジオにこもって、幾重にも音を重ねてゆく作品はステージでは再現不能だ。
しかしコンセプチュアル・アートはアルバムとしての作品志向以外にも、ステージ自体をひとつの芸術表現の舞台として、スペクタル的な要素を強めていく方向性ももつ。つまりショーだ。そのときに「きわもの」的なショーとしてアートを実践したのが、デヴィッド・ボウイであり、ロキシー・ミュージックであった。その系譜にこのコックニー・レベルは属するだろう。プログレッシヴ・ロックではないのだが(といっても、このCD、プログレッシヴ・ロック・シリーズと銘打たれたアルバムの1枚として発売されている・・・)、それでもアルバムはひとつの様式美で貫かれている。その様式美とは、頽廃だ。
先日フランスのTéléramaが提供してくれているpodcastのロック番組で、Voix fragiles(壊れやすい声)というタイトルでイギリスのロックヴォーカルを特集していた。Kinks, Prety thingsそしてその次がこのコックニー・レベルのTumbling downだった。The Psychomodoのラストを飾る曲で、か細い、ひきつるような、そして粘着質のスティーヴ・ハーリーのヴォーカルが最後に絶叫に代わる、スケールの大きな曲だ。
久しぶりにアルバムを聞いているうちに、プログレとの親和性を示しながらも、大作志向ではなく、あくまでもひねくれたポップセンスにこだわるバンドがこの当時のイギリスにはいたことを思い出した。Deaf SchoolやKorgis、そしてStackridgeなどである。
しかしその中でもとりたてて、頽廃美にこだわっていたのがこのコックニーレベルだろう。抽象度の高い歌詞には狂気ということばが散見する。だがそれはあくまでも周到に演出された狂気であって、役者はあくまでも冷静に狂気を演じる。そうした人工的な美しさがこのバンドの魅力だ。特にこのアルバムは全編にわたって、道化師の皮肉な笑顔とでも言えるようなパフォーマンスが繰り広げられている。こうした歪んだポップというのはいかにもイギリスのロックのものだ。
ちなみにYoutubeにも何本も動画があって、75年のヒット作Make me smileを初めて聞いた。たしかに以前の毒気は影をひそめているが、鼻につまった、うれいをおびたヴォーカルは依然として魅力的だし、曲も質の高いポップソングだ。A級では決してないけれど、でもこうした卓越したメロディは誰にも書けない。こんな歌い方も誰もできないだろう。70年代のあだ花のような感じが一見するが、じつはスタンダードなポップソングをかいていたのが、このスティーヴ・ハーリーだと実感した。
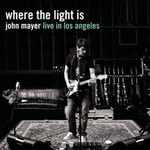 John Mayerは自分が最も聞きそうにないミュージシャンである。なにしろ顔よし、声よし、ギターよし。自分が惹かれる顔は、たとえば上前歯の2本の間にすきまがあるような顔。声は高音で裏返ってしまうようなへろへろ声。ギターは、弦が弛んでるのではと思うような、しまりのない音。その理想はKinksのLolaのB面一曲目All this tomorrowだ。イントロのギターのなさけなさ、ぐ〜っともりあがっていくところのRayの鼻づまり声。そしてあのニヒルな顔。すべてが好きだ。
John Mayerは自分が最も聞きそうにないミュージシャンである。なにしろ顔よし、声よし、ギターよし。自分が惹かれる顔は、たとえば上前歯の2本の間にすきまがあるような顔。声は高音で裏返ってしまうようなへろへろ声。ギターは、弦が弛んでるのではと思うような、しまりのない音。その理想はKinksのLolaのB面一曲目All this tomorrowだ。イントロのギターのなさけなさ、ぐ〜っともりあがっていくところのRayの鼻づまり声。そしてあのニヒルな顔。すべてが好きだ。
