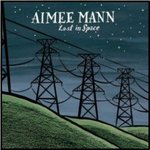 往々にしてロックは、「瞬間」に生まれることがある。一夜にして録音を終えてしまったとか、1テイク録りでアルバムを作ってしまったとか、その時のエネルギーを一気に凝縮して、緊張感をそのまま閉じ込めたアルバムは、それだけで伝説として語り継がれたりもする。
往々にしてロックは、「瞬間」に生まれることがある。一夜にして録音を終えてしまったとか、1テイク録りでアルバムを作ってしまったとか、その時のエネルギーを一気に凝縮して、緊張感をそのまま閉じ込めたアルバムは、それだけで伝説として語り継がれたりもする。
そうした最高度のテンションで、バンドの音を作り上げるようなロックがあるとするならば、Aimee Mannのこのアルバムはおよそそうした創作の仕方とは対極にあるものだろう。このアルバムは決して「偶然の産物」ではない。丁寧に織り上げられたハンド・メイドの肌触りがあるアルバムだ。これだけポップな曲作りをしていながらも、安易な既製品の音はまったく聴かれない。こうした仕事にはいったいどのくらい時間がかかるのかわからないが、音楽にまっすぐに対峙して、丹誠をこめて作られた曲が並んでいる。
これだけポピュラーな音作りをしていながら、なぜ平板な音にならないのだろうか?たとえばReal Bad Newsのアレンジは、夫Michael Penのアルバムにも似てとても深みがあるエコーの音で、けっこう不思議な音色だ。Pavlov's Bellのギターソロは、これだけ聞くと、曲の憂うつな感じとはそぐわない結構派手な音なのに、曲の中では違和感がない。そしてInvisible Inkの慎ましやかなヴォーカルに重ねられる控えめなストリングス・・・どの曲も実によく練り上げられたプロの音だ。Aimee Mannのヴォーカルを一切邪魔することなく、いやそれどころか単に美声で歌われるだけのなじみやすいメロディでは終わらない、聞き込めば聞き込むほど、全体のカラーが浮かんでくるコンセプトのしっかりしたアルバムに仕上がっていることがわかる。もちろんAimeeのヴォーカルの表現力もすばらしい。 This is How It goesのようなヴォーカルが全面に出ている曲での、彼女の抑揚の効いた歌い方は、とても地味なのだが、聞き終わった瞬間から、心の中で彼女の声が再生し始めるような印象深い歌い方だ。Pavlov's〜のOh Mario, という歌いだしなど、ほんとうにぞくぞくする。
なぜこんな音作りができるのだろう。それはやはりこのアルバムがソロ・アルバムではなく、バックミュージションとの共同作業によって作られたことが大きいのだろう。しかしそれが仲間内の楽しみに終わらないところが、Aimee Mannというミュージシャンの職人芸のなせるわざなのだろう。どこにもあるようでいて、実はどこでも得られないような、コマーシャルに十分なれるのに、安易な使い回しの手法は一切ないというストイックさに貫かれているアルバムだ。この作品は上質なポップアルバムとして、年を経ても聞き継がれていくであろう名盤である。

