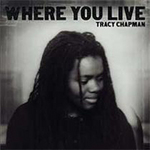フランス文法の非ラテン語化
1. 形容詞の独立
ラテン語文法において、adjectifはsubstantifと同じ語形変化をすることから、品詞の一分類とは見なされていなかった。 substantifもadjectifも「名詞」のカテゴリーであった。フランス文法もこれを踏襲していたが、adjectifを初めて独立させたのは、l'abbé Gabriel Girardであった(Les vrais principes de la langue française, 1747)。以後、この方式がBeauzé, Court de Gébelin, Domergue, Lhomondによって継承される。
2. 語形変化の放棄
16、17世紀のフランス文法の伝統では、フランス語の名詞は、ラテン語同様、格変化をすると教えられていた。フランス語とラテン語を並列に扱うことによって、フランス語をラテン語の学習をするための、準備段階としていたのである。もちろん、教師も文法家も、フランス語から格変化は消滅していることは知っていたが、ラテン語の衰退を先延ばしにするためにこのような策を講じたのである。たとえばRestautは、先達と同じく、「nominatif(主格)はle Prince, génitif(属格)はdu Prince、accusatif(奪格)はle Prince」と記述している。 Restaut自身、フランス語の格は存在しないことは自明であり、「語尾は、単数と複数、男性形と女性形を区別するためにあり、ある名詞と別の語の関係を明示するものではありえない」と述べているにも関わらずである。
1670年から1750年にかけて、学校のフランス語文法の教科書は、格体系のフランス化を、統辞のレベルで考えることにより、格を nominatif, datif(与格), génitifの3つにまとめるようになる。しかしそれは、ラテン語の体系に模してフランス語を叙述するだけであり、たとえば、àに先立たれる名詞はすべてdatifとみなされた。こうしたラテン語とフランス語の間に起こる齟齬があったにも関わらず、ラテン語格体系のフランス化は18世紀なかごろまで続く。こうした格変化の放棄は、1794年のNoël-François de WaillyのGrammaire française, ou la manière dont les personnes polies et les bons auteurs ont coutume de parler et d'écrire (1763年の再版時にPrincipes généraux et particuliers de la langue françaiseと名前を改称)になってようやくなされたのである。
18世紀を通じて、Restautの著作とDe Waillyの著作は競合関係にあったが、徐々にDe Waillyが優勢となる。これはつづり字の教育が、基本文法の教育よりも重要視されるようになった流れと期を同じくしている。しかしながら1810年まで、フランス語の名詞の格変化は数々の文法テキストに残っていたのである。
3. 主格、«un cas particulier»
nominatifという用語は、フランス語文法の中でも使われ、その後sujetという用語が使われるようになるのだが、両者は同義語ではない。sujetとは「話題」であり、論理哲学では、「文の主辞」である。一方nominatifは格変化とは関係がなく、「動詞と一致をする語」という意味である。このように文法用語として、フランス文法においては、長らくこの「nominatif du verbe 動詞の主語」という言い方がなされた。
Propositionという概念の導入によって、sujetとcomplémentというコンセプトが広まったが、nomnatifと長い間共存することになる。sujetが広く優勢になるのは、1780年代のことである。
4. «particule»の消滅
Parciculeという用語の定義は、明確になされることはなく、たとえばイエズス会の教育者たちは、この中に、ラテン語学習を単純化するために、学習者にとって学習上の難問をこのカテゴリーに入れていた。
基本的にはparticuleは前置詞、接続詞、代名詞、冠詞を指す。18世紀のフランス語文法の発展にあわせて、particuleという概念もあらためて厳密さをもって文法理論の中に取り込まれるようになる。Pariculeが、完全にひとつの品詞として確立できるかどうかということをめぐり、Dangeau, Girardがそれぞれの著作(1717, 1747)でparticuleという章をさくが、実際には後継者はあらわれず、Restaut, Beauzée, Domergue, Lhomondもparticuleについては言及をしてない。また一般文法でも、純粋に便宜的に役に立つだけのこのカテゴリを認めていない。この一般文法と文法分析の勝利とともに、particuleは、他の品詞分類に改称されていく。しかしそれは1830年代に入ってからのことである。というのも、 particuleに何らかの意味を与えようとした教師や学校機関の長がいたからである。ある者は、たとえばpréfixeのような語をさすことで、他の品詞とは分類を分けたり、不変化語をここにまとめたり、と様々な見解が出されたが、対象が「小辞」であることを除いては、統一したものはなかった。
5. いくつかの痕跡
フランス語文法の非ラテン語化は、いくつもの跡をのこしている。たとえばrégimeはラテン語文法から生まれた概念だが、19世紀半ばまでフランス語の学校文法の中に残っていた。substantifはadjectifが品詞として認知されたときに、nomにとって代わるはずであったが、 Lhomond(1780)、Chapsal(1823)は依然としてsubstantifを使っていた。«nom ou substantif»という表記は実に20世紀初頭まで続くこととなる。
«Degré de signification»は、フランス語文法に定着しているが、それにも関わらずcomparatif, superlatifは教科書に留められ使われ続けている。
動詞の活用分類は、ラテン語の動詞が4つに分類されていたことから、それにならってフランス語も-er, -ir, -oir, -reの4つに分類されていた。最終的に3つのグループにまとめる分類方法が大勢を占めるのは19世紀末になってからである。言語学者たちは、4つのカテゴリーのうち、2つだけが現在も「生きていて」、新しい動詞を造ることができる、それに対して、他の2つはそうしたさまざまな活用をする、古い動詞が入れられているという根底的な違いがあるとしたのである。