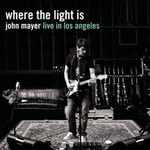60年代東海岸でソウル音楽のプロデューサー、作曲家として活躍したジェリー・ラゴヴォイの作品集である。タイトルに1953ー2003とあるように、その仕事は60年代だけではなく、20世紀後半の実に50年にわたっている。
60年代東海岸でソウル音楽のプロデューサー、作曲家として活躍したジェリー・ラゴヴォイの作品集である。タイトルに1953ー2003とあるように、その仕事は60年代だけではなく、20世紀後半の実に50年にわたっている。
有名な曲としてはローリング・ストーンズ、アーマ・トーマスがカバーしたTime is on my side。このアルバムにはオリジナルの、トロンボーン奏者Kai Windingによる演奏が収められている。トロンボーンがそこはかとない哀愁を漂わせるが、ヴォーカルの入ったヴァージョンの方がソウル音楽の黒さを感じさせる。
ジャニス・ジョプリンがカバーしたCry baby。オリジナルはGarnet Mimms & The Enchantersで、63年に発表されビルボードチャート4位、R&Bチャートでは1位とヒットしている。ラゴヴォイはバート・バーンズと多くの仕事をしているが、これが最初期のもの。
そして、誰でもが一度は耳にしたことがあるであろう。Pata Pata。この曲は、歌い手であるMiriam Makebaのアフリカン・フォークに、ラゴヴォイがアメリカン・バラードの雰囲気を脚色したダンスナンバー。
他にもGood Lovin'など、多くのカバー曲をもつラゴヴォイの仕事は、ソウルやブルーズそしてアカペラなどの黒人文化の音楽を、決して黒人だけのものではなく、その音楽自体のもつ魅力に親しみやすさを与えて、商業ベースにのせたことにあるだろう。
特に彼が得意にしたのは、ミディアム・テンポで少し哀愁を漂わせながらも、さびで一気に歌い上げる作風ではないだろうか。ジャニス・ジョプリンの歌い方もまさにそんな感じだが、Carl Hallという女性ソウル歌手も、多少ハスキーな声をもつが、泥臭くはない。スローなところの情感とさびでのシャウトの対照が実に見事で、魅力的な歌手だ。彼女の歌うYou don't Know Nothing About Loveは、この作品集の中でももっとも聞かせる一曲である。ちなみにここには収められていないが、この曲は、ラゴヴォイがプロデュースしたHoward Tateの同名アルバムにも収められてる。
Howard Tateとラゴヴォイの付き合いは長く、この作品集にも3曲と一番多く収められている。64年のYou're Looking Good、72年のアルバム制作後の74年のシングルAin't Got Nobody To GIve It To、そして、歌手をやめ、不遇な環境に身を落とし、辛酸をなめるような生活をずっとしていたTateに、ラゴヴォイがプロデューサーとして手を差し伸べたかのような2003年の復帰アルバムから、60年代の曲の再録Get it while you can。この曲が作品集の最後に収められている。若い頃の力強い歌い方ではなく、むしろ淡々を歌われるだけに、二人の歩んできた人生の道のりを感じさせ、胸をうつ好演である。
 歌はどのように生まれるのか。ことばはまず声であり、声は何よりもひとつの音である。だから単にハミングしたり、あるいは叫んだりしても、それは当然音楽とみなされる。ときには声そのものが楽器のように聞こえてくることもあるだろう。
歌はどのように生まれるのか。ことばはまず声であり、声は何よりもひとつの音である。だから単にハミングしたり、あるいは叫んだりしても、それは当然音楽とみなされる。ときには声そのものが楽器のように聞こえてくることもあるだろう。
しかし歌には多く歌詞がある。声は音でありながらも、それはことばとして同時に意味を伝える。朗読と歌は違うと直感的にわかるように、歌にはそれを歌だと私たちに思わさせる規則が、言い換えれば制限がある。それが抑揚やリズムだ。したがって、そのような歌に課せられる制約が、同じことばであっても、歌詞に独自の特徴を与える。フランスのミュージシャンの場合、この歌詞のオリジナリティによって評価されることが多い。それは定型詩にも見られる韻や、言い回しに乗せたことば遊びの妙でもある。
そしてまた歌は、ロマン主義の時代に言われた民族の覚醒という概念から見れば、古来からの魂の継続性の表象とみなされる。たとえばブルターニュにおいてケルト文化の復興および伝承に携わる人々にとって、民族楽器を用いて、ブルトン(ブレーズ)語で歌を歌うことは、彼らの精神的支柱となる活動であると言っても差し支えないのではないか。
だが文化は決して単層ではありえない。文化はたえず浸食しあい、多層的な表象を作り上げる。かつてアラビア詩を触媒としてトゥルバドゥールが生まれたように、現在でもフランスでは、とくにラップやエレクトロなどの音楽が、国籍を無化する形で生まれ続けている。
Maggaというミュージシャンについて調べてみてもほとんど詳しいことはわからない。10年ほどグループで活動した後、ソロに転向したらしい。その顔立ちから北アフリカ系のフランス人であろう。以前FNACでファーストを試聴して購入。その音楽は英米ロックの影響を受けたアコースティックフォークで、その外見が伺わせる民族的な背景はほとんど皆無だった。
しかし今回やはりFNACで見つけたセカンド(だと思う)には、イスラム的な意匠がかなり色濃く施されている。ジャケットしかり。タイトル曲Caravane du désertではサハラ砂漠の遊牧民トゥアレグ族が使うとされる楽器を奏でる女性が歌われる。また1曲目、2曲目はアラビア音楽の旋律がそのまま使われている。そして歌詞の主人公の男は「王妃たちの心を盗む男」として描かれる。
なぜここまで彼の作る音楽に民族性が反映しているのかはわからない。ファーストと同じアコースティックギターを基調としながらも、歌詞はずっと寓話性が高く、その哀愁はアラビア音楽に似た哀愁だ。エキゾティックな情景、女を前にして、夢幻の世界に浸る男、野生の熱、動物の息。音楽も歌詞も素直なまでに、アラビア音楽の表象をそのままなぞるようなアルバムになっている。
ようやく見つけたビデオの本人は、背が高く、細長い顔立ちで、アルバムの印象よりずっと内省的な青年であった。これほどまでに民族性を意図づけながらも、実は彼のピッキングによるギターの音はBen Wattを思いださせる。特にラストの、少しエコーがかかったギターの音色、憂いのあるヴォーカルは、Ben Wattの『ノース・マリン・ドライブ』だ。海辺の波にも似て、ギターの音色がせつなく近づいては、遠ざかってゆく。
音楽には定型がつきまとう。それらの定型の混ぜ合わせの妙がひとつのオリジナリティとなる。しかしこのアルバムではまださまざまな要素が分離している印象を受ける。それでもやはりBen Wattに似て、彼の声、ギターにはきわめてまれな透明感をたたえている。繊細で素直なこの音世界こそ、彼のオリジナリティなのだろう。
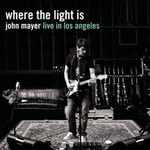 John Mayerは自分が最も聞きそうにないミュージシャンである。なにしろ顔よし、声よし、ギターよし。自分が惹かれる顔は、たとえば上前歯の2本の間にすきまがあるような顔。声は高音で裏返ってしまうようなへろへろ声。ギターは、弦が弛んでるのではと思うような、しまりのない音。その理想はKinksのLolaのB面一曲目All this tomorrowだ。イントロのギターのなさけなさ、ぐ〜っともりあがっていくところのRayの鼻づまり声。そしてあのニヒルな顔。すべてが好きだ。
John Mayerは自分が最も聞きそうにないミュージシャンである。なにしろ顔よし、声よし、ギターよし。自分が惹かれる顔は、たとえば上前歯の2本の間にすきまがあるような顔。声は高音で裏返ってしまうようなへろへろ声。ギターは、弦が弛んでるのではと思うような、しまりのない音。その理想はKinksのLolaのB面一曲目All this tomorrowだ。イントロのギターのなさけなさ、ぐ〜っともりあがっていくところのRayの鼻づまり声。そしてあのニヒルな顔。すべてが好きだ。
それに比べるとJohn Mayerはギターの弦は張り詰めている。声に一点の曇りもない。そしてあのルックス(アメリカ的美男子!)。どこを聞けばと思ったのだが、やはりアメリカン・ロックに対する憧憬の深さと、真のオリジナリティにまで達する技量の深さだろうか。ジェフ・ベックやクラプトンにはどうしても感動できないのに、彼のギターの音色にはほんとうに翻弄される。そしてヴォーカルはギターと同じく変幻自在。歌いながら、ギターをこれほどまでに弾くのだからまたすごい!
それから彼の魅力のひとつは、最近のスマートなブルースの影に多少隠れているが、90年代以降のミュージシャンぽい叙情性だ。この内省的ともおもえるメロディの美しさが、彼の音楽を手に届く等身大のものにしてくれる。とはいえおそらくヒットしたはずのWaiting on the world to changeは、一聴して親しみやすい、なつかしさを感じさせるメロディラインだが、Paul Youngほどではなく、どちらかといえば凡庸で叙情性とはほど遠い。それよりもアコースティックということもあるのだろう、Stop this trainや、名曲Daughtersは、確かなギターワークに裏打ちされた叙情性がうまく表現されている。特にDaughtersの最後、彼の声が高くなっていくところは、このアルバムの最高の瞬間だ。このアコースティックセットはこのライブアルバムの聞きどころだろう。
とはいえ実際は6曲だけ。なんだかここのパートは余技にすぎないと言っているかのようである。
 60年代東海岸でソウル音楽のプロデューサー、作曲家として活躍したジェリー・ラゴヴォイの作品集である。タイトルに1953ー2003とあるように、その仕事は60年代だけではなく、20世紀後半の実に50年にわたっている。
60年代東海岸でソウル音楽のプロデューサー、作曲家として活躍したジェリー・ラゴヴォイの作品集である。タイトルに1953ー2003とあるように、その仕事は60年代だけではなく、20世紀後半の実に50年にわたっている。