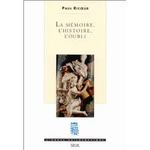テキストは、Etienne Pasquier, Recherches de la France(1561)の引用から始まる。 Pasquierはフランス語がラテン語に匹敵するだけの価値をもち、イタリア語よりも優れた言語であることを同書で述べた。しかしフランス語の出自が「俗なる=崩れた」フランス語であり、また、中世における言語の混乱状態(様々なidiomeの存在)を持っていることは、フランス語を顕揚する上で、おおきな支障となった。ここからフランス語の起源の神話形成が始まるのである。崩れたものではなく、純化された起源、あるいはラテン語以外の起源の探求、単一性と一貫性の検証、そしてIle-de-France優位の論証付けなどである。Cerquiligniは、français orphelineが正統なる両親=出自を求めていく歴史を緻密に跡づけていく。
Chapitre I MISERE DE FILIATION
第一章Misère de filiationは、フランス語とラテン語の関係をめぐる考察である。法律文書におけるフランス語使用を義務づけたヴィレ=コトレの勅令(1539)や、Louis Meigretによる最初のフランス語文法書(1550)が示すように、16世紀半ば以降、フランス語が支配を拡大するようになった。それと同時にこの言語の起源の探求が行なわれるようになる。そして、ヘブライ、ギリシア、ケルト諸語(ケルトマニーの強い運動があるとは言え)ではなく、ラテン語をその起源とするためには、なぜラテン語とフランス語は、屈折、語順、単語、どれをとってもかくも離れているのかを証明しなくてはならなかった(p.15.)。ここで生まれるのは、Claude Faucher(Recueil des Antiquités gauloises et françoises, 1579 ; Recueil de l'origine de la langue et poésie françoise, 1581)やGilles Ménageのような混合説である。しかしケルト系、ゲルマン系の影響を認めながらも、柱となるラテン語を古典ラテン語に求めていたところに限界があった。
こうした«érudits»には堪え難い事実、それがラテン語には古典ラテン語以外に、もうひとつのラテン語、こちらは古典ラテン語より劣った、田舎の、そして民衆のラテン語である。このラテン語こそ、フランス語の起源となったラテン語である。この考え方が主張されるには18世紀を待たねばならない。 Cerquigliniが重要視するのがPierre-Nicolas Bonamyである。BonamyはSur l'introduction de la langue latine dans les Gaulesのなかで、フランス語の起源は「日常表現の中で話され、使われていたラテン語に他ならない」と明確に主張する(p.18.)。フランス語の起源を俗ラテン語とする考え方は、この時点においても大胆きわまりないものであった。
18世紀におけるフランス語は矛盾を抱えていた。それは普遍的な言語として、ヨーロッパに拡張する傍らで、フランス語は17世紀に古典主義の作家によって完成され、以後は頽廃をしていくしかないという矛盾である。したがって思潮はpurismeという言葉通り、規範からの逸脱を許さない保守主義的傾向にはいっていた。そうした傾向のなかで、名声を克ち得たフランス語が「泥にまみれた出自」(=une source bien bourbeuse, p.21)であるという事実こそ、文法家たちをメランコリーに追い込むものであった。
しかし、メランコリーの要因は、その親となるラテン語の性質だけではなく、様々な他の言語との接触による「クレオール化」にもあった (p.23.)。つまり、10世紀におけるフランス語のプロトタイプは、口語としてのラテン語が、ゴロワと接触し、そして続いてフランク、すなわちゲルマンとの接触をうけて形成されたのである(そしてゲルマンとの接触が強かった北部ではlangue d'oilが、弱かった南部ではlangue d'ocが形成されることとなる)。
ならば、puristeたちはどのような方向へ向かうのか?それはフランス語を上品で、ラテン語に匹敵するものにするという古来からの欲求の充足である。それが新旧論争における、Modernes派の勝利である。ここでフランス語の顕彰は、王を讃えることと同義となる(p.26.)。 Dominique BouhoursのEntretien d'Ariste et d'Eugèneをひきながら、Cerquigliniは、出自不明のフランス語でありながら、その比類なき精髄(génie)、大作家による賞揚、そしてフランス王によってもちいられることによって、フランス語が「偉大さ」を獲得する過程を追う。
出自の不明をあがなう方法としては、上述のフランス語を高貴なものにする以外に、フランス語の「ラテン語化」が挙げられる(p.28.)。ラテン語からの借用による新語の増加(たとえば、entierに対応するintègre)、つづり字(書かれた文字としてのフランス語は、ラテン語に典拠する)におけるラテン性の保持である。ここからフランス語を改革することに対する論争の激しさも理解できる。またその言語的アイデンティティを脅かすようなヴァリエーションの存在への嫌悪も理解できる。
こうした単一性を乱すものへの恐れは、政治的理由とも関係する。たとえば19世紀のRaynouardがlangue d'ocはlangue d'oilの前身となる形式だということで、単一性のほころびを回避する(p.32.)。Langue d'ocのラテン語との近親性、文学的成果などにもかかわらず、言語的多様性は、「豊かさ」(abondance)ではなく、「放棄」(abandon) に結びついてしまう。それはすなわち、地域の口語への軽蔑や、patoisの撲滅、第三共和政の代表的ロマニスト、Paul MeyerやGaston Parisのgallo-romanに本質的な単一性を認めようとする試み、といった政治的、歴史的、そして学問的態度にまで現れてくるのである。
Chapitre II EPIPHANIE PARISIENNE
この章では、パリの言葉が、フランス語の規範とみなされるに至った歴史的経緯を振り返る。Cerquigliniによれば、言語的優位性をある地域に与えるならば、それはどこがふさわしいかという問いは、歴史的には二つの時代、16世紀と19世紀に検討されることになる。この章では、16世紀にパリをその地として選ぶに至った経緯を跡づける。
まず、パリの言語的優位性の考えが、同時代のイギリスから出てきた(フランス語を外国語として考察する時代に入ったことを意味する)ことに言及した後、フランスにおいては、言語は変化する、要は、頽廃に向かっているという悲壮な考えから出発しているために、当初は、パリの言葉も他の方言と同じく、不完全なものであるという認識があったことを指摘する。これはたとえばGeoffroy Tory(Champ Fleury, 1529, p.39)のように、そうした認識をもつ人物がラテン語学者であったためである。また同じ認識にたつJacques Duboisは、フランス語をラテン語のような当初の純粋性を取り戻す意図をもって、文法論を書くが、その典拠となったのはノルマンディー、ピカルディー方言であった。Charles de Bovellesはよりいっそう悲観的に、言語の混乱状態を嘆く。パリの言葉もその分散してしまった一方言に過ぎない。
したがって、パリの優位性という考えが出てくるためには、まずは俗なる言語に対する肯定的な考え方が始まらないといけない。これは同時に俗なる言語としてのフランス語を、そのもの自体として考察するということを意味する。その第一歩がLouis MeigretによるLe Tretté de la Grammere Françoezeである。ここでMeigretは、正しい用法を、パリ、すなわちフランス宮廷、すなわち王とその一族に求めるのである(p.43.)。この問題を考えるにあたっては次の二つの要素を考慮する必要がある。
まず、言語の規範を問うときにおける社会階層という観点である。Ile-de-Franceから特にパリに言語的優位性を与える考え方が広まる。しかし優位性は地理的な意味だけではなく社会的な意味でも問われなくてはならない。たとえばHenri Estienneにおいて、規範はパリのエリートたちの言語である。これは社会的にみて、パリは一様ではないことを示している。たとえばRamusは、パリの民衆のことばに規範をもとめる。しかしパリの民衆の口語は、以後価値のないものとして貶められ、社会階層的な亀裂が生まれる。つまり言語の規範化を問うことはこの時点ですでに社会階層的要素を含み込むものだったのである(p.46.)
次にEtienne Pasquierによる宮廷言語の批判である。ひとつはフランス語の最もよい用法フランソワ一世の時世においてのみ達成されたということ。二つ目は、パリの優位性により、他の口語はその正当性を失っていくが、そうした言語から、パリの言葉は様々な言葉を吸収していくということである。
Chapitre III LA FABRIQUE DE L'ORIGINE
この章では、19世紀におけるフランス語の起源についての思潮を扱う。19世紀とは史的言語学が形成された世紀である。印欧語族の系譜について科学的に検証され、フランス語がラテン語起源であることはもはや前提となった。それと同時に、ナショナリスムの勃興によって、国民語、つまり国語としての言語の起源の探求が始まることになる。そして、フランスにおいては、この国民的共同体は中世に求められることになるのだが、このことがまた失望を生んだ。そしてそもそもがこの考え方自体が誤りに満ちたものだったのである。
失望-それは、中世に国語の起源を求める場合、その資料となるのは、文学作品であったが、それがおおよそ統一的な基準を欠いたヴァリアントの集積として、目の前に呈されたからである。その意味でこの時代の学問は、一見ばらばらな状態にみえているテキスト間をつなぐような法則性を求めていくことになる。しかしそれがはたして真正なるものなのか?ここに疑問が生まれてくる。
では実際にはどのような解決策がはかれるだろうか?ひとつは文学作品ではなく、尚書局の証書の現物を資料として用いることである。日付も場所も確定できるし、公的文書である以上、書き手の主観も混じることがないので、まさに信用できる資料、というわけだ。こうして1821年、古文書を解読する専門家を要請する期間が設置され、以後、19世紀を通じ、現在にいたるまで、古文書の出版がなされる足場が築かれた。問題はフランス語で書かれたといえる公式文書は、13世紀以降にしか現れず、それ以前のものはやはり文学作品に頼る必要がある。しかし、国家語としてのフランス語を考えるには、こうしたテキストに現れる言葉はあまりにも一貫性を欠いたものであった。
この問題を解消するのが文献学の読解方法の厳密な適用である。それにより、変質前のテキストと言語の、完全な形での復元が可能であるとされる。 Lachmannの方法によれば、数学的方法によって、正しい読み方を決定することが可能であり、それによって、作品のオリジナルな状態、すなわち、作者が最初の書記に書き取られた状態、誤りのない状態が復元できるとする。CerquigliniはこうしたLachmannの方法論に、初期の印欧語族研究と同様の、比較という方法論、復元の欲求、そして始源の状態からの頽廃という要素を指摘する。これは始源から線上につらなる、過ちの系譜であって、それゆえにヴァリアントが生まれるのだという考え方である。Lachmannによれば、同じ間違いはそのまま引き継がれ、またある一つのmanuscritと複数のmanuscritの対立がある場合は、後者に真正さがあるとする。
Cerquigliniが批判するのはこの、真正なるテキストという大前提、それに伴う著者という独自の存在それ自身である。つまり Cerquigliniによれば、中世の作品というものは、口語にきわめて近い書き言葉の文化に属しており、著者概念、さらにはそれを取り巻く権威という概念はさらさらなく、常なる書き換え、解釈をもたらすものであった(p.58.)。これがラテン語、ギリシア語を対象とする文献学と異なる点である。
たとえば聖アレクシスの校訂を出したGaston Parisは実証文献学の目的は「作者の手を離れた瞬間の作品の形式をできる限り復元すること」(p.61.)、「オリジナル」(p.62.)をできる限り復元することであった。しかしCerquigliniはこのParisの作業が必ずしも「数学的方法」にのっとって行なわれたわけではないことを、例証する。Parisの主眼にあったのは、古フランス語によるテキストの復元であり、その意味ではParis自身が最もオリジナルに近いとする manuscritに準拠しない解釈がいくつも現れている。その結果、古フランス語自体(Parisによれば11世紀なかば)がParisの手によって「純粋、優美、簡潔」(p.64.)なものにされていくのである。つまりは文学作品を通して、ラテン語に似た簡素さをそなえたまま生まれたフランス語、優美なるフランス語が「発見」されたのである。しかしこの「発見」は、Parisによる「始源の創作」(fiction de langue primitive)に他ならない。冠詞、代名詞、前置詞をフランス語における夾雑物、ロマネスク様式に12,13世紀になって付け加えられた装飾と Parisは見なしているが、これらはすでに俗ラテン語の中にみとめられる。Parisはしかしその点に言及することはないのである。
さらにParisはこの言語の地理的起源をIle-de-France、とりわけParisに置こうとする。Parisによる方言数はきわめて数が少ない。その中でも断定はしないがSaint-Germain-des-Présという中心がParisの中で浮かび上がってくるのである。
こうして19世紀におけるParisを代表とする文献学は、異本の中から純粋な言語を構築(=再現)することによって、冒頭で述べたように、国民語を中世において起源づけることに寄与したのである。
一方、異本の中にみつかる規則性を欠き、つづり字もばらばらで、一貫性を欠いた状態、そのものが始源のフランス語であると考える学者もいた。たとえばFrançois Guessardは、このフランス語を、言語そのものの子ども時代と考える。
しかし、大方の学者たちは、これとは逆の方向を辿る。言語の規則性の探究において注目されるのは、文法性である。たとえば現在完全に規則化されている複数の-sは、古フランス語においては、きわめて不確か(aléatoire)なものであった(p.68.)。この現象は古フランス語の整合性を持ち合わせていないことの代表的な例であった。しかしプロヴァンス語専門家であるFrançois Raynouardは、18世紀の南仏語研究者Hughes Faiditを読み、-sの使用に規則性があることを示した(p.70.のCerquigliniの引用を参照のこと)。Raynouardの学説は、形態論的にみて規則性(語の位置の自由を規則によって裏打ちされたものとして保証する規則,p.72.)が働いていることを証し、さらにその規則性は曲用というラテン語との系統をしめすものであった。
この結論に対し、前述のGuessardはさっそく批判を開始するが、AmpèreやBurguyといった古フランス語研究者は賛辞を惜しまない。Burguyは、この形態論的規則性が示すラテン語との親縁性によって、古フランス語は、現在のフランス語よりも調和のとれた明晰な言語であるとする。つまり18世紀にRivarolがフランス語の明証性の根拠とした語順の厳密さという根拠にまっこうから対立する。この根底には起源としての言語を完成したもの、均整のとれたものであってほしいという学者たちの欲望があるのである。
Chapitre IV LA RAISON DIALECTALE
フランスの言語学史における1830年から1860年の30年間は、言語有機体説と国民語としての言語の起源の探究、すなわち、土地の言葉=方言、俚語の探究と2つの傾向が交錯する時代であった。たとえばGustave Fallot(1807-1836)は、この両方について考察を進めた言語学者であった。
言語有機体説においては、Fallotは、あらゆる言語はという3段階にわたる円環を巡るとする(p.77.)。そしてフランス語ももちろん、内在的な法則に典型的に従っている言語であり、またfixationの段階は中世に相当するとした。Fallotが対象として選択するのは13世紀の公的文書であり、目的はそこに使われているフランス語から、文法的規則性を見いだすことである。ここでCerquigliniが注目するのは、Fallotが、Gaston Parisのように始源における言語の完全性というものは信じていず、また、混沌状態だとも捉えていない点である。Fallotによれば、13世紀は、ある完全な形態(=fixation)へ向かっていった時期なのである。
方言の重要視については、Fallotは方言に着目することによって、語の形態の分類が可能になるとする。
事実1830年代にはpatoisへの興味が再びわき上がってくる。patoisは長らく、矯正する対象であり、地域のヴァリエーションが学問の対象になるということがなかった。百科全書のpatoisの定義が示すように、これは頽廃した(corrompu)言葉だったのである。それが19世紀にはいって、考察の対象になったのには様々な理由が考えられる。1806年にMonbretによって行なわれた「放蕩息子」に関する方言調査はフランスにおける地理言語学の基礎を打ち立てた。このようなpatoisへの興味は、「民衆へのロマン主義的興味、過去への憧憬、オシアンの風景といった文学、南仏やブルターニュといった地方主義的運動、そして革命によって行き場を失った田舎貴族の自らの土地への回帰ちった政治」(p.82.)という三重の運動として考えることができる。
地方における失われた民族的過去を復権する試みが、patoisの再評価へとつながる。たとえばCharles NodierはNotions élémentaires de linguistique(1834)の中でpatoisが書き言葉よりも豊かであると主張し、patoisのことばはそのことばが形成された時の起源を宿しているとした。つまりpatoisの研究こそが、フランス語のかつての綴り字、発音を知る手立てになるのである。
またpatoisが、「言語の本質と言うだけではなく、具体的な存在物であり、フランス語の頽廃した形ではなく、原初形態」であるみなされる背景には、フランス語がラテン語起源であること、またラテン語からプロヴァンス語、そしてフランス語と変化したのではなく、ラテン語が、それぞれのロマンス語に分化したこと、それが「方言」となっていたという認識がある。
方言学は、当初応用音韻論として始まる。また地域を確定していくことも重要な作業であった。しかしこの確定という作業は困難を伴う。 Cerquigliniが引用するBrun-Trigaudによれば、19世紀を通じてlangue d'ocとLangue d'oïlの確定は大きな論点であった。
だが、話し言葉であるpatoisの探究は、地域の方言による発音の差が、つづり字のヴァリエーションをもたらすというように、混乱の理由を明示することができる。綴り字と音との関係を、3つの方言(ノルマンディ、ピカール、ブルゴーニュ)にまとめること、これがFallotが行なったことである。これは別の観点から言えば、Fallotが言語の単一性というものを認めていないということを意味する(p.89. l'ancienne langue laquelle ne possédait aucune langue)。そしてFallotにとって、この差異は、歴史的事象ではなく、言語に内在する特徴であり、歴史性によらないということは、パリを上位に置く言語的ヒエラルキーの正当性を認めないということを意味する。そして書くという行為が始まって(14世紀より前ではない)、共通語の形成がなされるようになる。混合と融合から書き言葉としてのフランス語が形成され、このことによってdialecteはpatoisへと座を追われることになる (p.90.)。
次にCerquigliniが検討するのは、「進歩と理性」、ジャコバン的思想をもつ言語学者、François Géninである。GéninはFallotの業績であった、ドイツの言語学、古フランスにおけるflexionの問題、そしてflexionに関連する方言の問題、これらをすべて否定する。Géninは、Fallotと同じく古フランス語の一貫性を求めようとするが、彼の目的はあくまでも始源の言語の根本的単一性を明るみにだすことにあった。Fallotの功績は、混沌としたものと思われていた中世の言語に方言化という考えを提出したことにあった。しかしこの方言化ということは、まさにフランス語は、最初の段階において「地域ごとのヴァリエーション」(p.94.)でしかないことになる。この点がジャコビニストGéninには到底受け入れられない点である。たとえば、規範と普遍をもとめるGéninにとって綴り字とは、音と文字が正確に一致しなくてはならないものである。表面上のヴァリアントに目先が狂い、古フランス語の単一性に気づいていないのがFallotの致命的欠点である。Géninにとって、国の中心はすでにパリに置かれ、フランス国民という一つの集団には、フランス語というひとつの言語があったのである。
同じく国民語の誕生を描いたのがJean-Jacques Ampère(p.99.)である。Ampèreが強調するのは、中世の言語における一貫性と法則性であり、共通語が現れたのは決して遅い時代ではない、という点である。Fallotの主張では、中世の言語の異質性だけが目立ってしまい、現在のフランス語とのつながりが見えなくしてしまう。またパリに中心を置き、francienのフランス語を区別し、そこに現在のフランス語との関連を直接づけたのもAmpèreであった。
Chapitre V LES RECITS DE LA GENESE
19世紀の国民語の起源の学説は大きく次の2つにまとめることができる。一方はFallot, Littré, Brachetの系譜で、古フランス語の諸方言にはみな同等であり、統一化は遅くになってからであるという立場。他方は、Ampère, Génin, d'Abel du Chevalletの系譜で、中央のフランス語によって統一化がはかられたという立場である。
この章でCerquigliniが最初に取り上げるのは、Emile Littréである。Littréは起源のフランス語と、フランスそれ自体の歴史的栄光(Charlemagneをはじめとしたヨーロッパにおけるフランスの覇権)を重ね合わせる(p.111.)。Littréが着目するのがflexionとdialectesである。
まずLittréがdéclinaisonを研究するのは、langue d'ocとlangue d'oïlだけが、ラテン語のdéclinaisonをとどめているからである。そしてdéclinaisonをもつ、すなわち学者語であるラテン語との系列関係をもつならば、この、ラテン語ほど複雑ではないものの、現代語ほど単純でもないこの古フランス語にpatois grossierという言葉をあてることはおかしいとする(p.112.)。こうして今まで貶められていた古フランス語をとして復権をはかったのである。以後歴史的にみると、14世紀にflexionの衰退が始まり、15世紀以降、現在のフランス語の形成が行なわれる。そして LittréがFallotと異なるのは、歴史的経緯を論証に用いる点である。封建制、俗文学の隆盛、こうした歴史的要素が古フランス語の再評価に役立ったのである。
dialecteについては、Littréはdialecteを4つにわける。ノルマンディ、ピカール、ブルゴーニュに加えて、フランス中心部が加わる。そしてあくまでもこれらは、patoisではなく、dialectesである。その意味で、中心部のフランス語も地方の一つのヴァリアントとみなされ、idiomeとpatoisにわかれてはいなかった(p.115.)。
La culture était égale partout : la Normandie, la Picardie, les bords de la Seine produisaient, à l'envi, trouvères, chansons de geste ou d'amour, fabliaux. Il est manifeste que les auteurs ne se conformaient pas à une langue littéraire commune et qu'ils composaient chacun dans le dialecte qui lui était propre.(Emile Littré, Histoire de la langue française. Etudes sur les origines, l'étymologie, la grammaire, les dialectes, la versification et les lettres au Moyen Age.I. p.127)
つまり、Littréにとって、フランス語という呼称は、抽象化でしかなく、諸方言の類似につけられた名前に過ぎないのである。そしてこの認識は、 Diez, Fallotの影響を受けながらも、やはり歴史的要素を考慮している点で、Littré独自のものである。それはつまり、封建制の形態である。地方が同等に併存する封建制という政治的形態こそが方言の分化状態を保証していたのである。そして王権の伸張による封建制の解体が、同時に中央部の方言の進展につながる。それが14世紀のことである。そしてそれはflexionを含んだ言語の消滅でもある。こうして14世紀を転回点とした13世紀から15世紀への、古フランス語から現代フランス語への変化をLittréは見事に描いてみせる。
しかし、現実には、歴史は長期持続の中であくまで変化していくのであり、断絶という見方をとらない。たとえば、987年、カペー朝の始まりにおいて、言語と政治の関連性がすでにみられる。つまりLittréがいう14世紀よりかなり前のことである。これに対してLittréは、王と諸侯との関係が、「臣従の誓い」をしないうちは、langue d'ocもlangue d'oïlも方言の状態のまま存在しつづけているとする(p.119)。だがlittré自身、変化や動きはないという主張の一方で、歴史事象における、王権の漸次的伸張、パリの言葉の漸次的伸張を認めてしまっている。
結局Littréは、中央部の方言が、それ以外の方言と融合し、現在のフランス語になったことをあくまでも主張し、中央部の方言が、はやばやと優位を占めたという考えをきっぱりと否定する。
Cerquigliniによれば、Littréの誤りは、パリの他地域への伸張をあまりにもはやく認めすぎた点にあった。しかし、言語学において、歴史的観点を取り込んだ点は、大いに評価できる。
Albin d'Abel du Chevalletも、歴史的見地になって中世における諸方言を考える。そしてFallotなどとくらべChevalletによる方言数は飛躍的に多い。こうした細分化の意図は、Ile-de-Franceの優位さを打ち立てるためである。この方言がフランス語という名で呼ばれることになり、また王権の伸張によって、この言語も同様に優越性を持つようになる。こうしたChevalletの考えには、はっきりした時代区分がなされていないが、12世紀にはこの優位性が獲得されたとする。Chevalletはその理由として、2人の証言をひく。Conon de BéchuneとAymon de Varennesである。たとえば、後者は自らの母語、リヨンの言葉で書くことを望まない。そしてこれ以降、Ile-de-Franceの言葉は、王権の補助も得て、広まっていったとする。ここにある物語(récit)は、フランスにおいて言語は、長らく国家が関与する問題であったことを示している。これは現代にまで続く物語となる。
Chapitre VI L'INVENTION DU FRANCIEN
1870年以降、共和国の体制が整うのと呼応するかのように、言語学もひとつの科学的学問として確立される。Gaston Paris, Paul Meyer, Michel Bréal, Arsène Darmesteterは、g言語学の学者・研究者として、学派を形成していく。言語学、文献学、文学など多方面における活躍、そして、綴り字改革や教育改革などの社会参加など、さまざまな形で共和国そのものに関わっていく言語学者たちの課題は、もはやラテン語という親の問題ではなく、フランス語そのものの起源をいつ、どこにおくかということであった。つまり俗ラテン語という失望の事実よりも、フランスの国土において、中世という時期にどのように起源を画定できるかということが問題となった。
この課題は、Fallot-Littréが古フランス語に規則性を見いだしたものの、結局は諸方言が同等にばらばらに存在するという見解の見直しを目的とする。それは、第3共和制において、教育現場で、共通の言語、すなわち、共和国と理性の言語であるフランス語を普及させるという使命と深くつながっている。つまり言語的統一のためにdialectの併存という事実は都合がわるいのである。
こうして言語学者たちは言語における規範の形成へと乗り出していく。その規範は、貴族の作り上げたものではなく、パリの大衆の言語実態から得られることが求められる。首都とは、国家と学問と言語(p.130)を一緒に結びつける場所なのである。特にパリの方言の優越性を証だてる理論的構築がセダンの戦いの後、本格化する。
その代表的な学者がGaston Parisである。Parisの言語観は、ドイツにおいて積み重ねられた言語有機体説からの脱却であり、言語の変化において歴史的要素を導入することであった。その考えが展開されるのが、1868年、ソルボンヌにおける開講講義«Grammaire historique de la langue française»である。
言語とは、社会的対象物であり、生活様式、時の権力、そして土地の影響を受ける。実際、言語は文化の伝達手段であり、文化もまた言語を形づくる(p.132.)。ただし、Parisは「歴史」と「科学」とに言語研究を分割するのではなく、両者を融合することを提案する。
Le développement du langage est dirigé par des lois qui lui sont propres, mais rigoureusement déterminés par des conditions historiques.
言語の発達は、それに本来的にそなわった法則によって導かれる。しかし、同時に歴史的条件によって厳密に規定されている。
しかし、この歴史的条件は、大きな力を持ち、言語の不動性に「打撃」を与えることになる。その大きな力とは、「文芸文化」(la culture littéraire)である。この文化こそが、言語における「慣用」と「恣意性」をもたらし、その一方で、言語に美的価値を与えることになるのである。
この歴史的手法においてフランス語が検討される。フランス語の歴史、それは間違いなく、ラテン語を起源とするものであり、そこからの継続性はもはや明らかである(la continuiét est indéniable, p.134.)。しかしラテン語が、様々な言語に分化したことが事実である以上、この「ばらばら状態」から出発するしかない。しかしParisの中でそれが最終的に「フランス語」として統一されることは、必然であった。そのために選ばれたのが、Ile-de-Franceの方言である。
Parisは5つの方言群を分類するが、その中にIle-de-Franceが含まれている。しかしそれは明確に画定されるのものではない。むしろ4つの方言に「含まれない」方言という消極的なものであった(p.135.)。しかしParisはIle-de-Franceという言葉がFrance という言葉と同時に生まれたものと考える。さらに奇妙なことにfrançaisという呼称を、なんの証拠もなく、langue d'ocに対立するものとみなす。CerquigliniはParisの理想を「ガロ=ロマン語のLangue d'ocとlangue d'oïlへの分裂、langue d'oïlの分裂とそれによって生まれる諸方言の同等性、Ile-de-Franceの言語の価値付け」と整理する(p.139.)。しかしParisの論拠では、時間軸の取り方の上で、方言の同等性の時代を設けるのは難しく、ひとつの言語の正当性を言う以上、その他の言語はpatoisと見なさざるを得なくなる。
それから20年後、文部大臣を含めたインテリ階層に向けて行なった、«Les parlers de France»と題する講演において、Parisは、国民語の浸透によりpatoisが死滅の状態に陥っているという前提から出発し、その保護を聴衆に向かって呼びかけるが、それは、patoisのヴァリアントがそのままラテン語から離れて以降の変化を跡づけるからという理由のためである。そして郷土の風習、民話に結びついたpatoisはこれまで、地元の愛好家によってもっぱら保存されていたが、今後は科学的学問の対象として取り扱うべきだと訴える。
またParisは、イタリアのロマンス語学者Ascoliが3つ目の言語としてfranco-provençalを提唱したことに対し、これまでの方言学の成果を無視してまで、その論を否定しようとする。それは、1870年の普仏戦争を契機とし、フランスが分割されることを拒否するためである。ここにはParisの矛盾が浮き彫りになっている。学者としては言語の分割が、言語の変化において必然であることを理解していながら、ジャコバン派としては、フランスの統一を希求してやまないからである。
この矛盾を解くために、Parisは3つの概念を提唱する。一つ目はcontinuum「連続帯」(p.145.)である。隣の住民との相互理解という点から、等語線を否定する。二つ目はlangue d'ocとlangue d'oïlの分割の否定である。フランスはタピスリーのような広がりであって、現実に境界を引くことは不可能であるとする。三つ目はdialecteではなくtrait dialectalという概念を入れることによる、分割地図ではなく、様々な特徴が偏在する地図を作り上げることである。こうした操作により、Paris はフランスの分割は避けようとする。そしてフランスにおける言語的単一性は、ラテン語からの変化の敷布での上から、Ile-de-Franceで編まれた一様な敷布がフランスを覆うことよによって実現したとする(p.147.)。
Ile-de-Franceの言葉は、Parisに言わせれば、古い形をほとんどそのままとどめている言語である。なぜこのようなファンタスム(p.149.)が可能になったのか?Parisにとっては、この言語は、中世においてはっきりとした言語的特徴を持った言語ではなく、他諸方言の均衡の上に形成された言語である。土着ではない分、どのようなoïlの話者によっても受け入れられる。こうしてIle-de-Franceの言葉は、最初からフランス語として、フランス全国土を覆っていったという考えをParisは強く表明する。
しかしIle-de-Franceの言葉を現代フランス語の始源とするには様々な欠点がある。たとえば、その地方の言葉をさす用語さえ存在していない。
このフランス中心部の言葉の重要性を深く検討したのは、文献学の分野で進んでいたドイツである。Ernest Merzkeはその博士論文(1880, 1881)において、13,14世紀の中心部の言葉の特徴を、他の言葉が持っている「特徴の欠如」(p.151.)にあるとする。続いてSuchier (1888)は、北の文学語の基礎となる方言を、中心部と類縁性をもつノルマンディー方言であるとする。そしてその方言が、中心のことば、Suchier の言うfrancischへと移っていったとする。これが中心部のことばをさす「名」であり、francienと翻訳される。
Parisはこのfrancienという考えを積極的に押し進める。Ferdinand Brunotが、Ile-de-Franceの言葉に対して、政治的状況以外の優位性を与えることに慎重であるのに対して、ParisはBrunotの仕事に敬意を払いながらも、まさにその点が不十分であるとする(p.156.)。Brunotはfrancienという言葉を用いないし、Ile-de- Franceで話されていた言葉の地理的な画定もしない。それにたいして、Parisは批判を行なうのである。
Brunotは1905年のHistoire de la langue françaiseの第一巻において、ついにfrancienという言葉を用いる。
Le francien ne doit pas être considéré comme un amalgame, une sorte de koiné, analogue à la koiné grecque. C'est essentiellement le parler d'une région, comme le normand est le parler d'une autre.(p.325.)
以後、francienは辞書の世界にも入っていくこととなる。francienという新語は、恣意性がみとめられず、領土を画定するでもなく、しかし中央部と関係し、さらにその名から国家的統一も喚起する。ここにきて、francienはfrançaisとみなされる。そしてParisにとっては、この言葉は最終的にparisienにもつながっていく。
以下続く