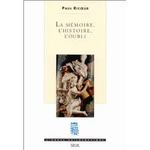タイトルLe cœur régulierは日本語にするならば「心の鎮まり」だろうか。小説中の一節«Sentir battre en moi un cœur régulier»(「自分の中で心臓が正しく鼓動しているのを感じること」)からこのタイトルがとられている。正しい鼓動とは、「正常で規則的で」ということだが、この小説のテーマが「喪の作業」である以上、動揺していた心がやがて、平常へと戻っていくことを指しているのであろう。
主人公のサラ(Sarah)は、弟ナタン(Nathan)を亡くし、それまでの完璧に見えた生活が、自らの本心ではなかったことに気づく。銀行員で高給取りの夫、私立に通う娘と息子、そして自らの仕事。そのいずれもが現代フランス社会での成功者の縮図となっている。それに対して子ども時代は双子のように仲の良かったナタンは、定職につかず、世間への憎悪をむき出しにし、アルコールのほとんど溺れつつ、小説を書いている。
そのナタンのほとんど自殺に近い死の知らせのあと、サラは、ナタンが旅行をし、みずからの心の平安を見いだした日本のある町へと旅立つ。その海岸に面した町は自殺の名所としても知られるが(おそらく東尋坊だろうか)、そこで自殺をしようとする者に声をかけて、自殺を思いとどまらせる「夏目」という人物と出会う。この町での滞在は、サラにとって、ナタンの存在を思いださせる機会であると同時に、ナタンと自分との関係、そして自分自身の喪の作業の機会ともなる。
喪の体験は、残された者に自らの生について問いかけをせまる。その生と死において、みずからの生活が丸裸にされるような体験だろう。今までの自らの価値、人生の歩み、人間関係そうしたものがむき出しになって、目の前に現れる。
「社会的成功」(réussite sociale)の中で暮らしていたかに思えたサラは、ナタンの死をきっかけに、その生活を離れ、ナタンとの関係において自分の存在を見つめ直してゆく。それが喪の作業なのだが、もちろん心は容易には鎮まらない。
「しかし本当には何も鎮まるものはなかった。私の中の何かがまだ抵抗している。何かが激しく泡立ち、神経がいらだつ。あの高みにのぼりたい、そして呼吸をする」
自分の存在とは、他者に取り巻かれた関係としての私である。しかし喪においては、そのような他者との関係性さえもが壊れてゆく。
「死が私たちの愛するものをとらえたとき、おたがいにどれほどなぐさめあおうとしても、それは不可能であり、堪え難くさえある」
愛する者の死によって、私たちは生き残った者同士の関係も変わらざるをえないのだ。死を契機として、お互いが疎遠になったり、あるいは親密になったりと、人間関係に変化がもたらされるのだ。その新たな人間関係を受け入れることが生き続けるということであろう。
この小説で描かれているサラとナタンはあまりにもfragileであり、その二人をとりまく人間たちはあまりにもindifférentである。その人物描写の深まりのなさが、時に読んでいるものに、登場人物をあまりにも幼稚な人間として伝えてしまうきらいがある。類型としての人間しか、ここでは行為していないかのようだ。約束事しか話さない人間たち。それがこの小説の弱さでもある。
 カール・ヤスパースの『戦争の罪を問う(責罪論)』は、ドイツの敗戦間もない45年から46年にかけて行われた講義をもとにして、刊行された小著である。この時期と平行してニュルベルク裁判が行われている。この裁判は、ヤスパースいわく「戦勝国が裁判所を構成している」という意味で「世界史上まったく新たな」裁判である(p.78.)。
カール・ヤスパースの『戦争の罪を問う(責罪論)』は、ドイツの敗戦間もない45年から46年にかけて行われた講義をもとにして、刊行された小著である。この時期と平行してニュルベルク裁判が行われている。この裁判は、ヤスパースいわく「戦勝国が裁判所を構成している」という意味で「世界史上まったく新たな」裁判である(p.78.)。
ヤスパースは、敗戦国ドイツの中でこの裁判を「侮辱」と受け取る風潮があることを認識した上で、この裁判に積極的な評価を表明している。裁判は「刑事裁判」であり、それはとりもなおさず、特定の個人を罰するのであり、集団的に民族を弾劾するわけではないからである。またドイツにふりそそぐ災厄は「当然の報い」なのでもない(p.73.)。この裁判では戦争が「正義と真理」のもとで、罪として裁けるかが課題であり、法が実現され、その法を敗戦国もふくめて、世界が承認できるかどうかの可能性がこの裁判にかかっているとする。この点こそヤスパースが信をかけて裁判を評価する理由である。ただその最も大きな価値は、実は「指導者たちの特定の犯罪の間に区別を立てて、決して集団的に民族を断罪するのではない」という点にある。後述するように、ここにはヤスパースの中に「指導者たち」と「私たち」の峻別があることがうかがえる。
ニュルンベルク裁判での罪は「刑法上の罪」であるが、ヤスパースはこの「罪の問題」の議論が感情的なものではなく、認識と思考に訴えるものとして、思考の対象として捉えられるものになるように、「罪」を分類する。
「刑法上の罪」の次のカテゴリーが「政治上の罪」である。すべての国民が刑法上の対象となって裁判を受けるわけではない。刑事責任はあくまでも個人を処罰の対象とする。それにたいして政治上の罪は、「国家の行為から生ずる結果に対してすべての公民が責任を負うこと」になる(p.50.)。この場合審判者は戦勝国であり(p.65.)、政治的に問われる責任とは、具体的に言うならば「戦勝国に対してわれわれの労働と給付能力とをもって責めを負い、敗戦国に課せられた通りの償い」(p.122.)をすることである。そしてヤスパースは「政治上の罪がヒットラーの刑事犯罪と同列のものではない」(p.141.)と強調している。
三つ目は「道徳上の罪」である。これは内心における罪の意識であり、審判者は「自己の良心」(p.49.)である。それは他者との関わりにおいて、自分の振る舞いにおける無関心、「怠慢、安易な順応」(p.52.)に対する責めである。四つ目は「形而上的な罪」である。
この罪の区別の主眼は、罪と「民族全体」との関係にある。たとえば刑事上の罪は、個人が負うものであり、「民族」が負うものではない。また道徳上の罪も個人が負うものであり、「民族」が負うことはそもそもが不合理である。
民族というくくり方に対する反論の根拠は、個人というものを民族へと還元して、あるいはあらゆる「類」(若者、年寄り、男、女)に還元して考えること、つまり類を実体とみなすことの不合理さにある。ヤスパースの議論では、罪は「民族」が背負うものではなく、「集団を有罪と断言」(p.64.)することは不可能であり、ドイツ国民が背負うのはあくまでも敗戦国の国民としてであって、民族としての存在そのものが弾劾されることは、むしろナチスの民族大虐殺と同じ考え方に立つものでありおおよそ受け入れられないとする。ヤスパースはこの弾劾の声を「お前らは民族として劣等、下劣であり、犯罪性をもち、人間の屑で、他のすべての民族とは別種のものだぞ」という表現に集約させる。確かにこのような、個人を集団に従属させる考え方は、ヤスパースの言うように「非人間的な行き方」(p.76.)であろう。
だが、ナチスそのものがドイツ民族国家のなかで生まれてきたことはどう解きうるのか。ナチスのような民族主義と全体主義が結びついたイデオロギーは、世界のどこであっても、そしていつの時代であっても<生まれうる>ことと、20世紀前半のドイツで<生まれた>という歴史的特殊性は区別して考えなくてはならないのではないか。
その意味で、ヤスパースの議論のなかで腑に落ちないのは、ナチスとナチスに加担した「彼ら」と、自らの妻がユダヤ系であったために公職を追われ苦難に道を歩まざるをえなかったヤスパース、そしてヤスパースと同じような境遇に貶められた人々の「私たち」とのあまりにもはっきりとした峻別である。刑事的な罪は確かに個人が負う。その意味で、ナチスの「犯罪」は、あくまでも「個人」が負う。しかしその「個人」と、私たち他者とは政治的な罪以外何の共通性もないのだろうか。
たとえば次のような辛辣な文章がある。
かれら(ヒットラーとその共犯者たち)は悔悟したり生まれ変わったりする能力がないらしい。かれらは要するにあれだけの人間なのだ。そういう人間はみずからも暴力によってのみ生きるのだから、かれらに対しては暴力を用いる以外に道がない。(p.97.)
ここでのヤスパースの言い回しは、自らが感情ではなく認識を、と説いた慎重な姿勢からははるかに遠い荒々しい憤懣に満ちている。彼らには道徳上の罪という意識がない、道徳の限界を超えてしまっているとヤスパースは言う。しかし彼の振る舞いは本当に少数の例外的な犯罪者の特殊な振る舞いなのだろうか。 またヤスパースは戦争の残虐行為、ユダヤ人の排斥は、「ドイツ人独特の残虐行為である」という弾劾を受けて、次のように言う。
他の諸国にあると認められる罪、ないしは他の諸国自身が自己の罪と認める罪は、すべて、ヒットラー・ドイツがおかしたたぐいの刑事犯罪たる罪ではなかった。かれらの罪は当時、事態を黙認して中途半端の態度をとったことであり、すなわち政治的な過誤であった。(p.150.)
ここでもヤスパースは、我々だけに(民族という単位としての我々)に罪があることを断固として否定し、罪が民族、ここでは人種に還元されることに反論する。
確かにヤスパースの民族と個人に対する考え方は正しい。私たちは集団に解消されえないことが、私たちを人間たらしめる存在の根源なのだ。しかしヤスパースが「われわれが劣等人種なのではない。どこでも人間は同じような属性をもっている。機会があれば政権を握って残忍なふるまいをする暴力的、犯罪的で、野蛮な才能をもつ少数者はどこにでもいるのだ」(p.154.)というとき、その少数者から「われわれ」は除外されていないだろうか。除外されているならば、その除外されうる根拠は何なのか。とくにヤスパースが民族に回収されない人間としての個の尊厳を解く時、この普遍性の希望を抱くとき、ともに普遍的な人間存在でありながら、どのようにして少数の犯罪者と、私たちが峻別されるのか。
ヤスパースは言う。「私はまず人間である。私は特殊的に見ればフリースラント人であり、大学教授であり、ドイツ人であり、他の集団と深い繋がりを、また深い浅いの差はあるにしても、私と接触するに至ったあらゆる団体との繋がりを持っている」(p.125.)。私は人間であるからこそ様々な属性を持っている多層的な存在である。だからこそ、関係の深さは異なっても、その多層性において、私たちは他者と繋がりうる。しかしその「私」を形成する多様な層のどこかに「ナチス性」はないのだろうか。その他の集団、すなわち、隣人にナチスはいないのだろうか。私が人間であり、人間だからこそ多層であり、だからこそ普遍的に他者とつながりうるとするならば、ナチスも「我が隣人」なはずである。その意味において「ナチス」と「私」による「私たち」において、罪について再考する必要があるのではないか。さらにこの「私たち」を措定したところに生まれてくる、「彼ら」すなわち、「被害者」についての関係性を問いつめていかなくてはならないのではないか。
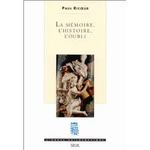 リクールがエピローグで扱うのは「赦し」(pardon)の問題である。90年代にフランスで「赦し」の問題がどのように議論されたかは、その歴史的状況をふまえ、訳者久米博の「記憶と歴史、忘却と赦し」に詳しい。その論文に言い尽くされている観があるが、多少本文に寄り添って内容を詳しくみていきたい。
リクールがエピローグで扱うのは「赦し」(pardon)の問題である。90年代にフランスで「赦し」の問題がどのように議論されたかは、その歴史的状況をふまえ、訳者久米博の「記憶と歴史、忘却と赦し」に詳しい。その論文に言い尽くされている観があるが、多少本文に寄り添って内容を詳しくみていきたい。
「第一節 赦しの方程式」で提出されるのは「過ちの深さ」と「赦しの高さ」である。そして久米が明晰にまとめているように、過ちと赦しを考える上で、リクールが依拠するのが「行為者」と「行為」の関係である。過ちとは、行為を行為者へと結びつける構造を持っている。私たちがある行為者を責めることができるのは、その行為者に行為の責任を帰することができる場合のみである(imputabilité帰責性)。
自己への帰責性の形式が「告白」である。そして告白において行われるのが想起の作用である。リクールは「想起自体は無実である」という。そこから告白においては、無実と有罪の区別のし難さが生まれてくる。ここでリクールが問題にしているのは、mémoire-souvenirとmémoire-réfléchieの区別であろう。前者は回想を散逸させる方に向かい、後者は罪悪感の中心を自己の記憶力の中に置く。
次に問題とされるのが行為の中にある悪と因果性の中にある悪の区別である。ここには人間の「存在」を考える上での本質的な議論があるように思われる。すなわちリクールは、存在を「実態、属性、偶有性」ではなく、むしろ「可能態と現実態」(puissance et acte)として捉えていると思われる。
最後に問題となれるのが、アダムの神話におけるイノセンスの喪失である。ここでの悪は、経験の中にありながらも、その悪が本質的に偶然的な悪であることから、リクールは、行為者と行為の間に距離がひかれることを指摘する。
このリクールの考えは、悪がたとえ永遠のものであっても、主体(行為者)自身は可能性に置かれていることを意味しないだろうか。もし罪と人が本質的に切り離しえないものであるならば、極端に言えばそれら罪人をすべて排除してしまえば、悪のない世界が到来するはずである。しかし現実に悪のない世界などありえないとすれば、悪は人間に内在するものではなく、むしろ人間という行為者からは離れたところに存在するものではないだろうか。
「赦しの高さ」では赦しは愛として語られる。「コリント信徒への第一の手紙」を引用しつつ、リクールは愛がもっとも大いなるものであるのは、それが「高さそのもの」であるからとする。そしてデリダにおける赦し、すなわち、「愛がすべてを赦すというなら、そのすべてには赦しえないものも含まれる」という言明に歩を合わせる。そしてやはりデリダと同じく、赦しを政治性と切り離すことを強調する。なぜならば、政治的舞台における赦しとは、計算や猿芝居であり、何らかの意図をもってなされるという意味で、赦しの概念が「汚染されてしまっている」からである。
「第二節 許しの精神のオデュッセイアー諸制度横断」では赦しと法と道徳の問題が扱われる。「犯罪的有罪性と時効なし」では、まず時効(prescription)と特赦(amnistie)の違いが述べられる。後者は心的痕跡も社会的痕跡も消してしまう「消滅」という傾向を持つのに対して、前者は時間の不可逆性、すなわち時間を遡ることの禁止を意味する。時効は結局社会の中で調整を果たす機能を有するわけだが、この点が赦しとは異なっている。なぜならば赦しは、「共通の平和への思い」を持った社会的機能だからである。
このように時効の意味を考察したあと、人道に反する罪において、時効がないことと赦しえないことの混同を批判する。時効がないことの対象は罪に対してであるが、罰はその罪をなした当人に及ぶ。このときリクールはその当人に対してなされることがあると言う。それは「考慮」(considération)である。この「考慮」とは、法的なレベルと道徳的なレベルの二つのレベルにわたってなされると考えられる。法的なレベルとは、訴訟によって、暴力が言説に、殺人が議論によってとってかわられるということ。その上で、道徳が法に対する裁きを行う。それによって「法の前の平等の具体的条件」に対してよりいっそうの配慮が働くのだ。
「政治的有罪性」では、ヤスパースの『責罪論』(『戦争の罪を問う』)にそいながら、「侵略者と被侵略者のそれぞれの位置を校正な距離関係に指定する」正義の言葉が重要とされる。
「道徳的有罪性」では、政治的な性質の集合的有罪性から、個人的責任へと移る。ここで問題になるのが民族、文化、宗教などの要求によって行われる植民地戦争のような歴史的事件における、公的なものと私的なものの絡み合いである。これに関してリクールは、コダーレの「諸国民の和解についての言説は、敬虔な願望にとどまる」ということばを引用する。
「第三節 赦しの精神のオデュッセイア - 交換の仲介」では、贈与との関連において赦しの問題が扱われる。赦し(pardon)と贈与(don)は言語的にも関連性があるが、ここでモースの『贈与論』を引用し、贈与と対立するのは交換ではなく、利益であること、贈与には「お返しを与えること」という双方性があることを指摘する。
この贈与に類似する赦しの双方向性の対極に置かれるのが「見返りなしに敵を愛すること」である。だがそこにも「敵を味方に変える」という愛が期待していることがある。この相互性に対してリクールは、高さと深さで検討した垂直的という非対称性を導入し、それを赦しの方程式とするのである。ここでリクールは南アフリカの「真実と和解」委員会の活動に言及する。この活動の中にリクールが見るのは政治的な和解とは異なる赦しのあり方である。それをリクールは「赦しの<ひそかな行為>」と呼ぶ。
「第四節 自己への回帰」の「赦しと約束」ではアレントの「活動」(action)に基づく、赦しと約束の相関性が検討される。活動の不確定さはひとつは過去、すなわち、過ぎ去ったものは制御できないという不可逆性であり、それに赦しが対応する。もうひとつは未来に対する予見不可能性であり、これに約束が対応する。そしてアレントが着目するのはふの二つの行為が複数存在に依存しているという点である。この複数性は、政治的と呼ばれ、アレントは福音書を解釈しながら、「神から赦されるのは人々が赦し合えるかいなかにかかっている」とする。しかしリクールは、このような赦しが政治性に近づいていくことに留保を示す。アレントが政治的友愛、尊敬という「社会的生活の人格化」(『人間の条件』p.380.)の根底をなす人間の複数存在で行使される力に対して、リクールはあくまで愛を置くのである。
この政治的解釈に対してリクールはあくまでも「行為者を行為から解放すること」(délier l'agent de son acte)を考え通す。そのために再び人間存在を「現実態と可能態」としての存在を強調する。行動の哲学、可能としての人間の存在である。リクールは言う:
「物語形式は、出来事の発生については取り返しがつかないが、けっして運命的ではない出来事の歴史的地位の根本的偶然性を保存している。人間の被造物としての地位からのこの逸脱は、もう一つの歴史の可能性をとっておく。それは悔い改めの行為によってそのつど開始され、時の経過のなかで善意とイノセンスが不意に出現するたびに区切られる歴史である」
人間の善としての根本存在への確信とともに、私たち人間の行為は歴史を生んでゆくのだ。運命ではない人間の可能性のもとに赦しの可能性も開かれてゆくのではないか。「有罪者は行為する能力を取り戻し、行為は継続する能力を取り戻す」とリクールは言う。
 数々のライブ音源のオーヴァーダビングと徹底的な切り貼り編集によって完璧なアルバムを作り出すザッパだが、このアルバムのもとになっているのは1975年5月の二日間のコンサートである。
数々のライブ音源のオーヴァーダビングと徹底的な切り貼り編集によって完璧なアルバムを作り出すザッパだが、このアルバムのもとになっているのは1975年5月の二日間のコンサートである。
その前年の74年にはApostropheとRoxy & Elsewhere, 75年に入ってからはOne Size Fits All。それに続いてだされたのがこのBongo Furyである。この時期は実験的な音楽というよりもバンドアンサンブルを前面に出し、ロック色の強い演奏を繰り広げていた時期である。それは緻密な計算による予定調和の世界と、超絶テクニックと音圧によって生まれるインプロヴィゼーションの予定不調和の世界がいっしょくたになった、ザッパだけが到達した唯一無二の音楽だ。
さらにザッパのジャケの中でもおそらく最高の1枚であるここにうつっているのがキャプテン・ビーフハート。3曲にヴォーカルとして参加しているのだが、A面の冒頭変拍子のイントロに続いて、いきなりしぼりだされるだみ声はほとんど雑音のようである(ちなみに手元にある当時の日本盤につけられた対訳には「対訳不可能」とあり)。それにたたみかけるようにテリー・ボッジオのドラムを始めとしたやたら音数の多い演奏が入ってくる。
そのまんまのタイトルA面2曲目のCarolina Hard-Core Ecstasyでは、ザッパのハードなギタープレイが堪能できる。また5曲目の「200歳のウェイトレス」ではありえない詩の内容にあわせて、本格的なブルースロックギターが弾かれている。そしてアルバムタイトルはA面3曲目の歌詞から。しかしこの歌詞も対訳によれば「さしたる意味なし」とのことである。
このアルバムで何といってもすばらしいのがB面最後のMuffin Manである。このタイトルもほとんど意味がないのだが、そのナンセンスきわまりなく、猥雑ななかにありながら、演奏はどこまでもストイックである。メンバー紹介に続く、ザッパのギタープレイはまさに究極の「泣き」である。指さばきもすごいが、これだけのテンションの中で、冷静にメロディラインが保たれているところが、まさに「永遠に続く奇蹟」だ。