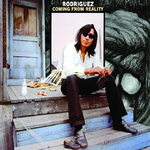宗教の話をフランス語でしていると、なかなか話がかみあわないことがある。それはreligionという単語の意味するところが日本語の宗教とはときどき異なるからだ。教義や宗派の話をするならば問題はないのだが、人の心の精神性について話すときはspiritualitéといったほうが齟齬が少ない。
宗教の話をフランス語でしていると、なかなか話がかみあわないことがある。それはreligionという単語の意味するところが日本語の宗教とはときどき異なるからだ。教義や宗派の話をするならば問題はないのだが、人の心の精神性について話すときはspiritualitéといったほうが齟齬が少ない。
ゴスペル音楽が、キリスト教のための、あるいはアフリカンアメリカンのためだけの音楽ではなく、信仰者でなくとも、その心に響いてくるのは、もっぱらその音楽が高いスピリチュアリティをたたえているからではないか。それはたとえ神を想像しなくとも、自分の存在を遥かに越える圧倒的な力に引き寄せられる感覚を私たちの中に生むからではないだろうか。
ゴスペル音楽をひとつの職能として、アーティストとして活動している人たちが多くいたわけだが、牧師自身も歌い手として、その声を教会に集う信者に聞かせていた。このアルバムのバレット牧師もそのひとりである。バレットはシカゴの教会で聖歌隊を結成し、若者たちを教会に足を運ばせるよう活動をした。それは単に信仰に誘うというだけではなく、60年代のアメリカにおいて、何とか真っ当に生きるための生活の場という意味があった。
教会で歌われた音楽はレコードに録音され、人々の生活に染み渡っていたのだが、そうした音楽は地域に密着しているがゆえに、より大きな反響を得ることは少なく、あくまでも対象は信仰者のためのものであった。
このバレットが録音したレコードも同様であるが、2009年、マニアックなソウル音源発掘レーベルとして知られるNumeroのコンピレーションアルバム「Good, God! Born Again Funk」に、そのうちの一曲が収められ、これが大きな話題となり、ついにこのアルバムが再発へと至った。
地域も時代も越えて、火がつくようにこのレコードが求められたのはは、当然ながらその音楽の質の高さによる。まずはバレット牧師の歌が本当にうまい。ファンキーでシャウトに力がある。メロウな歌い方もできる。また数曲で聞かれる女性ヴォーカルも彼に負けずファンキー。
だがこのアルバムが広いポピュラリティを獲得するのは、その音楽が極めて洗練されているからではないか。それはフィル・アップチャーチなどプロのミュージシャンが参加しているということもあろう。ただそれ以上に言えるのは、それぞれの曲がきちんとした構成をもって作られているため、完成された楽曲として聞けるということが大きい。
タイトル曲Like A Shipのベースラインのなめらかさ、鈴を鳴らしているかのようなリズムセクション、心地良いグルーヴ感に聖歌隊のコーラスが重ねられ、その上に、牧師のソウルフルな歌声が聞こえてくる。
あるいは2曲目Wondefulや5曲目Nobody Knows冒頭のダニー・ハサウェイを彷彿とさせる軽やかなピアノの旋律。特にWonderfulは歌い方もダニーを彷彿とさせる。70年初頭のまさにニューソウルに雰囲気をたたえ、コーラスや「ハレルヤ」の掛け声がなければ、ゴスペルだということを忘れてしまうようなスイートなソウルである。
かと思うと、1,2,1,2,3のかけ声で始まる4曲目のEver Sinceは、アグレッシブなゴスペルファンクで、コーラスもアップテンポ、バレット牧師もジェームス・ブラウンのようである(かけ声で発する単語は違うが...)。
こうした当時のソウル、ファンクの最新の形式がしっかりとそれぞれの曲に生かされている。それは当時の若者の心を捉えるという意味もあっただろう。だが何よりも、そのソウル、ファンクの音楽形式がきちんと曲にはめ込まれてなければ、これらの楽曲が普遍性をたたえることはなかっただろう。
単なる情熱や宗教心ではなく、あくまでも音楽として楽しめること、そのために楽曲自体がソウルやファンクの形式に沿っていること、それがあるからこそ、牧師のスピリチュアリティが、今、現在へと伝わってくるのだろう。音楽は楽しい、そんな単純な喜びを素直に感じられる名盤である。
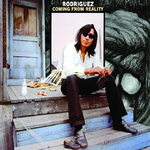 アメリカの音楽サイトWolfgang's VaultからのメールでRodriguezがアメリカで今も元気に歌っていることを知った。とはいえプロというわけではないらしい。それを知ったのは、実に驚きなのだが、Rodriguezを追ったドキュメンタリー映画がアメリカで公開され、彼のことがさまざまなホームページで語られていたからである。映画のタイトルはSearching For Sugar Man。Sugar Manは、1970年に発表されたファーストアルバムの1曲目。全く売れないまま、その後ほとんど消息不明になっていたRodriguezの40年も前のアルバムが、南アフリカでは、抵抗の象徴として大きな反響をよび、それを知った制作者が、アメリカでSugar ManことRodriguezを探すという映画らしい('Searching for Sugar Man' Spotlights the Musician Rodriguez - NYTimes.com)。
アメリカの音楽サイトWolfgang's VaultからのメールでRodriguezがアメリカで今も元気に歌っていることを知った。とはいえプロというわけではないらしい。それを知ったのは、実に驚きなのだが、Rodriguezを追ったドキュメンタリー映画がアメリカで公開され、彼のことがさまざまなホームページで語られていたからである。映画のタイトルはSearching For Sugar Man。Sugar Manは、1970年に発表されたファーストアルバムの1曲目。全く売れないまま、その後ほとんど消息不明になっていたRodriguezの40年も前のアルバムが、南アフリカでは、抵抗の象徴として大きな反響をよび、それを知った制作者が、アメリカでSugar ManことRodriguezを探すという映画らしい('Searching for Sugar Man' Spotlights the Musician Rodriguez - NYTimes.com)。
Rodriguezを初めて聴いたのは、2009年の仏Téléramaのpodcast音楽番組Hors pistesだった。発売当時も話題にならず消えてしまったミュージシャンの2枚のアルバムが、どういうわけかCDで再発になった。番組ではセカンド・アルバムからIt started Out So Niceという曲がかかっていた。かすかに枯れた声とアコースティックギターによる弾き語りの美しい曲。そして控えめにストリングスがアレンジされている。すぐにAmazon.frで2枚のアルバムを注文した。
ファーストのほうが若干サイケデリックっぽいだろうか。セカンドはぐっと質素で、飾り気のない優しい曲が多い。ポエトリー・リーディングのような曲もある。基本はアコースティックギターと控えめなストリングス。そして朴訥とした声。ジョン・ケールにも似たロマンティックな曲調だが、決して歌い込んだりはしない。あくまでも控えめに語るだけだ。Silver Wordsで歌われている「ああ、あなたに会って、ぼくがどんなに変わったか、わかってもらえたら」というひかえめな希望がこのアルバムを象徴しているように思う。決して声高ではない、ただいつかあなたに聴いてもらえたなら、そんな控えめな希望が、何十年たって、実際に本当になった。
とりわけ印象的なのはCauseという曲。いきなり「クリスマスの2週間前にオレは仕事を失った」と歌い出される。不運と自虐的ユーモアという意味では、こちらの曲のほうがSugar Manより、Rodriguezにふさわしいかもしれない。ヒットや反響という意味では、きわめて不遇のキャリアだったかもしれない。しかしWolfgang's Vaultのヴィデオで歌っているつい最近のRodriguezの姿は、本当に楽しそうなのだ。ギターを肩からかけ、かるく体をゆすりながら、歌う姿は本当に素敵だ。決してヒットはしないだろう。でも良い音楽は少しずつでもずっと聴き継がれてゆく。いつか彼の3枚目のアルバムを聴きたい。
 アル・クーパーは、ディランのアルバム録音に参加したり、バンド活動を繰り広げるなかで注目を集め、ソロ・アルバムも何枚も発表した。しかし根本的にはセッションバンドのキーボード奏者であると思う。よく言われることだが、彼のヴォーカルは、声量があるわけではないし、細やかなニュアンスに欠ける。
アル・クーパーは、ディランのアルバム録音に参加したり、バンド活動を繰り広げるなかで注目を集め、ソロ・アルバムも何枚も発表した。しかし根本的にはセッションバンドのキーボード奏者であると思う。よく言われることだが、彼のヴォーカルは、声量があるわけではないし、細やかなニュアンスに欠ける。
それでも彼のアルバムの魅力が衰えることがないのは、次々とあふれてくるアイデアを、アルバムであますことなく表現しえたからであろう。ハードロック調の曲もあれば、都会的なバラードもある。脈絡なぞあまり考えずに、頭の中に浮かんだものをとにかく音にしてみるという、考えてみれば贅沢な、しかしそれだけ高い制作意欲につらぬかれたアルバムである。
代表作として、そして日本で人気があったのは『赤心の歌』であり、自分も一番最初に購入したアルバムである。しかしNew York City (You're a woman)は、アル・クーパーの強い思い入れを感じる好盤である。プレイヤーとしての自信にあふれ、さらにプロデュース、アレンジも手がけ、一枚の作品へとアーティストの発想が結実している。
特に表題作の1曲目。ピアノと語りかけのヴォーカルから始まるイントロが素晴らしい。アル・クーパーのニューヨークによせる郷愁を歌ってはいるが、中盤からの力強さこそこの曲の魅力だ。この曲があるだけでこのアルバムは名盤と言える。そして切れ目なく2曲目へと。こうした着想や、ソウルロックのテイストがTodd Rundgrenを確かに思い起こさせる。
作曲能力の高さ、オリジナリティという意味ではインパクトに欠けるかもしれない。Elton Johnのカバーもあるが、これも楽曲がもともと良いから聞けるという点は否めない。それでも一人のミュージシャンが創意工夫をこらしてひとつの作品を創造できたということ、その音楽を創造する高い志に深い敬意を抱く。
 宗教の話をフランス語でしていると、なかなか話がかみあわないことがある。それはreligionという単語の意味するところが日本語の宗教とはときどき異なるからだ。教義や宗派の話をするならば問題はないのだが、人の心の精神性について話すときはspiritualitéといったほうが齟齬が少ない。
宗教の話をフランス語でしていると、なかなか話がかみあわないことがある。それはreligionという単語の意味するところが日本語の宗教とはときどき異なるからだ。教義や宗派の話をするならば問題はないのだが、人の心の精神性について話すときはspiritualitéといったほうが齟齬が少ない。