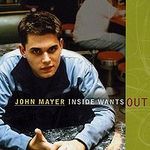Sonic YouthやDinosaur Jr.などの名前が浮かんでも、そうした音楽の影響関係を語ることはほとんど虚しい。Number Girlだけの固有の音楽は、その一瞬の凝縮度から生まれてくる。ライブにおいてこの一瞬だけの音、もう二度と出せないような音の塊が、彼らの音楽を唯一無二のものにする。
Sonic YouthやDinosaur Jr.などの名前が浮かんでも、そうした音楽の影響関係を語ることはほとんど虚しい。Number Girlだけの固有の音楽は、その一瞬の凝縮度から生まれてくる。ライブにおいてこの一瞬だけの音、もう二度と出せないような音の塊が、彼らの音楽を唯一無二のものにする。
それぞれのパートの音が激しくぶつかりあう。高度な演奏力に裏打ちされた緻密な計算と、金属音の凄まじい破壊の衝動が一曲の中で混じり合う。鍛えられたミュージシャンの破壊の衝動は、決して音楽そのものを破壊はしない。根底のところで曲として成立しているところが並じゃないのだ。
好きなところはいっぱいあって、突然ドラムとベースがやんで、ギターのリフがえんえんと続くところ、ドラムのロールがギターの爆音と重なりあうところなど。聞かせどころを心得ている。「我起立一個人」の歪みきったギターの音など、アンプに耳をくっつけたくなるほどよい音だ。そこから「Super Young」のロック定番のリフへと入っていくところなど、実にうまい。
ロックは、うまく歌わなくても曲として成立するジャンルだ。こんな叫び声で歌っても音楽として成立するところがロックだ。
何度も成立ということばを使ってしまうが、まさに音楽として成立するかしないかのぎりぎりのところで、曲として成り立たっているところが素晴らしい。あるいは「日常を生きる少女」なんて、けっこうスカスカなところがあるんだけど、それがサビにきて一気に空間が音で埋め尽くされるところなど、音楽に立ち会っている気にさせてくれる。
もちろん「透明少女」や「OMOIDE IN MY HEAD」のようななんだか青春ロックの定番のようなメロディラインの曲もある。でもまたこれがいい。まさに今を生きられないような前のめりの性急さが限りない魅力だ。「透明少女」のドラムのロールがいい。「OMOIDE IN MY HEAD」のドラムにギターがかさなって、一気に全員の音が轟音となって、さらにギターのリフが静寂に響いて、またふたたびバンドの音に戻ってくるのがいい。この演奏力、構成力、メロディのキャッチーさと、マイナーな感じのヴォーカル。どれをとってもこれほどまでに見事に破壊されているのに、緊密な構成をもっている曲が演奏できるバンドは本当に希有だ。虚空に響くギターのエレキ音をずっと聞いていたい。
ずっと前に解散していても、その会場に若い自分がいたと錯覚させてくれるライブアルバムだ。
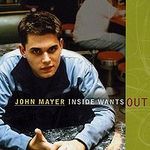 35分のEPということだが、最初の1曲を除けば、残りの8曲はすべてアコースティックであり、十分統一感がとれた1枚のアルバムだと言ってよいだろう(日本盤は1曲ボーナスつき)。
35分のEPということだが、最初の1曲を除けば、残りの8曲はすべてアコースティックであり、十分統一感がとれた1枚のアルバムだと言ってよいだろう(日本盤は1曲ボーナスつき)。
曲の最初の一小節を聞いただけで、まわりの風景が変わってしまう。ギター1本で、色彩豊かな世界が目の前に広がってゆく。No Such Thingは朝の起き抜けに聞きたい、さわやかで瑞々しい曲だ。つぎのMy stupid mouthは、少し落ち着いた、ギターのリフレインが心にじっくり刻まれる名曲。最初のわずか5秒のメロディだけれど、その刹那のメロディが、ずっと心に刻まれる。ふと気づくと自然に口ずさんでしまう、忘れられない曲だ。そしてサビのJohn Mayerの高音のヴォーカル・・・こういう曲を聴いてしまうと、なぜ自分がクラプトンに感動できないのか納得してしまう。John Mayerの曲の美しさは、こちらが立ち止まって、曲に向き合うことを余儀なくさせられる、そして、曲が終わっても、そのメロディがいつまでも響き続けている、強い「出会い」に満ちているのだ。ぼくにとってクラプトンの大方の曲はBGMでしかない。心地よくても、消費され、時間の流れにそのまま運びさられていってしまう音楽だ。
John Mayerの曲には、繊細さと強さが同居している。たとえば去年のライブアルバムでも1曲目にはいっていたNeonでのギターワークなど、繊細な弦からきわめて力強い音が流れ出してくる。もちろんcomfortableのような、ストリングスの入った泣きの曲もよいけれど。そして最後のQuietは三拍子の静謐な曲だ。リンゴ・スターのGood nightとあわせて聞きたい「おやすみソング」だ。
もし自分が17歳で、アメリカに暮らしている高校生で、ふとラジオから流れてくるJohn Mayerの曲を耳にしたら、おそらくはずっとJohn Mayerに寄り添って彼の音楽を聞き続けていくことになるだろう。30歳になっても40歳になっても彼の曲を聞いている間は17歳のままだろう。John Mayerもいくらキャリアを重ねても決して大御所にはならないだろう。プロでありながらも、デビュー当時の繊細さをずっと持ち続けてくれるだろう。
 ソウルというジャンルはいったいどうやって分類されるのだろうか?ひとくちにソウルといってもその幅はきわめてひろい。たとえばリズムの躍動はソウルの本質だろうか。それはジェームス・ブラウンのようなきわめて個性的なミュージシャンに負うところが大きいのかも知れない。ソウルのもつ高揚感、グル−ブ感ならば、まずはマーヴィン・ゲイを思い浮かべるだろう。そして黒人の魂の訴えならば、単なるメッセージソングに堕することはなく、しかし政治的なムーブメントとして大きな流れを作っていくほどの力をもったアルバムを生んだカーティス・メーフィールドだろうか。ここまで黒人の名前ばかりを挙げたが、ソウルは黒人の専有物ではない。60年のロック草創期からすでにスティーブ・ウィンウッドのようなきわめてブラックな、そして質の高いソウルフルなミュージシャンがいる。その歌唱の素晴らしさは、「ソウル=黒人文化」というきわめて安易な図式を払拭してくれる。
ソウルというジャンルはいったいどうやって分類されるのだろうか?ひとくちにソウルといってもその幅はきわめてひろい。たとえばリズムの躍動はソウルの本質だろうか。それはジェームス・ブラウンのようなきわめて個性的なミュージシャンに負うところが大きいのかも知れない。ソウルのもつ高揚感、グル−ブ感ならば、まずはマーヴィン・ゲイを思い浮かべるだろう。そして黒人の魂の訴えならば、単なるメッセージソングに堕することはなく、しかし政治的なムーブメントとして大きな流れを作っていくほどの力をもったアルバムを生んだカーティス・メーフィールドだろうか。ここまで黒人の名前ばかりを挙げたが、ソウルは黒人の専有物ではない。60年のロック草創期からすでにスティーブ・ウィンウッドのようなきわめてブラックな、そして質の高いソウルフルなミュージシャンがいる。その歌唱の素晴らしさは、「ソウル=黒人文化」というきわめて安易な図式を払拭してくれる。
少し振り返っただけでも、ソウルの歴史は、さまざまな豊かな財産を持っているわけだが、97年にファーストアルバムを出した、このRahsaan Pattersonの音楽が、ソウルと呼べるとしたら、それはどんな意味だろうか?
まずはっきりしているのは、90年代以降のソウルの流れは、かつての黒人という人種的枠組みにもとづく、プロテストとしてのソウルとは根底から異なっているということである。また汗の匂いといった肉体性も、パッションを歌い上げるような魂の叫びもない。しかしそれでもなぜ彼の音楽がソウルとしてここまで人の心をひきつけるのか?
Pattersonのソウルの魅力は、緻密に練り上げられた、楽器それぞれの粒だった音の構成にあるのではないだろうか?たとえばソウルを聞きながら「快適」と言えるのは、そのストリングスのアレンジのバランスの良さにあるように思う。それは、ソウルが本来持っていた、情念とも言えるスピリチュアルな部分を抜き取ってしまい、メロディの妙だけで聞かせるイージーリスニングにも似たお手軽なソウルになってしまったという危険も意味する。
しかしPattersonの音楽が、そうした批判に耐えうるとしたら、それはまさに計算されつくした、楽曲のよさによる。それぞれの音が個性を持ちながら、うまくアレンジされることで、曲としての一体感を醸し出していく。音と音の間の取り方が、いわゆるグルーブを生み出していく。そこがかろうじてソウルなのだと言えよう。つまり徹底的に知性的な音作りをしているのである。天性の才能や、人間の激しい生き様を聞くのではなく、最高のスタジオ環境で、過剰になる部分は極力抑えながら、音を重ね合わせていくその妙を堪能するのだ。そうした音作りは、彼の男性としては、ずいぶん細くて、高音にいけばいくほど、金属質になっていく声質にとてもあっている。この中性的な声は、音のアレンジの中でほとんど楽器の一部として溶け込んでしまっている。いってみれば人工的なソウル。しかし音楽の楽しさは、なにも生身の人間らしさだけにかかっているわけではない。スタジオワークによってここまで完璧な音作りをしてくれれば、それは、ひとつのエンターテイメントとして、聞くに堪えると言えよう。
なお、Rahsaan Pattersonはこれまで3枚のアルバムを出している。デビューはRahsaan Patterson、2ndはAfter Hours。どのアルバムも素晴らしいクオリティである。
 Sonic YouthやDinosaur Jr.などの名前が浮かんでも、そうした音楽の影響関係を語ることはほとんど虚しい。Number Girlだけの固有の音楽は、その一瞬の凝縮度から生まれてくる。ライブにおいてこの一瞬だけの音、もう二度と出せないような音の塊が、彼らの音楽を唯一無二のものにする。
Sonic YouthやDinosaur Jr.などの名前が浮かんでも、そうした音楽の影響関係を語ることはほとんど虚しい。Number Girlだけの固有の音楽は、その一瞬の凝縮度から生まれてくる。ライブにおいてこの一瞬だけの音、もう二度と出せないような音の塊が、彼らの音楽を唯一無二のものにする。