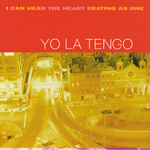 Yo La Tengoのアルバムを買ったのは確か80年代後半で、DB'sなどのアメリカインディーズを聞いていたときに、DB'sのピーター・ホルサップルやクリス・ステイミーの同志のアルバムとして買ったように思う。しかしそのアルバムの内容はむしろ、Peru Ubuなどのアングラ・ロックに等しく、聞くのに「忍耐」が必要だった。
Yo La Tengoのアルバムを買ったのは確か80年代後半で、DB'sなどのアメリカインディーズを聞いていたときに、DB'sのピーター・ホルサップルやクリス・ステイミーの同志のアルバムとして買ったように思う。しかしそのアルバムの内容はむしろ、Peru Ubuなどのアングラ・ロックに等しく、聞くのに「忍耐」が必要だった。
ところがこのバンド、粘り強く存在していたようで、今も活躍しているとのこと。入学以来500枚以上CDを買っている愛すべきO君から最近の愛聴盤と紹介され、聞かせてもらったところ、なるほど彼のいうようにソニック・ユース+ダイナソーな音作りで、さっそくCDを購入した。
ただこうして聞いてみるとむしろこのアルバムは4ADっぽい、マイ・ブラッディ・バレンタインのような音像処理のほうが耳に入ってくる。たとえば5曲目などはJoy Divisionにあるギターのエコーを最大限に聞かせて、それにヴォーカルを埋没させるような音作りである。そして途中からはFeeliesのようなアメリカのガレージバンドぽいギターを聞かせてくれる。でも面白いのはこのギターの音、結局はイーノの実験音楽的ロックと同じ音色なのだ。まさにこの雑食性こそ、このバンドの魅力なのだろう。
実際にはどうかわからないが、スタジオの録音代がまったくかかっていないようなチープな音、脱力したヴォーカルが全体の雰囲気を作っている。この金のかかっていない貧乏くさい音が、このバンドにシンパシーを感じてしまう理由である。もちろん本人たちはスタジオにこもっていろいろ機材をいじくっては楽しんでいるのだろうが...
 Ryan Adamsの在籍したWhiskey Townのセカンドアルバムがデラックスエディッションで再発になった。オルタナ・カントリーと言われる彼らの音楽だが、聞いていて感じるのは若さゆえの、破裂感を持ったと言おうか、結構パンキッシュな曲が多いのに驚く。この青々しさを聞いていると、Byrds〜Gram Personsというより、ニュー・ウェーブの動きを作り上げていった、あるいは、その中から生まれてきた、Big Star, dB's、Feeliesなどの、熱さの中にもどこか醒めてしまったバンドの音がむしろ浮かんでくる。だからBarn's On Fire sessionsのプロデューサーに、元dB'sのChris Stamyの名前があることにとても納得がいく。
Ryan Adamsの在籍したWhiskey Townのセカンドアルバムがデラックスエディッションで再発になった。オルタナ・カントリーと言われる彼らの音楽だが、聞いていて感じるのは若さゆえの、破裂感を持ったと言おうか、結構パンキッシュな曲が多いのに驚く。この青々しさを聞いていると、Byrds〜Gram Personsというより、ニュー・ウェーブの動きを作り上げていった、あるいは、その中から生まれてきた、Big Star, dB's、Feeliesなどの、熱さの中にもどこか醒めてしまったバンドの音がむしろ浮かんでくる。だからBarn's On Fire sessionsのプロデューサーに、元dB'sのChris Stamyの名前があることにとても納得がいく。
屈折したというほどニヒルではなく、情熱を向けるほどの希望への確信もない。そんな中途半端なやるせなさが、いろんな曲調で表現されたのが本作ではないだろうか。喜びや怒りといった単純な感情に流されることもできなくなってしまったアメリカの若者の心理を知るためには、もっとアメリカの時代思潮を考えた上で捉え返してみる必要があるのだろう。そうすればREMなどとつながる線もみえてくるかもしれない。
Ryanのアルバムを聞いていてうれしいのは、突然、今まで聞いたこともない美しい曲に出会えることだ。もう何十年も音楽を聞き続けているはずなのに、Ryanの曲にはいつも新鮮な発見がある。様々なバックボーンを感じさせながらも、新しく瑞々しい体験をさせてくれる、これこそRyan Adamsが天才的とよべる証拠ではないだろうか・・・
 エリオット・スミスの曲がとても生々しく聞こえるのは、それは「音楽が生まれる瞬間」に立ち会っている印象をとても強く受けるからではないだろうか?最小限の楽器。あらかじめ決まめられたリズムや、コード進行もないかのように、最小限のささやきと、ギターを刻む音で、音楽が始まる。エリオット・スミスが最初に浮かべたメロディそのまま、音はおさめられ、聞く者にとどけられる。だからエリオット・スミスの音楽を聞くと、本人の存在をとても身近に感じられる。エリオット・スミスの曲は、加工という作業からもっとも遠い。だから皮膚がすり切れるような痛々しいつぶやきまで僕たちは感じてしまう。
エリオット・スミスの曲がとても生々しく聞こえるのは、それは「音楽が生まれる瞬間」に立ち会っている印象をとても強く受けるからではないだろうか?最小限の楽器。あらかじめ決まめられたリズムや、コード進行もないかのように、最小限のささやきと、ギターを刻む音で、音楽が始まる。エリオット・スミスが最初に浮かべたメロディそのまま、音はおさめられ、聞く者にとどけられる。だからエリオット・スミスの音楽を聞くと、本人の存在をとても身近に感じられる。エリオット・スミスの曲は、加工という作業からもっとも遠い。だから皮膚がすり切れるような痛々しいつぶやきまで僕たちは感じてしまう。
およそ他人に聞かせることなど念頭になかったのだろう。おそらくはBasement Tapesにおさめられたまま、誰にも聞かれずに忘れ去られていくはずだったろう。しかし本人の意図とは別に、「グッド・ウィル・ハンティング」のサントラ曲として、突然、広く知られることになった。その時の違和感は確かに、彼の素直な反応だったのではないだろうか。自分の独り言にも似たメロディが、人にも聞かれてしまい、気に入られてしまうという戸惑い。そんな戸惑いによってその後の生き方そのものを縛られてしまうミュージシャンは多い。ピンクフロイドのシド・バレットはロック(産業)の歴史の中で、その最初のミュージシャンだろう。そして同時代のカート・コバーンを思わずにはいられない。ただしエリオット・スミスとカート・コバーンはとても対照的なミュージシャンでもある。あくまでも内に沈潜していくエリオットに対して、カートはやはり攻撃的だ。たとえその攻撃が結局は自分に向かってしまうとしても。
タイトルもない、断片だけの曲。エリオット・スミスにとってはそれだけで十分だったに違いない。しかしエリオット・スミスは、自閉的な、自己満足の音楽ではない。彼の歌の中には、時に他人との深い関わりを感じさせる歌がある。そのときの彼のメロディは本当に優しい。
I'm in love with the world through the eyes of a girl who's still around the morning after. (Say Yes)
恋する彼女の目を通して、世界を見る。そんな風に他人と重なるような一瞬がある。たとえ淡く崩れてしまう一瞬でも、それを静止画のように切り取ることのできるエリオット・スミスは素晴らしい詩人だ。こうしたまなざしをもったエリオット・スミスは、これからもロックを聞く者たちに一番に愛され続けていくだろう。ロックの優しさをここまで純粋に感じされてくれるミュージシャンは希有なのだから。
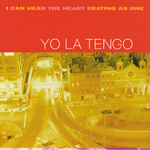 Yo La Tengoのアルバムを買ったのは確か80年代後半で、DB'sなどのアメリカインディーズを聞いていたときに、DB'sのピーター・ホルサップルやクリス・ステイミーの同志のアルバムとして買ったように思う。しかしそのアルバムの内容はむしろ、Peru Ubuなどのアングラ・ロックに等しく、聞くのに「忍耐」が必要だった。
Yo La Tengoのアルバムを買ったのは確か80年代後半で、DB'sなどのアメリカインディーズを聞いていたときに、DB'sのピーター・ホルサップルやクリス・ステイミーの同志のアルバムとして買ったように思う。しかしそのアルバムの内容はむしろ、Peru Ubuなどのアングラ・ロックに等しく、聞くのに「忍耐」が必要だった。

