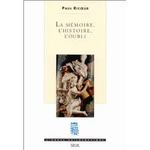リクールの思想はきわめて広大で、その分野は多岐に及び、一見すると全体像が掴みにくいかもしれない。しかし50年近くにも及ぶその活動を、ひとつの問題意識が貫いている。それはいささかもぶれることなく、リクールの思想の根幹をなしている。それは変容ということばに集約される生の躍動である。
ただ変容といっても、まるきり別のものに変わってしまうということではない。リクールの思想は、「あれかこれか」ではなく、ある一つの要素を含みつつも、別の要素も統合していく、ひとつのコスモスのような世界観を提示する。
人間の歴史的時間意識において、現在は過去も未来も含み込む。テキストは著者の思想を完全に消し去ることなく、読み手の新たな解釈を帯び、文化的、社会的制約を越えていく。言葉の意味が多義的であるのは、ある意味を捨て去って新しい意味を帯びるのではなく、一つの語に意味が堆積していくからだ。芸術の世界は、現実世界から離れた仮構世界を構築するとはいえ、その世界は、やがて私たちの現実世界を見る認識を変容させる。
こうした世界の多層性こそが、リクール哲学の特質であり、この多層性を含み込みながら、変化していく存在の実相こそ、人間の生の証である。その意味でリクールの解釈学はすぐれて人間学的である。
本論文でリクールが考察するのはテキストである。リクールはガダマーの「隔たりと帰属」という考え方の「隔たり」に着目し、テキストという問題設定によって、「隔たり」概念が生産的な機能として働くことを指摘する。久米博は『テクスト世界の解釈学』において、この意味でのテキストを次のように性格づける。
「主体と対象との間に介在するいろいろな距離(distance)は、対象を把握するのに障碍となるが、その障碍こそ解釈のための積極的な条件となる。文字言語によって固定されたテクストは典型的な疎隔の状態にある。」(p.95.)
距離とは交流の条件であり、交流は双方向の働きかけによって意味を産出していく。通常、話す行為(ディスクール)であれば、<今・ここ>に状況が設定され、話者同士の働きかけがなされ、意味の疎通があることは理解しやすい。しかしリクールの主眼はこのディスクールの性質を、書かれたものの中にも見いだしていくことにある。すなわち、テキストとは書かれたものと同一ではなく、書かれたもののなかにパロールの特質であるディスクール性を認めたものがテキストである。
I. ディスクールとしての言語の実現化
テキストのディスクール性を考えるため、リクールはまず言語をディスクールとして規定しなおす。ラングとしての言語学からディスクールとしての言語学へ、語としての言語学から文としての言語学への転換である。そしてディスクールの特質は「出来事」と「意味」である。それをリクールは「あらゆるディスクールは出来事として実現され、あらゆるディスクールは意味として理解される」と表現する。
まずディスクールは次の4つの意味で出来事とみなされる。
1) ディスクールは現在時において実現される=ディスクールの現前性、
2) ディスクールとともに主体も現前する。
3) 指示する世界がある。ディスクールによって世界が言語への到来する(ラングとしての言語がその体系を内部だけで閉じているのに対して)
4)ディスクールにおいてメッセージの交換がなされる(対話者をもつ)
次は意味の規定である。出来事が一回性の去りゆくものであるのに対して、意味は留まる性質をもつ。ではこの意味の静止は、ラングの言語学へ戻ることになるだろうか?むしろリクールはここに言語のもつ飛躍的な運動を認める。
「De même que la langue, en s'actualisant dans le discours, se dépasse comme système et se réalise comme événement, de même, en entrant dans le procès de la compréhension, le discours se dépasse, en tant qu'événement, dans la signification. Ce dépassement de l'événement dans la signification est caractéristique du discours comme tel. (p.105.)
ラングがディスクールにおいて現在へと姿を現し、それによって体系としての自己のあり方を越え、出来事として実現されるのと同様に、理解の過程に入ることによって、ディスクールは出来事としての自己のあり方を越え、意味の中に入ってゆく。この出来事が自らを越え出て、意味の中に入っていくことが、ディスクールそのものの特徴である。
ディスクールとラングは対立する二項ではない。その乗り入れは動的なものであり、私たちの発話は、ラングの体系によって支えられ、またラングの体系は、発話によって柔軟にその姿を変えてゆく。理解の過程は、決してどこかに行き着き、完結するものではないことを意味している。理解とは絶えざる更新である。
では「出来事が自らを越えて、意味の中に入っていくことが」書かれたものにおいてもどれほど可能だろうか。これについてリクールはオースティン、サールの言語行為論を援用し、行為がもつ意味が、書かれたものからも読みとれることを強調する。例えば「ドアを締めてください」というとき、発話者は次の3つの行為をしているが、それぞれの行為における意味は、程度の差はあるが、書かれたものの中にも認めることができる。
1)発語的、命題的行為:発話行為であるが、これは行為と行為者、被行為者に関係づけているわけだが、これはまさしく文として同定ができる(書いても同じ)。
2) 発語内的行為:言いながらしている行為。ここでは発話と同時に命令という行為をしている。この行為の意味も法(le mode)という形式上に認めることができる。もちろん抑揚やジェスチャーなど言語外的行為に負うことが多いとはいえ、やはり書くものの中にも反映可能であす。
3)発話媒介的行為:言うこと事実がもたらすもの。たとえば、命令行為による恐怖といったもの。これは実際にはディスクールから最も遠い。すなわち、話し手の意図ではなく、聞き手の心理に属する言語外的行為なのである。
これらの程度の差はあったとしても、意味とは文に内包されるだけではなく、発語内的行為や発語媒介的行為からもたらされるものも意味として認めることができる。この広い意味をリクールはsignification「意味作用」と呼ぶ。
II. 作品としてのディスクール
次にリクールは作品という書かれたものの中におけるディスクール的性質を主張するために、作品概念の3つの特徴を挙げる。
1)作品は文より長い連続体である。すなわち作品は文による構成である。
2)作品は、ジャンルを構成するコードによって成り立っている。すなわち作品はジャンルに属する。
3)作品はそれ固有の布置(configuration)をもっており、それは個人的文体と呼びうる。
この中でディスクール的特徴と言えるのは布置と個人的文体であろう。察するに、作品が文の連続体であるとしても、文の総和は作品の意味と重ならない。ジャンルを構成するコードも、作品をカテゴリー分類するだけである。
だが、作品にはそれ固有のconfigurationがあり、それが作品の個性を決定している。このconfigurationはstylisation「文体化」とも呼べる。文体とは比喩といった個別の一表現という意味ではない。そうではなく作品全体を個性化する、作品全体をつらぬく様式のことであろう。作品の個性を決めるもの、それは作品が唯一である限りにおいて、ひとつ出来事である。だが、それが作品と呼びうるならば、ひとつの構成を備えて、目の前に現れてくる。この生成と組織化が作品の条件なのではないか。
文体化が個性化を伴う以上、その個性をもつ作者をも指し示すようになる。したがってテキストにおいては、常に「誰かが何かについて誰かに何かを言う」という根本的特徴は失われていないのである。
III. パロールとエクリチュールの関係
ディスクールが話されたものから書かれたものへと映るとき、何が起きるのか?パロールと異なり、書かれたものは作者から「隔たって」生成されることがその特質である以上、テキストの意味と、作者が意味したかったことにはずれが生まれる。作者の意図を越えて、テキストが自律性を獲得することで、テキスト世界が作者の世界を壊してしまうこともありうるのである。
だがそれはテキストを解放することでもある。テキストはそのテキストが生まれた時代の社会や文化を越えていくことができる。読むという行為によって、テキストは、当初の文脈から引き離され、異なる状況の中に組み込まれることが可能となるのだ。
したがって書かれたものとしてのテキストは、これらの隔たりが、その構成の条件となっているのだ。そして同時にこの特質が解釈の条件となる。隔たりの存在が解釈を可能とする。
IV. テキスト世界
次にリクールが検討するのが、指示の問題である。パロールからエクリチュールへの以降は、指示対象を変質させることになる。すなわちパロールにおいて指示対象はその状況の枠組みの中で、共通の現実世界の中で、明示される。
それに対して書かれた作品では、書いた人間と読む人間の間に状況の同一性を確保することはできない。それが「文学」の条件ですらある。リクールは、「大部分の文学の役割は、世界を破壊することである」とさえ言う(C'est le rôle de la plus grande partie de notre littérature de détruire le monde)。
この文学世界においては現実への指示は廃棄される。ただリクールはここで「日常のディスクールの指示参照機能」が廃棄されると、「日常」という形容詞を足している。なぜならば、リクールはこの日常的なディスクールは第1番目の指示であり、その現実参照が廃棄されたところに、第2番目の指示参照の可能性が広がってくる。その参照は「テキスト世界」を志向する(その世界はフッサールの生活世界、ハイデガーの世界内存在と等しいとされる)。
「テキスト世界」で参照されるのは、テキストの「背後」(derrière)にある意図ではない。なぜならば、それは私たちが求めようとする=参照しようとする世界に、隠されてはいても、すでに前もって完結した=固定化された存在を認めてしまうからだ。
テキスト世界において、私たちが追い求める行為とは、謎解きではなく、状況に根ざした可能性を世界に投映してゆく行為なのだ。つまりテキスト世界とは、私が可能性を投映することで、提起される世界のことである。
テキストの世界とは「日常」の言語の状況性が示す世界ではない。その意味で、テキストの世界と現実とは「隔たり」がある。だがそれが現実を再創造する契機となるのだ。
Nous l'avons dit, un récit, un conte, un poème ne sont pas sans référent. Mais ce référent est en rupture avec celui du langage quotidien ; par la fiction, par la poésie, de nouvelles possibilités d'être-au-monde sont ouvertes dans la réalité quotidienne.
すでに述べたように、物語、説話、詩は指示対象がないわけではない。ただ、この指示対象は日常の言語が指し示す対象とは隔絶している。フィクション、詩によって、新たな世界内存在の可能性が日常の中に開かれているのである。
私たちはこの可能性を創造することによって、この日常の現実さえも変容することができる。可能性という想像領域、そしてその想像の力とは、現実をひとつのヴァリエーションとし、それ以外のヴァリエーションを私に提示してくれるだけではなく、この現実自体を作り替えるような、バシュラールのことばで言えば「想像力の歪形能力」と言うことができるだろう。
V. 作品を前にして自己を理解する
そして世界の再創造は、テキストを読む私自身の再創造にもつらなる。テキストを通して、私たちは自分自身を理解することになる。これはテキストのappropriation「同化」=テキストを自分自身の中に含み込むこと、あるいはapplication du texte à la situation présente au lecteur「テキストの読者の現在状況への当てはめ」と言われる。
ただし同化とは、作者の意図への同化ではない。書かれたものが「隔たり」である以上、同化とは、距離のあるものへの理解と考えなくてはならない。
次にここでいう自己の理解とは、考える私という主体の発見ではない。むしろテキスト世界を経由することによって、人間性の印しに触れ、それによって自我(ego)ではなく自己(soi)としての自分を知るのである。そもそもそのような人間性に触れえないでは、人間は自分の主観の世界に留まったままである。だが私たちの存在は世界との関係、他者との関係、相互交流を含み込んで成立するものではないだろうか。それを示してくれるテキスト世界に自らが入ることによって、作品の前に立つことによって、初めて自己理解に達するのである。
自己とはすでに完結して存在し、それがただ明かされるのを待っているようなものではない。自己とは変容し、層を幾重にも形成し、絶え間なく動いていく存在なのだ。リクールはテキストの前で自己はより広大になると言っている(soi plus vaste)。自己はこうしてテキストによって作られていくのであり、ここにテキストに身を浸す喜びがあるのではないだろうか。
自己とはテキスト世界と同じく、可能性を含みこみ、今だ実現されず、変容する運動こそが実体である。世界の変容とは、実は自己の遊びとしての変容なのだ(La métamorphose du monde, selon le jeu, est aussi la métamorphose ludique de l'égo)。
自己とは単体ではない。この可能性や変容と通して、自分のなかで自己と自己が、隔たるがゆえに、対話をし、自己を放棄すると同時に、新たな自己を獲得してゆく。
このように考えれば、リクールの言語学理論は、すぐれて人間学であり、そこに変化と運動という命のあり方を認める上で、きわめて希望に満ちた人間学なのだ。