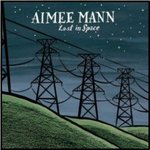最近はiTunesに登録されているインターネットラジオで、Radioio acousticという番組を聞くことが多く、ここで気に入ったミュージシャンのCDをAmazonで購入というパターンが続いている。とにかく日本では知られていない、でも質の高いミュージシャンがアメリカには多いのだと当たり前のことに気づかされる。Aimee Mannは、もちろん日本でも知られているし、日本盤も出ている。それでもソングライティングの高さから考えるに、もっともっと話題になってもよいはずだ。
最近はiTunesに登録されているインターネットラジオで、Radioio acousticという番組を聞くことが多く、ここで気に入ったミュージシャンのCDをAmazonで購入というパターンが続いている。とにかく日本では知られていない、でも質の高いミュージシャンがアメリカには多いのだと当たり前のことに気づかされる。Aimee Mannは、もちろん日本でも知られているし、日本盤も出ている。それでもソングライティングの高さから考えるに、もっともっと話題になってもよいはずだ。
95年に出された本アルバムは何と言っても10曲目のThat's Just What Yous areだろう。スクイーズのメンバーが参加しているこのアルバムであるが、この曲のサビのバックコーラスは、まさにスクイーズというか、なかでもChris Diffordのクセのある声に引き込まれる(去年出た、スクイーズの曲をアクースティックに演奏しなおしたSouth East Side Storyは名盤です。ときに過剰な味付けもあったスクイーズの曲が、本当にすばらしくよみがえっています)。この曲をはじめとしてAimee Mannのソングライティングとスクイーズのポップな世界はこれ以上ないというほど、素敵な取り合わせだ。
そして職人が作るポップロックの風味は、このアルバムでも何も変わりはしない。70年代後期、イーノ、ケール、ラングレンといった70年代初頭のポップマニアアーティストがえさをついばむようにして、ニューウェーブバンドのプロデュースをしたが、このアルバムにはところどころ、そんな70年代の雰囲気がただよっている。それはスクイーズとの相性のよさでもうなづけるが、たとえば、5曲目Superballの楽器の音色や、曲の途中のギターのフレーズとそれに重なるハンドクラッピングはイーノのTaking Tiger Mountainを彷彿とさせる。
アルバム最後の曲、It's not Safeの一気に盛り上がる始まり方は、これはまさにマイケル・ペン。途中のギターソロ、これもちろんマイケル・ペンが弾いているのでは? とにかく最初から最後までドラマチックで、でも控えめで、最後を飾るにふさわしい一曲だ。
80年代のうすっぺらい打ち込みの音の時代を経て、90年代楽器の音自体にこだわるアルバムが復活してくる。その音の作り込みがもっとも丁寧になされているアルバムとして、もっと評価されてもよいだろう。
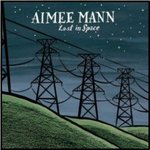 往々にしてロックは、「瞬間」に生まれることがある。一夜にして録音を終えてしまったとか、1テイク録りでアルバムを作ってしまったとか、その時のエネルギーを一気に凝縮して、緊張感をそのまま閉じ込めたアルバムは、それだけで伝説として語り継がれたりもする。
往々にしてロックは、「瞬間」に生まれることがある。一夜にして録音を終えてしまったとか、1テイク録りでアルバムを作ってしまったとか、その時のエネルギーを一気に凝縮して、緊張感をそのまま閉じ込めたアルバムは、それだけで伝説として語り継がれたりもする。
そうした最高度のテンションで、バンドの音を作り上げるようなロックがあるとするならば、Aimee Mannのこのアルバムはおよそそうした創作の仕方とは対極にあるものだろう。このアルバムは決して「偶然の産物」ではない。丁寧に織り上げられたハンド・メイドの肌触りがあるアルバムだ。これだけポップな曲作りをしていながらも、安易な既製品の音はまったく聴かれない。こうした仕事にはいったいどのくらい時間がかかるのかわからないが、音楽にまっすぐに対峙して、丹誠をこめて作られた曲が並んでいる。
これだけポピュラーな音作りをしていながら、なぜ平板な音にならないのだろうか?たとえばReal Bad Newsのアレンジは、夫Michael Penのアルバムにも似てとても深みがあるエコーの音で、けっこう不思議な音色だ。Pavlov's Bellのギターソロは、これだけ聞くと、曲の憂うつな感じとはそぐわない結構派手な音なのに、曲の中では違和感がない。そしてInvisible Inkの慎ましやかなヴォーカルに重ねられる控えめなストリングス・・・どの曲も実によく練り上げられたプロの音だ。Aimee Mannのヴォーカルを一切邪魔することなく、いやそれどころか単に美声で歌われるだけのなじみやすいメロディでは終わらない、聞き込めば聞き込むほど、全体のカラーが浮かんでくるコンセプトのしっかりしたアルバムに仕上がっていることがわかる。もちろんAimeeのヴォーカルの表現力もすばらしい。 This is How It goesのようなヴォーカルが全面に出ている曲での、彼女の抑揚の効いた歌い方は、とても地味なのだが、聞き終わった瞬間から、心の中で彼女の声が再生し始めるような印象深い歌い方だ。Pavlov's〜のOh Mario, という歌いだしなど、ほんとうにぞくぞくする。
なぜこんな音作りができるのだろう。それはやはりこのアルバムがソロ・アルバムではなく、バックミュージションとの共同作業によって作られたことが大きいのだろう。しかしそれが仲間内の楽しみに終わらないところが、Aimee Mannというミュージシャンの職人芸のなせるわざなのだろう。どこにもあるようでいて、実はどこでも得られないような、コマーシャルに十分なれるのに、安易な使い回しの手法は一切ないというストイックさに貫かれているアルバムだ。この作品は上質なポップアルバムとして、年を経ても聞き継がれていくであろう名盤である。
 最近はiTunesに登録されているインターネットラジオで、Radioio acousticという番組を聞くことが多く、ここで気に入ったミュージシャンのCDをAmazonで購入というパターンが続いている。とにかく日本では知られていない、でも質の高いミュージシャンがアメリカには多いのだと当たり前のことに気づかされる。Aimee Mannは、もちろん日本でも知られているし、日本盤も出ている。それでもソングライティングの高さから考えるに、もっともっと話題になってもよいはずだ。
最近はiTunesに登録されているインターネットラジオで、Radioio acousticという番組を聞くことが多く、ここで気に入ったミュージシャンのCDをAmazonで購入というパターンが続いている。とにかく日本では知られていない、でも質の高いミュージシャンがアメリカには多いのだと当たり前のことに気づかされる。Aimee Mannは、もちろん日本でも知られているし、日本盤も出ている。それでもソングライティングの高さから考えるに、もっともっと話題になってもよいはずだ。