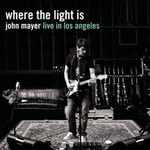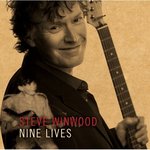60年代東海岸でソウル音楽のプロデューサー、作曲家として活躍したジェリー・ラゴヴォイの作品集である。タイトルに1953ー2003とあるように、その仕事は60年代だけではなく、20世紀後半の実に50年にわたっている。
60年代東海岸でソウル音楽のプロデューサー、作曲家として活躍したジェリー・ラゴヴォイの作品集である。タイトルに1953ー2003とあるように、その仕事は60年代だけではなく、20世紀後半の実に50年にわたっている。
有名な曲としてはローリング・ストーンズ、アーマ・トーマスがカバーしたTime is on my side。このアルバムにはオリジナルの、トロンボーン奏者Kai Windingによる演奏が収められている。トロンボーンがそこはかとない哀愁を漂わせるが、ヴォーカルの入ったヴァージョンの方がソウル音楽の黒さを感じさせる。
ジャニス・ジョプリンがカバーしたCry baby。オリジナルはGarnet Mimms & The Enchantersで、63年に発表されビルボードチャート4位、R&Bチャートでは1位とヒットしている。ラゴヴォイはバート・バーンズと多くの仕事をしているが、これが最初期のもの。
そして、誰でもが一度は耳にしたことがあるであろう。Pata Pata。この曲は、歌い手であるMiriam Makebaのアフリカン・フォークに、ラゴヴォイがアメリカン・バラードの雰囲気を脚色したダンスナンバー。
他にもGood Lovin'など、多くのカバー曲をもつラゴヴォイの仕事は、ソウルやブルーズそしてアカペラなどの黒人文化の音楽を、決して黒人だけのものではなく、その音楽自体のもつ魅力に親しみやすさを与えて、商業ベースにのせたことにあるだろう。
特に彼が得意にしたのは、ミディアム・テンポで少し哀愁を漂わせながらも、さびで一気に歌い上げる作風ではないだろうか。ジャニス・ジョプリンの歌い方もまさにそんな感じだが、Carl Hallという女性ソウル歌手も、多少ハスキーな声をもつが、泥臭くはない。スローなところの情感とさびでのシャウトの対照が実に見事で、魅力的な歌手だ。彼女の歌うYou don't Know Nothing About Loveは、この作品集の中でももっとも聞かせる一曲である。ちなみにここには収められていないが、この曲は、ラゴヴォイがプロデュースしたHoward Tateの同名アルバムにも収められてる。
Howard Tateとラゴヴォイの付き合いは長く、この作品集にも3曲と一番多く収められている。64年のYou're Looking Good、72年のアルバム制作後の74年のシングルAin't Got Nobody To GIve It To、そして、歌手をやめ、不遇な環境に身を落とし、辛酸をなめるような生活をずっとしていたTateに、ラゴヴォイがプロデューサーとして手を差し伸べたかのような2003年の復帰アルバムから、60年代の曲の再録Get it while you can。この曲が作品集の最後に収められている。若い頃の力強い歌い方ではなく、むしろ淡々を歌われるだけに、二人の歩んできた人生の道のりを感じさせ、胸をうつ好演である。
 歌はどのように生まれるのか。ことばはまず声であり、声は何よりもひとつの音である。だから単にハミングしたり、あるいは叫んだりしても、それは当然音楽とみなされる。ときには声そのものが楽器のように聞こえてくることもあるだろう。
歌はどのように生まれるのか。ことばはまず声であり、声は何よりもひとつの音である。だから単にハミングしたり、あるいは叫んだりしても、それは当然音楽とみなされる。ときには声そのものが楽器のように聞こえてくることもあるだろう。
しかし歌には多く歌詞がある。声は音でありながらも、それはことばとして同時に意味を伝える。朗読と歌は違うと直感的にわかるように、歌にはそれを歌だと私たちに思わさせる規則が、言い換えれば制限がある。それが抑揚やリズムだ。したがって、そのような歌に課せられる制約が、同じことばであっても、歌詞に独自の特徴を与える。フランスのミュージシャンの場合、この歌詞のオリジナリティによって評価されることが多い。それは定型詩にも見られる韻や、言い回しに乗せたことば遊びの妙でもある。
そしてまた歌は、ロマン主義の時代に言われた民族の覚醒という概念から見れば、古来からの魂の継続性の表象とみなされる。たとえばブルターニュにおいてケルト文化の復興および伝承に携わる人々にとって、民族楽器を用いて、ブルトン(ブレーズ)語で歌を歌うことは、彼らの精神的支柱となる活動であると言っても差し支えないのではないか。
だが文化は決して単層ではありえない。文化はたえず浸食しあい、多層的な表象を作り上げる。かつてアラビア詩を触媒としてトゥルバドゥールが生まれたように、現在でもフランスでは、とくにラップやエレクトロなどの音楽が、国籍を無化する形で生まれ続けている。
Maggaというミュージシャンについて調べてみてもほとんど詳しいことはわからない。10年ほどグループで活動した後、ソロに転向したらしい。その顔立ちから北アフリカ系のフランス人であろう。以前FNACでファーストを試聴して購入。その音楽は英米ロックの影響を受けたアコースティックフォークで、その外見が伺わせる民族的な背景はほとんど皆無だった。
しかし今回やはりFNACで見つけたセカンド(だと思う)には、イスラム的な意匠がかなり色濃く施されている。ジャケットしかり。タイトル曲Caravane du désertではサハラ砂漠の遊牧民トゥアレグ族が使うとされる楽器を奏でる女性が歌われる。また1曲目、2曲目はアラビア音楽の旋律がそのまま使われている。そして歌詞の主人公の男は「王妃たちの心を盗む男」として描かれる。
なぜここまで彼の作る音楽に民族性が反映しているのかはわからない。ファーストと同じアコースティックギターを基調としながらも、歌詞はずっと寓話性が高く、その哀愁はアラビア音楽に似た哀愁だ。エキゾティックな情景、女を前にして、夢幻の世界に浸る男、野生の熱、動物の息。音楽も歌詞も素直なまでに、アラビア音楽の表象をそのままなぞるようなアルバムになっている。
ようやく見つけたビデオの本人は、背が高く、細長い顔立ちで、アルバムの印象よりずっと内省的な青年であった。これほどまでに民族性を意図づけながらも、実は彼のピッキングによるギターの音はBen Wattを思いださせる。特にラストの、少しエコーがかかったギターの音色、憂いのあるヴォーカルは、Ben Wattの『ノース・マリン・ドライブ』だ。海辺の波にも似て、ギターの音色がせつなく近づいては、遠ざかってゆく。
音楽には定型がつきまとう。それらの定型の混ぜ合わせの妙がひとつのオリジナリティとなる。しかしこのアルバムではまださまざまな要素が分離している印象を受ける。それでもやはりBen Wattに似て、彼の声、ギターにはきわめてまれな透明感をたたえている。繊細で素直なこの音世界こそ、彼のオリジナリティなのだろう。
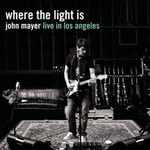 John Mayerは自分が最も聞きそうにないミュージシャンである。なにしろ顔よし、声よし、ギターよし。自分が惹かれる顔は、たとえば上前歯の2本の間にすきまがあるような顔。声は高音で裏返ってしまうようなへろへろ声。ギターは、弦が弛んでるのではと思うような、しまりのない音。その理想はKinksのLolaのB面一曲目All this tomorrowだ。イントロのギターのなさけなさ、ぐ〜っともりあがっていくところのRayの鼻づまり声。そしてあのニヒルな顔。すべてが好きだ。
John Mayerは自分が最も聞きそうにないミュージシャンである。なにしろ顔よし、声よし、ギターよし。自分が惹かれる顔は、たとえば上前歯の2本の間にすきまがあるような顔。声は高音で裏返ってしまうようなへろへろ声。ギターは、弦が弛んでるのではと思うような、しまりのない音。その理想はKinksのLolaのB面一曲目All this tomorrowだ。イントロのギターのなさけなさ、ぐ〜っともりあがっていくところのRayの鼻づまり声。そしてあのニヒルな顔。すべてが好きだ。
それに比べるとJohn Mayerはギターの弦は張り詰めている。声に一点の曇りもない。そしてあのルックス(アメリカ的美男子!)。どこを聞けばと思ったのだが、やはりアメリカン・ロックに対する憧憬の深さと、真のオリジナリティにまで達する技量の深さだろうか。ジェフ・ベックやクラプトンにはどうしても感動できないのに、彼のギターの音色にはほんとうに翻弄される。そしてヴォーカルはギターと同じく変幻自在。歌いながら、ギターをこれほどまでに弾くのだからまたすごい!
それから彼の魅力のひとつは、最近のスマートなブルースの影に多少隠れているが、90年代以降のミュージシャンぽい叙情性だ。この内省的ともおもえるメロディの美しさが、彼の音楽を手に届く等身大のものにしてくれる。とはいえおそらくヒットしたはずのWaiting on the world to changeは、一聴して親しみやすい、なつかしさを感じさせるメロディラインだが、Paul Youngほどではなく、どちらかといえば凡庸で叙情性とはほど遠い。それよりもアコースティックということもあるのだろう、Stop this trainや、名曲Daughtersは、確かなギターワークに裏打ちされた叙情性がうまく表現されている。特にDaughtersの最後、彼の声が高くなっていくところは、このアルバムの最高の瞬間だ。このアコースティックセットはこのライブアルバムの聞きどころだろう。
とはいえ実際は6曲だけ。なんだかここのパートは余技にすぎないと言っているかのようである。
 大学の学食で、大学院生のmrt君と昼飯を食べながら、日本の音楽の話になった。年齢のわりには古いものをよく知っている彼と、年齢の割には新しいものをかろうじて知っている僕の間には、非常に親密な「わかる」感覚がある。この日も「エグザイルにはメンバーが何人いるかわからないし、アンジェラ・アキはこちらが気恥ずかしくなってしまう。でサザンにたいしてはまったく無関心でしかいられない、好き嫌いの次元以前に、視野に入りようがない」ということで、大いに盛り上がってしまった。平成生まれがまわりにちらほらいるなかで、ぼくらの話はほとんど意味不明だろう。
大学の学食で、大学院生のmrt君と昼飯を食べながら、日本の音楽の話になった。年齢のわりには古いものをよく知っている彼と、年齢の割には新しいものをかろうじて知っている僕の間には、非常に親密な「わかる」感覚がある。この日も「エグザイルにはメンバーが何人いるかわからないし、アンジェラ・アキはこちらが気恥ずかしくなってしまう。でサザンにたいしてはまったく無関心でしかいられない、好き嫌いの次元以前に、視野に入りようがない」ということで、大いに盛り上がってしまった。平成生まれがまわりにちらほらいるなかで、ぼくらの話はほとんど意味不明だろう。
では日本のロックにだれがいるだろうか。ここで名前がのぼるのが若い割にはロックの歴史をしっかり咀嚼している「くるり」。というわけで、その夜家に帰って「ワルツを踊れ」を聞いてみた。I-tunesをみたら、なんと最後に再生したのは去年の12月・・・結局そう、最近のくるりは少し聞くに耐えないところがあるのだ・・・たくたくのライブはとてもよかったが。
では何が一番再生されているか。それがこのThe Guitar plus meという日本的な文脈からかなり遠いところにいるミュージシャンである。今回の新譜も今までとまったく変わらない。歌詞はすべて英語で、対訳つき。この新譜は大手コロンビアからの発売だが、音数は今まで通り、きわめて質素である。1曲目のhighway througt desertから、まったく今までの音作り同様のやさしいアコースティックギターが流れてくる。音を重ねながらもこのすきすき感があるところがなんともいえない魅力だ。
また3曲目school bus bluesのようなコード進行、ヴォーカルも音の階梯を降りてゆくような、せつなさ、それがI can't see your smileという歌詞と重なる。
次のBlue printもほぼギターの弾き語りで、そこに多重ヴォーカルが重なる。
YouTubeでみたthe guitar〜は超絶ギター少年だったが、アルバムではそこまでテクニックに走ることはない。fortune-tellerには途中でギターソロが挿まれるが、それもテクニックを聴かせるものではなく、あくまで曲の流れの一場面だ。それよりも一本一本の弦の音色がここまで違うのかと教えてくれる、丁寧な演奏である。winter afternoonは、リフが幾度ともなくくりかえされ、そこにハミングのようなヴォーカルが重なってくる。その溶け合いかたが、とてもやさしい。
1stアルバムから基本的には何の変化もない。アルバムジャケットも音の構成も。ギターの肌触りと、人工音の類い稀なフュージョンといえばよいだろうか。最後の曲horizonはそうした人工音の中に、アコースティックギターが流れてくる魅惑的な構成だ。イントロを3秒聴けば、すぐに彼の音楽だとわかる。
そして詩的喚起力の強さーそれが、作品に淡い物語性を生んでいる。それもこのミュージシャンの魅力であり、アルバムを通して聴きたくなる強い磁力のもとであるのだろう。
 James Taylorの最近のライブを聞くと、若い頃と比べても遜色なく、かえって今のほうがずっと輝きのある声になっていることに驚く。衰えるどころか、今が一番脂の乗り切った充実期であることを感じる。Jackson Browneも、2枚のアコースティックシリーズでの弾き語りを聞くと、依然声質が衰えていないことがわかる。そしてアルバムテイクよりも、実はこちらのアコースティックのほうが曲の良さが断然生かされている。
James Taylorの最近のライブを聞くと、若い頃と比べても遜色なく、かえって今のほうがずっと輝きのある声になっていることに驚く。衰えるどころか、今が一番脂の乗り切った充実期であることを感じる。Jackson Browneも、2枚のアコースティックシリーズでの弾き語りを聞くと、依然声質が衰えていないことがわかる。そしてアルバムテイクよりも、実はこちらのアコースティックのほうが曲の良さが断然生かされている。
そのアコースティックシリーズを経て、今回出されたニューアルバムはバンドでの録音である。Jackson Browneの曲でひっかかるのは、明確なメッセージがあることはわかるが、それを「音楽」という媒体を使って表現する必然性が果たしてあるのだろうかという点である。愚直といえばそれまでで、もちろん愚直であることの潔さを曲から受け取ることはできるのだが、それはたとえばニュース番組と同じで、メッセージが情報として伝達されれば、「再放送」されないように、一回聞けば終わってしまう危うさがある。そうした一回性で終わらないがために音楽が選ばれるのだと思うが、はたしてJackson Browneの曲は、その一回性で終わらないほどのクオリティが保たれているだろうか。
アコースティックシリーズをつい何回も聞いてしまうのは、やはり曲自体をクオリティの高さが一番純粋に出ているからであり、だから繰り返しに耐えられるのだ。
こうした実直なミュージシャンがはまり込む陥穽は、純粋な表現として音楽を作ることができず、自分が置かれている今の状態や、社会情勢にどうしても真摯に立ち向かわざるをえないという不器用さにあると思うのだが、ではこの60歳のミュージシャンが出したこのニューアルバムはどうなのだろうか。なんだか歯切れの悪い言い方になってしまうが、「歌うべきことをもっている限りは、曲は生まれてくる」という点で、命のこもった曲が並んでいるとは言える。しかしそれが初期のアルバムにおさめられたような、永遠性をもちうるかといえば、それはなかなか難しいのかも知れない。アレンジは、大人といえば大人なのだが、あまり切実さが感じられず、バンドといってもお互いに切り結ぶものはなく、雰囲気にながされてしまっている。
だがそれでも歌い続けるということ、その生きる姿をけれん味なくみせてくれるということ、その態度自体がロックなのだろう。誠実に音楽を作り続けるということ、しかも何十年にもわたって。過去ではなく、今を共有できることの喜びはなにものにも代え難い。どんなに歳月を経ても、友人から便りがとどけば、うれしいように、今後も僕は新譜を買い続けるだろう。
 今年のRyan Adamsの新譜が出た。Easy Tigerと同じゆとりのある雰囲気を漂わせながら、正統的なアメリカン・ロックを堪能させてくれる曲が並ぶ。
今年のRyan Adamsの新譜が出た。Easy Tigerと同じゆとりのある雰囲気を漂わせながら、正統的なアメリカン・ロックを堪能させてくれる曲が並ぶ。
青春の最高傑作Heart Breakerのようなナイーブなところは影を潜め、Rock'in Rollのようなニュー・ウェーブのひ弱さのようなものもすっかり払拭されている。
もちろん憂いに満ちた曲もある。しかしAdamsのヴォーカルは酔いどれのつぶやきではなく、あくまでも骨太で、シャウト寸前の歌いっぷりだ。曲の沈んでゆく感覚と歌の激しさのアンバランスが素晴らしい。
Easy Tigerよりもとにかく曲がヴァラエティに富んでいる。Magickのようなバンドの緊迫感を感じさせる曲は、前回のEasy Tigerとは違うところだ。いたって短い曲だが、密度は濃い。次のCobwebはU2っぽいニュー・ウェーブの残り物のような曲で、途中のギターのリフがダサイ。ヴォーカルのエコーもダサイ。でもキャッチーで、深みもあってと、なんだか中途半端な曲だけど引き込まれる。かと思えばEvergreenのような可憐な小曲もあり、Like YesterdayのようなCold Rosesを思い起こさせる泣きのギターに心を揺さぶられる曲もあり、これでノック・アウトだ。最後はピアノの弾き語りでRyanの優しい声でしめくくられる。
アルバムのトータル感はEasy Tigerのほうがあり、今回は多少散漫なところもなきにしもあらずだ。朝聞いたほうがよいのか(Goldの前半のように)、深夜に聞いたほうがよいのか(Goldの後半のように)・・・しかしどんな曲も聞いた瞬間にRyan Adamsでしかありえない。駄作、傑作という評価の定規にひっかからないところがこのミュージシャンの偉大なところなのだろう。
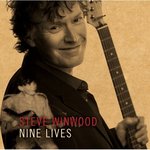 自分がロックを愛している理由を考えてみると、結局はロックというジャンルは、はっきりしていないことにつきるように感じる。ロックとは関係ない映画をみてて、「これってロックだよね」などとつい言ってしまうが、そのロックの意味の根拠など実はきわめてあいまいなのだ。だがそれがロックの強みなのだ。
自分がロックを愛している理由を考えてみると、結局はロックというジャンルは、はっきりしていないことにつきるように感じる。ロックとは関係ない映画をみてて、「これってロックだよね」などとつい言ってしまうが、そのロックの意味の根拠など実はきわめてあいまいなのだ。だがそれがロックの強みなのだ。
かつてトルコ人の友人に、「日本人はとても優秀な民族であり、自分は尊敬している。だが、西洋の文化に汚染されてしまっているのが残念だ。日本には素晴らしい伝統ミュージックがあるのに、なぜおまえはビートルズやローリング・ストーンズなど聞いているのだ(注:ぼくはあまりストーンズは聞かないけど)」と言われたことがあるが、まさにそこにロックの秘密がある。ロックは、イギリス、アメリカで生まれたかもしれないが、その源流にはブルース、ジャズ、あるいはフォークなどの影響があるわけで、「源流」は結局「源流」にはなりえない。だがその雑食性にロックの楽しみがあるのだ。ぼくは、いまだに「本物」のブルースやソウルは聞けない。日本の伝統音楽も同じ理由で。
そう考えると、このSteve Winwoodのアルバムはまさにロックアルバムである。アフリカンなパーカッションに、ブルースぽいギターライン、それに白人Winwoodのソウルフルなヴォーカルがからむ。この雑食性に富んだアルバムに、Winwoodの音楽観の豊穣さが十分に凝縮されている。60歳のミュージシャンが作るアルバムは、これまでの音楽を咀嚼しつくした上で、それらを奥深くまで含みこんだロックである。
どの曲もリズムの進行が素晴らしい。パーカッションとギターのリフのからみや、ハモンドオルガンがフューチャーされる瞬間、個々の楽器がこれほど完璧にセッションしているアルバムが他にあるだろうか。
そしてSpencer Davis Groupの頃から変わらない、これこそホワイト・ソウルというヴォーカル。
とくに心を奪われるのはたとえば、ソプラノサックスが美しい、大地の広がり、飛翔の高みを感じさせる二曲目。On a brave new morning, smiling at the skyという歌詞のすがすがしさから始まり、どこまでも深みを感じさせるアレンジが展開され、やがてOh what you're healingと、歌い上げられる。このヴォーカルも素晴らしい。だが一番素晴らしいのは、この曲がアフリカにもイギリスにも、どこにも根をはっていない、真にロックとしかいいようのない曲のエッセンスだ。
もちろん繰り返されるギターリフが印象的な一曲目から、ロックのかっこよさに引き込まれる。三曲目の変則拍子の展開も緊迫感があり、そこにはりのあるヴォーカルが重なるところが、聞き所だ。そしてブルージーなギターがはじけ飛ぶ、クラプトン参加の四曲目。黒っぽいロックが聞きごたえたっぷりである。他にも八曲目の最初のハモンドオルガンが入ってくるところなどは、何度聞いても鳥肌がたってしまう。パーカッションの効いた部分と、盛り上がるところでのハモンドオルガンとヴォーカルの絡みの対比に本当にどきどきする。最後の十曲目はまずもって泣けてくる名曲。
40年以上のキャリアをもつ人間が、今だにクリエイティブなアルバムをだし、人々を感動させ続けている。ロックの存在価値は、Winwoodのような最高の仕事人によって保たれているのだと実感できる2008年最高のロックアルバム。
 タワーレコードで初めてレコードを買ったのは、受験のために東京に上京したときだった。試験が終わった翌日、念願の渋谷のタワーレコードに行った。買ったレコードは2枚、The Smithsの新譜、The meat is murderと、友人から借りて録音したカセットしか持っていなかった、Elvis CostelloのArmed Forcesだった。友人のレコードはカッティングが悪く、A面の最初に針を落とすとすでに曲が始まっているような代物だった。自分でLPを買って、はじめてコンプリートなイントロを聴き、強い感動にうたれたのを今でも覚えている。
タワーレコードで初めてレコードを買ったのは、受験のために東京に上京したときだった。試験が終わった翌日、念願の渋谷のタワーレコードに行った。買ったレコードは2枚、The Smithsの新譜、The meat is murderと、友人から借りて録音したカセットしか持っていなかった、Elvis CostelloのArmed Forcesだった。友人のレコードはカッティングが悪く、A面の最初に針を落とすとすでに曲が始まっているような代物だった。自分でLPを買って、はじめてコンプリートなイントロを聴き、強い感動にうたれたのを今でも覚えている。
東横線が事故で止まったため、久しぶりにタワーレコードに行き、いろいろ試聴した。金曜日の夜、ゆっくりアルバムを見ている人は、実はそんなにいない。試聴の順番をおとなしくうろうろしながらまっているのは、おっさんばかり。店内には「大人買い」や、「おやじのための紙ジャケ、ボックスコーナー」という文句がならぶ。
今日はまだ買わなかったAimee Mannの新譜、She & himという男女デュオのデビューアルバム、Steve Winwoodの新譜などを存分に聞きまくった。その中でタワーレコードがプッシュしていたのが、このEric Hutchinsonである。タワーの説明によると、メジャー契約を結んでいない中で、ヒットしているミュージシャンらしい。これがファーストであることに確かに驚く。タワーの推薦ということで購入した。
かなり老成したミュージシャンである。まずソウルフルでありながら、どこかフォークっぽい情けなさのただよう、ヴォーカルが印象的だ。そのわりにはバックのアレンジはかなり人工的でしゃれている。曲の雰囲気からは様々なミュージシャンが浮かぶ。フリージャズ的な即興性が潜まり、曲としてのまとまりを強く感じるようになったInto the musicの頃のVan Morrison。6曲目Oh!のサビは、Todd RundgrenのSomething, anythingのピアノワークを感じさせる。控えめなグルーブ感はThe fifth avenue bandなんかも浮かんでくる。そしてもちろん、Stevie Wonder。8曲目のパテティックなちょっとださい感じもする音はElton Johnあたりだろうか。
ただ、そのようなミュージシャンの名前を連ねると、この新人は、その模倣なのかということになるが、全くそんなことはない。とにかく凝ったアレンジには新鮮なオリジナリティを感じる。曲によって目玉がストリートミュージシャンぽい弾き語りの音だったり、ピアノだったり、ブラスバンドだったりと様々で飽きさせない。声もまた実に奇妙なのである。ただ最大な魅力は、「明るい遊び心」だろうか。アルバムトータル37分の一気にきいてしまえる軽快な、遊び心がこのアルバムにはつまっている。
もっぱらインターネットで情報を仕入れることが圧倒的に多くなってしまった今だが、タワーレコードのバイヤーたちのセンス、ポスターなどで宣伝して、プロモで1500円で売ってくれるところなど、タワレコ文化、まだまだ健在です!
 60年代東海岸でソウル音楽のプロデューサー、作曲家として活躍したジェリー・ラゴヴォイの作品集である。タイトルに1953ー2003とあるように、その仕事は60年代だけではなく、20世紀後半の実に50年にわたっている。
60年代東海岸でソウル音楽のプロデューサー、作曲家として活躍したジェリー・ラゴヴォイの作品集である。タイトルに1953ー2003とあるように、その仕事は60年代だけではなく、20世紀後半の実に50年にわたっている。