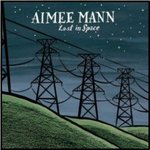John Mayerを聞いていたら、フランス人の友人から「これが好きなら絶対気に入るよ」と紹介されたのがGérald De Palmasである。確かにJohn Mayerぽい。とはいえ、このアルバムがライブであることもあり、むしろブルース・スプリングスティーン兄か。最初の« On y va ! »「イクぜ!」や曲の間の« Est-ce que vous êtes avec nous ? » 「お前らオレたちと一緒かい?」と煽るところなど、熱いです。
John Mayerを聞いていたら、フランス人の友人から「これが好きなら絶対気に入るよ」と紹介されたのがGérald De Palmasである。確かにJohn Mayerぽい。とはいえ、このアルバムがライブであることもあり、むしろブルース・スプリングスティーン兄か。最初の« On y va ! »「イクぜ!」や曲の間の« Est-ce que vous êtes avec nous ? » 「お前らオレたちと一緒かい?」と煽るところなど、熱いです。
曲はきわめてシンプル。ギターが印象的なリフを繰り返し、サビでもTu vas manquer「寂しくなるぜ」やRegarde-moi en face「オレを真っ正面からみてくれ」など、「ああやっぱりフランスって」という赤面するような歌詞が歌われる。でもそれは結局ロックというパフォーマンスが持っている共通の部分だろう。それを越えると、たとえばディランのような詩人の聖域に入って行くのだ。
そうフランスにも卓越したテクニックをもったミュージシャンは数多くいる。このDe Palmasのライブでも、まったくぶれのない、端正ともいえる演奏が楽しめる。
フランスのロックがほとんど聞くにたえないのは、甘ったるい叙情性、耽溺したナルシシズムのようなヴォーカルが多いためだが、De Palmasは珍しく硬派だ。ロックのリズムにうまくフランス語が乗っている。少しハスキーな声も魅力的だ。John Mayerほど弾きまくるわけではないし、むしろ控えめなのだが、ギターもいい音色を出している。とっても誠実なミュージシャンなのだ。
でもやっぱり曲が終わって言われるMerci Beaucoup !はちょっと谷村新司かも...
 「オブラートにつつんだ」声と言おうか。ハナレグミの魅力はその少しだけハスキーで、少しだけ鼻にぬけるような、ノスタルジックな気分にさせる声だ。肩肘をはらず、ジャケットのようなギターの弾き語りを中心につくったアルバムは、とてもパーソナルで、大上段にかまえたところがない。ロックがもっていた批判精神のようなものはすっかり抜け落ちている。その代わりここで描かれるのは、日常へのオマージュだ。CMにも使われた「家族の風景」は、まさにそうしたパーソナルで、普段の生活の風景を描いている。ハイライトとウイスキー。
「オブラートにつつんだ」声と言おうか。ハナレグミの魅力はその少しだけハスキーで、少しだけ鼻にぬけるような、ノスタルジックな気分にさせる声だ。肩肘をはらず、ジャケットのようなギターの弾き語りを中心につくったアルバムは、とてもパーソナルで、大上段にかまえたところがない。ロックがもっていた批判精神のようなものはすっかり抜け落ちている。その代わりここで描かれるのは、日常へのオマージュだ。CMにも使われた「家族の風景」は、まさにそうしたパーソナルで、普段の生活の風景を描いている。ハイライトとウイスキー。
アレンジもきわめてひかえめで、楽器の木のぬくもりがするような音作りだ。レゲエやスカのリズムはあまりにもあっけらかんとしすぎであるが、それは愛嬌ということで受け流しておこう。そうしたちょっとはずかしいアプローチは3枚目の『帰ってから歌いたくなってもいいようにと思ったのだ』ではすっかり消えてしまい、アルバムの完成度としてはこちらのほうが高いだろう。ハナレグミ節が十分満喫できて、ゆとりさえ感じられるし、「催促嬢」のようなふざけた曲も十分楽しめる。それに比べれば『音タイム』はあまりにも素直すぎる曲が多い。でもそれでも歌いたいことがいっぱいあったのだろう。そんな音楽への愛着と衝動が感じられる若いアルバムだ。
そしてなによりもこのアルバムには前述の「家族の風景」が収められている。この一曲がはいっているだけで「買い」だ。(ただ、やはり聞き比べると『帰ってから〜』はやっぱり充実している。くるりの「男の子と女の子」、ラブソング「僕は君じゃないから」、単純な弾き語りだけどメロディが印象に残る「かえる」、「おまえはポールか」とちゃちゃを入れたくなる「ハナレイ ハマベイ」など。う〜ん、やっぱり3枚目を推します)。
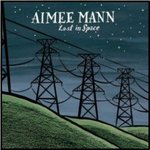 往々にしてロックは、「瞬間」に生まれることがある。一夜にして録音を終えてしまったとか、1テイク録りでアルバムを作ってしまったとか、その時のエネルギーを一気に凝縮して、緊張感をそのまま閉じ込めたアルバムは、それだけで伝説として語り継がれたりもする。
往々にしてロックは、「瞬間」に生まれることがある。一夜にして録音を終えてしまったとか、1テイク録りでアルバムを作ってしまったとか、その時のエネルギーを一気に凝縮して、緊張感をそのまま閉じ込めたアルバムは、それだけで伝説として語り継がれたりもする。
そうした最高度のテンションで、バンドの音を作り上げるようなロックがあるとするならば、Aimee Mannのこのアルバムはおよそそうした創作の仕方とは対極にあるものだろう。このアルバムは決して「偶然の産物」ではない。丁寧に織り上げられたハンド・メイドの肌触りがあるアルバムだ。これだけポップな曲作りをしていながらも、安易な既製品の音はまったく聴かれない。こうした仕事にはいったいどのくらい時間がかかるのかわからないが、音楽にまっすぐに対峙して、丹誠をこめて作られた曲が並んでいる。
これだけポピュラーな音作りをしていながら、なぜ平板な音にならないのだろうか?たとえばReal Bad Newsのアレンジは、夫Michael Penのアルバムにも似てとても深みがあるエコーの音で、けっこう不思議な音色だ。Pavlov's Bellのギターソロは、これだけ聞くと、曲の憂うつな感じとはそぐわない結構派手な音なのに、曲の中では違和感がない。そしてInvisible Inkの慎ましやかなヴォーカルに重ねられる控えめなストリングス・・・どの曲も実によく練り上げられたプロの音だ。Aimee Mannのヴォーカルを一切邪魔することなく、いやそれどころか単に美声で歌われるだけのなじみやすいメロディでは終わらない、聞き込めば聞き込むほど、全体のカラーが浮かんでくるコンセプトのしっかりしたアルバムに仕上がっていることがわかる。もちろんAimeeのヴォーカルの表現力もすばらしい。 This is How It goesのようなヴォーカルが全面に出ている曲での、彼女の抑揚の効いた歌い方は、とても地味なのだが、聞き終わった瞬間から、心の中で彼女の声が再生し始めるような印象深い歌い方だ。Pavlov's〜のOh Mario, という歌いだしなど、ほんとうにぞくぞくする。
なぜこんな音作りができるのだろう。それはやはりこのアルバムがソロ・アルバムではなく、バックミュージションとの共同作業によって作られたことが大きいのだろう。しかしそれが仲間内の楽しみに終わらないところが、Aimee Mannというミュージシャンの職人芸のなせるわざなのだろう。どこにもあるようでいて、実はどこでも得られないような、コマーシャルに十分なれるのに、安易な使い回しの手法は一切ないというストイックさに貫かれているアルバムだ。この作品は上質なポップアルバムとして、年を経ても聞き継がれていくであろう名盤である。
 ノイズに満ちた音で癒される。このアルバムで構築される音の渦は、ノイズと呼んでいいだろう。そのノイズの渦に身を浸しながら、癒されていく体験がこのアルバムにはある。それはどんな感覚だろうか。2曲目は「静かの海」。深海で砂が何らかの拍子にふと舞い上がるときのかすかな音は、きっとこのアルバムで聞かれるような音に違いない。それは音楽とはいえない、たんなる音のかたまり。しかしその音こそが癒しをもたらしてくれる。そんな雑音がちりばめられたこの「THE WORLD iS MiNE」は、くるりの最高傑作である。ここまで音響、音の破片でしかないものが、ひとつの音楽に結晶するなど、いったいどんな力量があればできることなのだろう。
ノイズに満ちた音で癒される。このアルバムで構築される音の渦は、ノイズと呼んでいいだろう。そのノイズの渦に身を浸しながら、癒されていく体験がこのアルバムにはある。それはどんな感覚だろうか。2曲目は「静かの海」。深海で砂が何らかの拍子にふと舞い上がるときのかすかな音は、きっとこのアルバムで聞かれるような音に違いない。それは音楽とはいえない、たんなる音のかたまり。しかしその音こそが癒しをもたらしてくれる。そんな雑音がちりばめられたこの「THE WORLD iS MiNE」は、くるりの最高傑作である。ここまで音響、音の破片でしかないものが、ひとつの音楽に結晶するなど、いったいどんな力量があればできることなのだろう。
しかしこのアルバムが恐ろしいのは、極端に音数が少なくなる瞬間があることだ。「アマデウス」は、たとえいくつもの音が聞こえるとしても、印象に残るのは単調なピアノの音色とヴォーカルだけだ。そしてもう一つの特徴は、メロディとリズムの反復だ。「Buttersand/Pianorgan」や「Army」は、うねるノイズだけで構成されている楽曲だといえよう。
しかしそんなアルバムの印象も「水中モーター」あたりから、ロック色が強まっていく。「水中モーター」のヴォーカルはスチャダラパー的なアプローチといってもよいが、そうした雑食性もまたくるりの楽しさである。「男の子と女の子」は、ハナレグミもカバーしているが、あきれるほどめめしい曲だ。そんなロックのストレートさは、「Thank You My Girl」で最高潮になる。そして再びアルバムは、「砂の星」、「Pearl River」を辿って、深海へ戻っていく。たゆたう水のうねりがゆったりとはてしなく円を描く。
このアルバムが最高傑作と言えるのは、どう頭をひねってもシングルカットできない曲ばかりならんでいるからだ。どの曲もこの音の流れから引きはがすことができない。それほどの緊張感をもって作り上げられたアルバムである。
 John Mayerを聞いていたら、フランス人の友人から「これが好きなら絶対気に入るよ」と紹介されたのがGérald De Palmasである。確かにJohn Mayerぽい。とはいえ、このアルバムがライブであることもあり、むしろブルース・スプリングスティーン兄か。最初の« On y va ! »「イクぜ!」や曲の間の« Est-ce que vous êtes avec nous ? » 「お前らオレたちと一緒かい?」と煽るところなど、熱いです。
John Mayerを聞いていたら、フランス人の友人から「これが好きなら絶対気に入るよ」と紹介されたのがGérald De Palmasである。確かにJohn Mayerぽい。とはいえ、このアルバムがライブであることもあり、むしろブルース・スプリングスティーン兄か。最初の« On y va ! »「イクぜ!」や曲の間の« Est-ce que vous êtes avec nous ? » 「お前らオレたちと一緒かい?」と煽るところなど、熱いです。