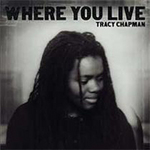80年代に結成されたバンドはどんな音楽を志向しようと活動を始めたのか。パンクやニューウェーブといったアメリカ、イギリスのロックは、様式美から隔たった地点で、そして社会を変革することができるという意気込みからは遠ざかった地点で、自分の日常を見つめ直し、その日常自体も、そして生活の中での鬱屈とした不機嫌さえ表現の原点となると認識した時点で始まったのではないか。
80年代に結成されたバンドはどんな音楽を志向しようと活動を始めたのか。パンクやニューウェーブといったアメリカ、イギリスのロックは、様式美から隔たった地点で、そして社会を変革することができるという意気込みからは遠ざかった地点で、自分の日常を見つめ直し、その日常自体も、そして生活の中での鬱屈とした不機嫌さえ表現の原点となると認識した時点で始まったのではないか。
パンクというムーブメントは、たとえばジミ・ヘンドリクスやジョン・レノンなど大御所の名前を挙げれば歴然とするように、音楽による社会変革とは言い難く、自分を中心に置いたとはしても、それを表現へと高めるにはあまりにもつたなく、かつ幼いわがままでさえあった。しかし死んでしまうパンクと生き残るパンクがある。ファッションとして消費されていくパンクと、日常を不器用に問い直し続けるパンクがある。
パンクとは日常へのささいな違和感を真正面から抱き続ける人生の態度ではないだろうか。パンクとは衝動ではなく緊張を保った持続であり、慣性に流されることなく意味を問い続ける行為ではないだろうか。
だからこそパンクとは単純な曲調で衝動的に叫べば出来上がるものではなく、目に見えない屈折やためらいを曲の上に反映させてゆく繊細な精神が必要になるのだ。
ブッチャーズを聴くとヴォーカルの直情的な歌い方がまずは耳に入ってくる。その歌い方は一本調子で、不器用だ。しかしそうした欠点を補ってあまりある切実感と緊張感がこのヴォーカルにはあるのだ。ぶっきらぼうなのにこよなく繊細なヴォーカルだ。
ブッチャーズの曲は、パンクでありながら、展開に味がある。パンクだから、イントロの入り方がいかにかっこいいかがもちろん大事。Yamaha-1のギターのカッティングからドラムがはいってくるところ、爽快とまでいえるほどかっこいい。Maruzen Houseもパンクの定番。ギターのカッティングからタテノリリズムがはいってくる構成はパンクの書式にしっかりとのっかっている。だがブッチャーズが素晴らしいのはそのことよりもバンドという複数のいるメンバーでそれぞれがどう曲に関わりながら、ひとつのまとまりを作り出してくかということにきわめて意識的であるところだ。
卓越した技術を持っていることは言うまでもない。しかしその上で、せめぎあいながらも、それぞれが個性を殺さず、緊張感を携えながら、それぞれが切り結びながら、やがては1つの曲への結実していくところがブッチャーズの真骨頂なのだ。
 このアルバムを渋谷のHMVで試聴したとき、ジュディ・シルのことはまったく知らなかったが、1曲目を聞いた瞬間に、他のどんなミュージシャンにも求めることのできない世界に触れた気がした。試聴機の前で文字通り立ちつくしてしまった。
このアルバムを渋谷のHMVで試聴したとき、ジュディ・シルのことはまったく知らなかったが、1曲目を聞いた瞬間に、他のどんなミュージシャンにも求めることのできない世界に触れた気がした。試聴機の前で文字通り立ちつくしてしまった。
宗教的ではないのに、きわめて宗教性を感じさせる音楽と言おうか。もちろん1曲目のタイトルがThat's the spiritとつけられているように、歌詞の内容には神を感じさせるものが多い。しかしその詩の内容よりも、音楽そのものもつ高揚感がそう感じさせる。彼女の声の高音へと上りつめるときの、抑揚のきわめて細やかな変化が、聞いている側を崇高な気持ちにさせる。
メロディ自体は飾り気のないシンプルなものばかり。ホンキー・トンク調の曲や、フォーク、ポップス、カントリー、そしてクラシックさえもが自由にまざりあっている。だが、1枚目や2枚目の簡素さに比べると、この3枚目には、それまでに見られなかった華やかさがある。それまでの内省的な雰囲気から、希望へと移るような音楽に対する信頼感が感じられる。ソフトな歌声なのに、その歌には彼女の強い確信があるのだ。歌うこと以外の生き方はありえないような心の底からの確信だ。
このアルバムはデモテープのまま残され、本人の生前には発表されることはなかった。オーバードーズで35歳で亡くなってから、26年の時を経てようやく発売へと至った。ローラ・ニーロの初期のアルバムにも鎮魂歌のようなものを感じるが、どちらかというと厳粛な気持ちを起こさせる雰囲気があって、明るさが指してくるのは、活動休止後に出したSmileぐらいになってからだろう。それに対してジュディ・シルは同じ鎮魂歌であっても、彼女の生き様とは正反対に本質的におだやかなのだ。魂の救いや、希望というものをこれほどまでに素直に表現したミュージシャンは希有なのではないだろうか。
そして再発にあたったジム・オルークを始めとするスタッフの愛情がそのまま伝わってくる丁寧な作業ぶりが目をひく。その後ライノからデモテイクがたっぷりとはいった1枚目、2枚目の再発、そしてロンドンでのライブの発掘音源と、ジュディ・シルの仕事をしっかりと歴史化するアルバムが出されることになった。
 たった一言のことばでも心がふるえることがあるように、簡素なギターの音色とつぶやくような歌だけでも、心がかきむしられることがある。『No direction home』は61年から66年までのディランの音楽活動を追った映画だが、はたしてここで歌われている歌はフォーク歌手の歌だろうか。これらの音源を耳にすると、そうした音楽ジャンルが本当に吹っ飛んでしまう。またこれが20歳に満たない人間のパフォーマンスであることにも驚く。甘さやつたなさなどみじんもない、激しさと氷つくような冷徹さが同居しているような演奏だ。
たった一言のことばでも心がふるえることがあるように、簡素なギターの音色とつぶやくような歌だけでも、心がかきむしられることがある。『No direction home』は61年から66年までのディランの音楽活動を追った映画だが、はたしてここで歌われている歌はフォーク歌手の歌だろうか。これらの音源を耳にすると、そうした音楽ジャンルが本当に吹っ飛んでしまう。またこれが20歳に満たない人間のパフォーマンスであることにも驚く。甘さやつたなさなどみじんもない、激しさと氷つくような冷徹さが同居しているような演奏だ。
まず耳をひくのはDisc1の5, 6曲目におさめられた61年演奏の「ミネソタ・ホテル・テープ音源」。当たり前だがデビューすらしていないディランの演奏だが、ここには単純なギターの音なのに恐ろしいほど攻撃的なにおいが漂ってくる。たとえ誰かのカバーだろうと、ディランがやってしまうとディランにしか聞こえない鬼気迫るものがある。特に6曲目のタイトルI was young when I left home。この曲の圧倒的な孤独感が胸をしめつける。ほとんど自分のテーマ曲にしたいほど素晴らしいパフォーマンスだと思う。
もちろんここにおさめられたオルタナティブ・バージョンもよい。「くよくよするなよ」、「風に吹かれて」、「戦争の親玉」などもともと名曲なんだけど、別バージョンを聞いてもそのクオリティには優劣がない。というかそもそもディランはもうどの曲がいいとか悪いのレベルではないのだ。その瞬間を凝縮させるパフォーマンスこそが彼の歌であり、歌の生命であり、それだからこそ、彼が演奏しているという事実そのものが、こちらを曲に正面から向かわせる。
瞬間が凝縮されているからだろう。彼のパフォーマンスには8分を越える曲が何曲もある。「はげしい雨が降る」(8:23)、「自由の鐘」(8:04 しかし何でこんな歌い方をするのだろうか...がなっているのか、大声張り上げているのか、でもその吐き出すような歌い方にぐっとくる)、「廃墟の街」に至っては11分を越えている。しかもギターソロがあるわけではなく、ひとつのメロディだけで延々と続いていくわけだが、時間の長さというか、時そのものを感じさせないほど濃密な歌なのだ。
そしてクレジット上はやはり8分を越える「ライク・ア・ローリングストーン」。観客との緊張感張りつめたやり取りはロック史上の一事件として有名だが、その後のディランの演奏が何もなかったかのように「冷静に熱い」のが、もうほとんど狂気に近いと思わせてしまうのだ。これが今からほとんど50年も前のものだとは思えないほど、熱気が伝わってくる。冷めて保存された遺物ではない。今でも私たちに刃物をつきつけるような鋭敏さをもって、50年前のディランは歌いかけてくるのだ。
 CD4枚+DVD1枚。ディスク・ユニオンの中古で2000円ちょっとで購入。DVDはオースティンでのライブだが、これは必見。どの曲もメンバーがはねている。とくにギターとベース。若いバンドの演奏って実にいいと感じさせてくれる。とにかくすばらしい。
CD4枚+DVD1枚。ディスク・ユニオンの中古で2000円ちょっとで購入。DVDはオースティンでのライブだが、これは必見。どの曲もメンバーがはねている。とくにギターとベース。若いバンドの演奏って実にいいと感じさせてくれる。とにかくすばらしい。
Disc2は前半が新宿JAMでのライブ。あの狭い空間で濃密な音楽が流れたかと思うと、感慨深い。一曲目Omoideはもったいぶったイントロが実にかっこよく、ドラムのロールからギターが入ってきてのっけから最高にスリリングなのだが、このテイクはドラムのバランスが大きいせいか、かなりストレートな曲に出来上がっている。解散直前にくらべれば曲のもつレンジがせまいけれども、ライブバンドとして卓越した技量をみせつける爽快さがこのテイクにはある。次の「大あたりの季節」もノイジーではあるが、いわゆるロックバンドの定式を抜け出しているわけではない。ライブバンドのノリだけで押し通してしまう若さがあるといおうか。いったいこのバンドはどれほどのスピードで円熟へと達してしまったのだろうか。
このdisc2を聞くと、演奏力だけでは歴史にならないことを強く感じる。このライブだけでは、Number Girlが日本のロック史に名を刻むバンドになったかどうかわからない。演奏だけではなく、いわゆるオーラのようなもの、唯一無二なものが生まれて初めて、歴史の中でこのバンドを考えることができる。解散時の圧倒的な存在感、何かが取り憑いたような存在感ではない。たとえば8曲目「日常を生きる少女」など、このテイクでは単調なタテノリで、性急で突っ込みがちだ。しかし「シブヤ」では、それだけではおさまらない幅がある。ヴォーカルが遠いといおうか、それでも曲として深まりがあるのだ。空気をつかんでひきのばしたような、それでいてはりつめた音の世界が広がってゆく。
Disc4は、裸のラリーズのように、ギターのエコーと、それがノイズとなって渦巻くところから曲が始まる。最高にかっこいい始まり方だ。この1曲目の「日常に生きる少女」から2曲目の「Omoide」へとつながるところも実にいい。Omoideは渋谷のライブ盤、そして札幌ラストコンサートのテイクの鬼気迫る「いってしまった」感にくらべると、こちらのテイクは、たたみかける「まともな」演奏だが、音の圧力はひけをとらない。
このdisc4のベストテイクはZazenbeats kemonostyle。もともとヴォーカルは叫びではなくうなりのようなものだが、この曲では吠えまくっている。サイケデリックなギターによる演奏が延々と続き、そこにひたすらヴォーカルがかぶってくるところ、この10分のノイズの渦巻きが圧巻だ。そのあとのeitht beaterもやたら攻撃的だ。もうこれ吠えまくりでほとんど歌になっていない・・・実にエフェクターの効き具合がたまらない。
で、disc1,4はまだ聞く時間がない・・・
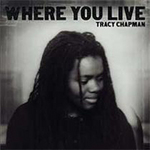 まず耳をうつのは、何年にもわたって使い込まれたと感じさせる、素朴だけれども味わいの深い楽器の音色だろうか。日本盤ライナーにあるように、プロデューサーのチャド・ブレイク、そしてレコーディングに参加しているミッチェル・フレームのコンビといえば、ロン・セクススミスでの仕事が思い浮かぶ。たとえば 5曲目、Never Yoursのアコースティック・ギターのエコー処理、同じリフが浮遊感をもってくりかえされるところなど、同じ空気を共有しているといってよいだろう。弦楽器の弦がゆっくり指ではじかれる響きや、パーカッションの鉢が太鼓の表面をかすめる響きが、丁寧に掬い取られて、やがて少しずつ消えていく、そんな一音のはかなさにまで気を使った音作りである。
まず耳をうつのは、何年にもわたって使い込まれたと感じさせる、素朴だけれども味わいの深い楽器の音色だろうか。日本盤ライナーにあるように、プロデューサーのチャド・ブレイク、そしてレコーディングに参加しているミッチェル・フレームのコンビといえば、ロン・セクススミスでの仕事が思い浮かぶ。たとえば 5曲目、Never Yoursのアコースティック・ギターのエコー処理、同じリフが浮遊感をもってくりかえされるところなど、同じ空気を共有しているといってよいだろう。弦楽器の弦がゆっくり指ではじかれる響きや、パーカッションの鉢が太鼓の表面をかすめる響きが、丁寧に掬い取られて、やがて少しずつ消えていく、そんな一音のはかなさにまで気を使った音作りである。
なかでも一番好きな曲は3曲目の3,000 milesだ。パーカッションの懐かしい響きから始まり、そこにトレーシー・チャップマンの声が重なる。さびのI'm 3,000 miles awayの誠実な歌い方が心をうつ。次のGoing Backもよい。とても淡々とした曲なのだが、そのゆっくりとしたリズムが、心を落ち着かせる。
トレーシー・チャップマンは88年にデビューしているので、今年で20年になる。こうしたミュージシャンが20年にわたって活動をし、7枚のレコードを出していることを考えるとき、アメリカの音楽の奥深さを感じないではいられない。もちろん、彼女が優秀なシンガーソングライターであることは間違いない。しかしそれでも、彼女の作品は、けっしてコマーシャルではないし、派手な社会的メッセージを全面に出す訳でもない。彼女にあるのは歌だけだ。しかしその歌には確信がある。ことばがひとを揺り動かす、そのフォークロックのスピリットがまだ、彼女には生き続けているようだ。そんな存在が、きちんと評価されて、コンスタントにアルバムを出せるアメリカとは、やはり文化の度量が広いと言わねばならない。
 あるレコード屋(死語!)の試聴機に、「洋楽ファンにもぜひ」と書いてあったので、早速試聴し、見事気に入ってしまった日本のミュージシャン。しかしその音楽は、洋楽とか日本とか、そうした国籍を消し去った雰囲気がある。the Guitar plus meは全編英語で歌っているが、だから洋楽っぽいというわけではない。むしろこうした種類の音作りが、今、世界のあらゆるところで様々なミュージシャンによって行なわれている気がする。趣味や、感性が日本も欧米もそんなに変わらなくなってきているし、日本にこだわって音楽を考える時代でももはやなくなってきている。みな最近の若い人たちは、軽々と国境を越えて、自由に自分の世界を表現しているように思う。
あるレコード屋(死語!)の試聴機に、「洋楽ファンにもぜひ」と書いてあったので、早速試聴し、見事気に入ってしまった日本のミュージシャン。しかしその音楽は、洋楽とか日本とか、そうした国籍を消し去った雰囲気がある。the Guitar plus meは全編英語で歌っているが、だから洋楽っぽいというわけではない。むしろこうした種類の音作りが、今、世界のあらゆるところで様々なミュージシャンによって行なわれている気がする。趣味や、感性が日本も欧米もそんなに変わらなくなってきているし、日本にこだわって音楽を考える時代でももはやなくなってきている。みな最近の若い人たちは、軽々と国境を越えて、自由に自分の世界を表現しているように思う。
the guitar plus meはミニアルバムも含めて5枚ほどアルバムを出していると思うが、どのアルバムも構成はほぼ同じである。無表情なうち込み、ときおりループする電子音と、アコースティックギターの音色がすべての曲調を作っている。
このアルバムのテーマは冬。小品が多い彼の作品の中では珍しく、1曲目Silver Snow, Shivering Soulは10分ほどもある長尺な曲である。でもこの曲の中で果てしなく続く、打ち込みと電子音のゆらぎがとてもすばらしい。ここまで人工的でありながら、ゆっくり舞い散る雪の自然の情景がとてもリアルに浮かんでくる。
どの曲もリズムは単調であるのだが、その曲、曲ごとにテーマがあって、微妙な曲調の違いがそのテーマを浮き立たせているのが楽しい。例えば4曲目はNew Year。新年を迎える時の浮き浮き感が伝わってきて、ちょっとした幸福を噛み締めることができる。
the guitar plus meの憎いところは、同じように見えても、この「テーマ」ということにとてもこだわってアルバムを作っている点である。動物のユーモラスな情景がうかぶZoo、水をテーマにしたWater Musicなど、音によるイメージの喚起がとても上手に作られている。
そう、職人の手仕事感といえばいいだろうか。それが一番よく感じられるのは、やはりアコースティック・ギターの音色である。パーカッションが作る音の空間を刻むようにしてギターの音がおかれていく。そんな構成美にとてもひかれる。そんな構成にとことんこだわったのは、2003年のTouch meだろう。ミニアルバムの5曲目Bakeryから6曲目Castleへの流れは、ギターの音は、チェンバロにも似て、バロック的な構成が見事に生かされている。特に5曲目の終わり、単純なリフを繰り返すギターの音色がだんだん大きくなっていき、突然途切れて終わるところで、僕は大きく息をついてしまう。
 CDで2枚組、原盤は18曲入りのアルバムである。といっても散漫な作りの曲は1曲もない。Ry CooderやJohn Hiattあたりの作品に敬意をはらいながらも、しかしそうした完成度の高さとは無縁でありたい、いつまでも未熟でありたいというロック的な激しい欲求が「オルタナ・カントリー」というような安易な呼称を斥けている。親しみのある思わず口ずさみたくなるメロディでありながら、しかしけっしてBGM的な心地よさへとリスナーを誘いはしない、正面切った叫びがこの作品をまさにロックのアルバムにしている。
CDで2枚組、原盤は18曲入りのアルバムである。といっても散漫な作りの曲は1曲もない。Ry CooderやJohn Hiattあたりの作品に敬意をはらいながらも、しかしそうした完成度の高さとは無縁でありたい、いつまでも未熟でありたいというロック的な激しい欲求が「オルタナ・カントリー」というような安易な呼称を斥けている。親しみのある思わず口ずさみたくなるメロディでありながら、しかしけっしてBGM的な心地よさへとリスナーを誘いはしない、正面切った叫びがこの作品をまさにロックのアルバムにしている。
曲はどれも、ひとひねり効いていて、単純な展開を許さない。たとえばCherry Laneは、ガレージバンド風な始まり方をするが、途中でささやかれるI can never get close enoughのリフレインはほとんど後期のフリードウッド・マックといってもよいセンチメンタルな曲調だ。しかしそんな展開もまったく無理なく聴かせてしまう曲作りの才能が彼にはある。
Goldはまさに青くて、胸がひりひりさせられるが、Cold Rosesはもう少し、自分に対する距離感が生まれているようだ。また演奏そのものも、バンドに対する信頼が、安定感を生んでいるのか、余裕が感じられる。もちろんGoldもよいアルバムなのだが、多少型にはまりすぎた曲もあるのに対して、Cold Rosesは、アルバムのトータルなイメージがきちんと作り込まれている。どの歌詞にもroseがちりばめられいて、ちょっときざなのも、かれの羞恥心の現れのような感じがしてとてもよい。
Ryan Adamsのヴォーカルは、Stan RidgwayやChris Isaakなど、憂愁を帯びた感じなのだが、センチメンタルな叙情には流されない激しさを持っている。それが彼のどのアルバムも生々しい感情を感じさせる理由だ。
60年代にBob Dylanの音楽が生まれ、70年代にはそれをBruce Springsteenが受け継いだ。どの時代にもその時代と対峙するボブ・ディランが必要ならば、00年代のディランはこのRyan Adamsだ。ファースト・ソロアルバムHeart Breakerの2曲目To be Youngの始まりは、完全にSubterranean Homesick Blues Farm、あるいはMaggie's Farmのそっくりコピーだが、これは単にディランへの憧憬ではない。ディラン程度のことなら、こんなに簡単にコピーしてしまえるという、Ryan Adamsの若々しい、不敵な決意の宣言だ。しかしその決意は、まさにHeart Breakerという言葉が表すように、傷を隠しきれないナイーブさと同居している。Dyranは70年代にはいってThe Bandと組む。Ryanも同じようにCardinalsというバックバンドとくんで、Cold Rosesなどのアルバムを作りあげることになる。それによって、たくましい土着のアメリカン・ロックをこの時代に謳いあげることに成功した。その骨太さがいかんなく発揮されたのがこのアルバムだと言える。
 このアルバムを聴くとちょっと驚くことがある。それは曽我部恵一の声が、とてもハスキーになっていることだ。ツアーのさなかで声が枯れてしまったのか?それとも彼の声は、シャウトするとこのようなしゃがれた感じになるのだろうか? 憂歌団というには、そこまで成熟していないというか、成熟を拒否しているか、どちらかなのだが、いずれにせよ、観客への挑発という点では、かなり魅惑的な声質だ。それは曲と曲の間に入れられている、しゃべりの部分でも同様だ。当日ライブの場に居合わせた観客はもちろん、このライブアルバムを聴く者さえ、どんどん音楽のなかに引き込んでいく。
このアルバムを聴くとちょっと驚くことがある。それは曽我部恵一の声が、とてもハスキーになっていることだ。ツアーのさなかで声が枯れてしまったのか?それとも彼の声は、シャウトするとこのようなしゃがれた感じになるのだろうか? 憂歌団というには、そこまで成熟していないというか、成熟を拒否しているか、どちらかなのだが、いずれにせよ、観客への挑発という点では、かなり魅惑的な声質だ。それは曲と曲の間に入れられている、しゃべりの部分でも同様だ。当日ライブの場に居合わせた観客はもちろん、このライブアルバムを聴く者さえ、どんどん音楽のなかに引き込んでいく。
サニーディ・サービスのころには、こんなしゃがれた声を聞くことはなかった。「東京」のクレジットに記された吉井勇という詩人の名が示すように、とても内省的で、叙情的な詩にふさわしい声。「江ノ島」に歌われる、ゆるやかなカーブ、平日の昼間の海といった、静謐さを歌うのにふさわしい声、それが曽我部恵一の声だったと思う。でもこのライブアルバムでは、たとえば「浜辺」のような、グルーブたゆたう曲でさえ、彼の声は枯れて、震えている。
そんな声質の違いが、サニーディ・サービスとソロになってからの彼の音楽の違いなのだと思うが、それでも変わらないところはいっぱいある。それはたとえば、「恋の始まり」。曽我部恵一ほど、「恋の始まり」を素敵にスケッチしてくれるミュージシャンもいないのはないだろうか。「恋に落ちたら」は、今日のデートで、おそらく二人は、お互いがすきだってことを感じるはず、だから、今家をでて、デートに向かう「僕」の心を歌う。「テレフォン・ラブ」は、相手が見えないのに、声だけは耳に生々しくすぐ近く聞こえてくる、「電話」。それはいざとなれば真夜中だって彼女の声がきけるのに、でもダイヤル(!)するには、とっても勇気がいる、そんな「恋」を歌ってくれる。
ちなみにこのアルバムの名義は「曽我部恵一Band」である。Bandってなんだろうか?それはアンサンブルなんだけど、それぞれのパートが勝手に自己主張するグループのことではないだろうか。そんな緊張感をここちよく感じながら、一気につっぱしって聴いてしまえる、イカしたライブアルバムである。
 80年代に結成されたバンドはどんな音楽を志向しようと活動を始めたのか。パンクやニューウェーブといったアメリカ、イギリスのロックは、様式美から隔たった地点で、そして社会を変革することができるという意気込みからは遠ざかった地点で、自分の日常を見つめ直し、その日常自体も、そして生活の中での鬱屈とした不機嫌さえ表現の原点となると認識した時点で始まったのではないか。
80年代に結成されたバンドはどんな音楽を志向しようと活動を始めたのか。パンクやニューウェーブといったアメリカ、イギリスのロックは、様式美から隔たった地点で、そして社会を変革することができるという意気込みからは遠ざかった地点で、自分の日常を見つめ直し、その日常自体も、そして生活の中での鬱屈とした不機嫌さえ表現の原点となると認識した時点で始まったのではないか。